HPのUP:2014年03月25日

旬報社は今秋創立65周年を迎える。小社をご指導いただいた故沼田稲次郎先生は、『労働法律旬報』誌上において健筆を振るわれ100本を超える論文を発表されるとともに、『著作集』全10巻を含め20冊余の単行本を刊行された。ここに「沼田稲次郎著作目録――人と学問の歩み」を掲載し、労働運動・社会運動とともに歩んでこられた研究の足跡を、先生の人間としての歩み、先生の思想の成熟と交錯させながら、あとづけることができたらと思う。
沼田稲次郎・書に序す――団結と平和と人間の尊厳とお知らせ
目 次
1 現地をまわりて(『英雄なき113日の闘い』労働法律旬報社刊、1954年)
2 闘魂と団結のモラル(『みいけ20年』労働旬報社刊、1967年)
3 現代の罪と罰(『歴史の告発書』労働旬報社刊、1967年)
4 平和を売る政治(『日本の黒書』労働旬報社刊、1967年)
5 批判力と憤りとの結合を(『未来を語りつづけて』労働旬報社刊、1969年)
6 運動の火をつぐ科学的作業(『抵抗の歴史』労働旬報社刊、1969年)
7 この道をすてず(『明けない夜はない』労働旬報社刊、1969年)
8 「マル生」闘争の真価(『国鉄マル生闘争資料集』労働旬報社刊、1979年)
9 平和への執念こそ原点(『平和教育実践事典』労働旬報社刊、1981年)
10 由々しき問題なればこそ(『警察の盗聴を裁く』労働旬報社刊、1988年)
私が帰途につく前夜、札幌の宿舎に三井美唄労組の組織部長の訪問をうけて、美唄も亦砂川と同様に闘争力が、高揚していることを知らせられた。どちらかというとわが国の組合は解雇反対闘争には弱い傾向があり、闘う炭闘でも必ずしも例外ではあるまいと思われていた。私自身も企闘(企業整備反対闘争)には多少弱気の見透しをもっていたが、希望退職者募集と指名解雇勧告という二本建の狡猾な首切り方法を何とか団結力をもって克服する組合があるとすれば三鉱連はその中枢組合の一つとなるにちがいない、という感じを北海道の旅でもたらせられたのであった。その後“三井独走”の声をきいた。然るに三鉱連は「英雄なき113日の闘争」によって英雄的勝利を闘いとったのであった。大いなる“独走”であった。いな、“独走”を支援しながら、日本の組合は三鉱連と共に走っていたのである。独走の勝利は三鉱連の勝利であると共に、炭労や総評の勝利でなければならない。労働運動というものはどの一隅における闘争も全体にかかわり、一組合の勝利も全体の前進の一歩となる。況や三井独占資本に対する三鉱連四万余の組織の闘争においておやである。私は今年の3月三池労組の組合員諸君や炭婦協の方達と職場や社宅で親しくお話しする機会を与へられたが、そのとき山の人達の間に、組合の力と指導とに対する信頼感や自分達の行動力に対する自信とがみなぎっているのが深く感ぜられた。企闘における長期の団結行動とそれによって捷ちとられた勝利とが、いかに山の人達の連帯意識を高めたかを確め得たように思う。職制から睨まれることよりも組合を裏切ることを恐れるという階級的なモラルが打ち立てられてきている。企闘の政治的経済的意義や戦術、組織、行動における卓越性についてはもとより、その間に練り上げた階級的モラルにおいても、この「英雄なき闘争」は巨大な足跡であった。この成果は貴重な社会的実践であり統べての労働者のものにしなければならない。
三鉱連がこの度、忙がしい闘争のうちにあって腰を落ちつけて企闘白書を作られた努力には心から敬意を表すと共に喜びに堪えない。全組合員とその家族との長期にわたる闘争の記録と、真剣な実践のうちから組合員が謙虚に反省した自己批判とを整理されたのがこの白書である。組合はつねに労働運動史から実践的な教訓を学びながら、創造的な闘争を重ねてゆく。闘争の記録は過去のものではなく、まさに現在の闘争のうちに生きるものである。戦後わが国の組合は企業別組織形態が支配的であって、特殊的な問題を少なからず含んでいるのである。かかる組織形態における闘争は外国の組合運動史からも、また、現在の外国の労働運動からも直ちには移入しがたい特殊な方法を要請することもあるにちがいない。この戦後的現実においてわが国の組合が行った闘争の足跡こそ直接的につぎの闘争に生きた智慧と血の通った戦術とを与える給源に他ならない。企闘白書の価値は極めて高いと信ずる。
(全国三井炭鉱労働組合連合会編『英雄なき113日の闘い』、1954年)
 |
みいけ20年 三池炭鉱労働組合編 判型A5上製 ページ数1128 発行日:1967年01月 |
三池労組20年史が刊行せられることは、私に感激を覚えさせるのです。労働者の不屈の闘魂を堅持しつづけてきた三池労組が、向坂先生やその学統につらなる良心的な、そして三池労組と深い縁に結ばれた学者たちの協力をえて、その闘いの足跡を印刷に付するということは、労働運動の前進にとって価値のあることだと思います。それは、組織運営上の経験や戦略戦術上の教訓の宝庫であるからというだけではありません。むしろひとは三池労組の闘争史において、階級闘争の実相を見、労働者の階級的根性のすばらしい発揚と団結のモラルに血の通っている美しさとに心動かされ、みずから社会的実践の正しい姿勢を自覚するだろうからです。三池労組、その組合員ならびにその家族の踏みこえきたった20年の歴史、わけても昭和28年の企業整備反対闘争の勝利を闘いとった大衆行動以来、創造的な闘争によって炭労いな総評の闘争に大きな寄与をなし、職場闘争にも超企業的連帯活動にも精力的に犠牲をいとわず闘ってきた足跡、さらに昭和35年の大闘争とその後の眼を覆いたくなる会社側の切崩し、差別待遇、兵糧攻めまでの反組合戦術に堪えぬき、かの三川鉱の炭塵爆発に際しては、脱落者集団の遺族のためにも闘争を組織するといったこの英雄的な闘争の5年間、この歴史の激流を思いうかべるだけで私は心の引きしまるのを覚えるのです。そしていまその記録が刊行せられ、そしてこのように皆さんに語りかける機会を与えていただいたということは全く感激のほかありません。この組合、この組合員そしてこの家族の人たちが私を友人とみて下さることに私は喜びと光栄とそして重い責任とをひしひしと感じております。
私が東京に定着するようになって間もなく親しくなった組合の一つは炭労であります。物覚えが悪く、しかも日記もつけていないのではっきりはいえませんが、その後、昭和27年の秋頃でしょうか、宮川組合長ほかの執行部の5、6名の人たちが、たしか九州地方の豪雨のあと出水のまだ治らないときに川をこえて上京され、上野の韻松亭で、学者や弁護士の若干と会談されたときに、はじめて私は三池労組にお目にかかったと思います。あのときは、組合は社宅にまでおよぶ会社の妨害を排して炭婦協の結成に努力せられていたときで、不当労働行為の法律論が問題になっていました。組合員やその家族の多くの人たちをお訪ねしたのは昭和29年の春でした。時あたかも「英雄なき闘争」の勝利のあとで意気すこぶる盛んでした。団結の力は社宅のすみずみにまで意識せられていました。「何て、うす気味の悪りイ! あやつどんが、おッどんたち鉱員に、やぁたらニタニタするごつなったこん頃のかっこう」(三鉱連編『英雄なき113日の闘い』の末尾の詩より)がいい気持ちで語られていた頃でした。私はいくらか不安を覚えたほどでした。というのは独占資本がこれほど強力な組合を野放しにしておくはずはない、きっと隙あれば斬りこもうとするだろうという気がしたからです。そしてその不安は7年後、石炭産業合理化推進の第一前提として独占資本が三池労組に対するすさまじい攻撃を加えてきたとき現実のものとなりました。この昭和35年の大闘争の勝敗は第二組合への脱落を阻止できるかどうかに大きくかかわっていたと思います。もとより他の事情も相互にからみながらこの闘争の成否を規定しておりましたが、脱落集団が第二組合を作ってはなれるかどうかという時点は一つの危機であったと思います。そのとき私は脱落しないように念じながら社宅で組合員や炭婦協の人びとに一所懸命話しかけていました。闘争委員会に顔を出したこともありますが、そのとき集まっていた幹部のなかからさえ、――しかも私の久しく知っている人まで――脱落者が出たことをあとで知ったときの悲憤は、忘れたいと思うが忘れられないのです。スクラムを組んでいた仲間が翌日はピケ・ラインに躍りかかってくるのを体験せられた皆さんの苦悩は察するにあまりあります。
大闘争のあと、二度ばかり三池労組をお訪ねしました。そして、会社の三池労組組合員にたいする差別的不利益取扱いの非人道的なやり口をつぶさにうけたまわりました。日常の職場で、びしびしいためつけられるのを堪えることは並大抵のことではありません。この段階で崩れた人たち――長期のストをホッパーの闘いまで一しょにスクラムを組んできた人びとです。生涯得がたい友人だろうと思います。スト中に脱落したのとはちがっていると思っています――を、あまりきびしく非難することは私にはできません。とはいえ、それを堪え忍んで団結を守りぬいている三池労組の組合員に足をむけてねる資格はあるまいと思っています。大闘争を知る人でも、この陰惨な職場での差別待遇との闘いを知らない人が少なくないでしょう。だが、この闘争にこそ三池労組の真髄を見ることができると私は考えています。本書の第1部第4章はかみしめて読まねばならぬと思います。大闘争に結集した闘魂が、ここでも燃えつづけているのです。正直にいって今日では三池労組は労働運動をひっぱってゆくような大組合ではありません。またそれができるような環境でもありません。石炭合理化の嵐はなお去っていません。しかし、日本の労働組合における団結の真義如何、と問われれば、第一に指すべきは三池労組でありましょう。また、日本の労働者の階級的土性骨を見せろ、といわれればやはり三池労組の組合員にまず登場ねがわねばなりますまい。日本の労働運動の良心の灯をかかげ、精神的には先頭を切っている戦列には、いまもなお三池労組が毅然として立っているといわねばなりません。
こうして筆をとっている間にも、宮川、灰原、塚本、久保田その他の友人たちのそれぞれ個性ある顔、炭婦協のピチピチした婦人たちとそのまわりをはねまわっている子供たち、子供たちといえば、113日の闘争のあと社宅を訪ねたときに「民族独立行動隊」の歌か何かをうたっていた子供たち、そしてその一人の子供の父親から、闘争中両親も子供たちまでもデモに参加したのは教育上悪くなかったか、ときかれて、北支戦線で子供が日本軍来攻にそなえて村はずれの廟で歩哨に立っていたのを見た私の経験を話し、あの子供たちがいま中国の建設をやっているのでしょう、と答え、そのあとに両親と共に誇りうる行動に参加したという思い出はいつまでも教育的作用をもつでしょう、とつけ加えた、そのようなさまざまな印象が尽きせず眼底に浮かんできます。その子供たちはもう働き盛りでしょうが、きっといろんな職場で仲間に「英雄なき闘争」の思い出を胸をはって話していることでしょう。また申すも悲しいことですが、打ち消し得ないのは三川鉱の炭塵爆発の犠牲者の方たちへのやるせない気持であります。三池労組はあくまでもこの人びとを守ってあげて下さるよう切望いたします。
貿易自由化の下に、さらに資本の自由化をむかえて日本の独占資本陣営はあわただしく動いております。それに対応すべき労働組合の闘争は容易ではありません。組織上も運動上もさまざまな困難が予想せられます。三池労組がその30年史を書く頃には、また多くの闘いがつみ重ねられ、労働者団結のモラルの軌道が一層鮮やかに敷かれていることでしょう。そして三池労組がつねに日本の労働運動に対して不屈の闘魂と団結のうるわしきものを示し、この国のファースト・ユニオンとしての役割を営まれるように期待してやみません。
(三池炭鉱労働組合編『みいけ20年』、1967年)
 |
歴史の告発書 戦争犯罪調査日本委編 判型A5並製 ページ数157 発行日:1967年01月 |
日本の人民の50歳前後から上の年代者は、軍閥、ファシスト、独占資本のひきおこした満州事変以後の侵略戦争をどの段階においても無抵抗に見送ってしまったことに悔恨を感じ、アジアの被侵略国に対していつか償わねばならぬ負い目を意識している筈である。
ベトナム人民に対するアメリカ軍の言語に絶する残酷非道の暴行はまぎれもない犯罪であり、ベトナム民主共和国に対する無頼漢的無法な空爆と人民の殺傷も国際法廷によって罰せられるに値する攻撃にほかならぬ。このアメリカ帝国主義の悪魔の業に対する怒りと憤りとがむらむらと湧きおこらないとすれば、それは自らが悪魔の族であるからだ。人類の一人として、人間として、この戦争犯罪は裁かるべきだ、いな人間が自らの手によってそれを裁くべき法廷を国際的に創立すべきだと叫ばずにいられない。そしていまその法廷が創設せられつつあるのだ。戦犯裁判は現行犯についてなされた方がよい。
アメリカ帝国主義国家の強力な侵略軍に対するベトナム人民の英雄的戦闘は感激と胸をしめつけられる思いとを私に与えている。この抵抗と苦闘の貴重さは限りないものだ。民族としてその独立と自由のために死を賭するベトナム人民の偉大なたたかいを支援すること自体が、人類にとって絶対的に価値ある活動でなければならぬ。その意義を世界が自覚することによって20世紀の世界は永遠の生命をもつ。ベトナム人民のたたかいを支援して独立と自由とを勝利せしめ正義の貫徹を実証しうるかどうかが、いま20世紀の人類の良心に課せられた実践的課題でなければならぬ。そして私は、それが実現せられうる課題だと信じている。何故ならば、それは世界史的に必然なるものを自覚することによって自主的に、つまり自由に自かに課したものであり、それによって歴史の迂路をちぢめ、人類発展の歩度を早めようとする意味をもつものだからである。ベトナム人民の反帝独立の死闘を支援――それ自体が闘争を避けがたいことだ――する世界的な活動に積極的に参加することは、50歳年代の日本人にとって、またその一人である私にとっても、過去の無抵抗の負いめを償うチャンスであると思われるのだ。
アメリカ帝国主義国家の支配階級の戦争犯罪は実に今にはじまったことではない。第二次大戦において日本の降伏が必至であり、本土上空は完全にアメリカ空軍に支配されていた段階において、日本の無辜の人民の頭上に――太平洋上でも瀬戸内海の上でもなく、まさに広島、長崎の両都市の上空で――原爆を投下したのはアメリカ軍であり、トルーマン大統領がそれを許したのである。戦後日本の戦争犯罪者は文明と正義の名において訴追せられた。それはそれでよいことだ。戦争や侵略の犯罪性を明確ならしめて好戦的な支配者たちに警告し、さらには戦争といえども個人の非人道的な行為の犯罪性を阻却せず個人の責任を阻却しないことを国際法廷で明示し、歴史的文書に刻みこんだということは、それによって人類社会が平和を確立することができるならば良いことである。それはファシズム戦争にこりごりした人類の良心と知慧とが見出した平和と正義を守る国際政治的な方途であったといえよう。だが、戦後の国際法廷は、アメリカの犯した無抵抗の人民に対するジェノサイドの罪という最大の戦争犯罪について、犯罪責任者を訴追するという正義と衡平との府たるべき法廷にとって最も重要な責任を果たさないでおわったのである。もとより真珠湾の不法爆撃や侵略戦争によって手のよごれた日本の支配階級はその不公平と反正義とについて国際法廷を責める資格はなかったかもしれない。だが、日本の人民にはその資格があったのであり、いまもあるのである。
ベトナムにおけるアメリカの戦争犯罪を訴追する国際法廷がいま準備されつつある。この法廷は世界で最強の軍事力と経済力とを有する帝国主義国家の大統領をも含めて被告席に立たせようとする法廷なのである。それは、いわゆる「力の裁き」の性格を払拭して、正義と人道と平和と自由と独立と、つまり人類が数千年の歴史のなかでみがきあげてきた至上の価値の視点に立つ裁きを行うに値する法廷でなければならない。もとより力の存しないところに裁きはありえない。だが、その力は価値に対立して語られる力ではなくて、価値を志向する世界各国の人民の力であり、武器なき力である。いいかえれば世界史を貫く理性的なるものあるいは必然的なるものの世界的自覚の力にほかならないのである。このような国際法廷によって下される断罪こそ、いうなれば神の裁きである。永遠にゆるされることのない――再評価されることのない――そういう最終の裁判がそこでは下されることになろう。
直視に堪えがたい写真の示しているように、ベトナム人民に対する残酷な殺りく虐待無謀極まる爆撃など、人間を虫けらのようにふみつぶすアメリカ侵略軍のやり方というものは、果たして帝国主義的侵略にとって不可避の宿命なのであろうか。ヒットラーのアウシュビッツは彼の狂気にのみ帰せられようか。ヒットラー以上といわれるアメリカ侵略軍の暴虐残虐はアメリカ帝国主義の狂気に憑かれた支配階級とその代弁者たる政治家軍人の狂気なのであろうか。もし人間を虫けらのように殺すことが帝国主義の宿命的狂気だとすれば、人類は帝国主義を弔り去るほかあるまい。そして地上から帝国主義が消失するまで、この国際的戦犯法廷は常設せられねばなるまい。
(ベトナムにおける戦争犯罪調査日本委員会編『歴史の告発書』、1967年)
 |
日本の黒書 日本平和委員会編 判型A5並製 ページ数205 発行日:1967年05月 |
このように書評の如き書き方をするのは、実は率直にいって私は本書については読者の一人でこそあれ、執筆者の側に立てるような研究をしているわけでもなく、戦略戦術を論ずる力はもとより持ち合せているわけでもないからである。ただ本書の原稿の段階で一歩早く読んだ国民の一人として、われらが時代の越し方ゆくすえを思いめぐらしながら、所見をのべるに過ぎないのである。執筆の機会を与えられて、それを避けてはならないと私が考えをきめたのは、本書の迫力にもよることだが、さらに最近、国土地理院が日本の軍用地図を米軍に渡しているという記事(毎日新聞、5月10日付)を見、この問題についての政府の議会答弁を読むにいたって、決定的になった。この事実を本書に加えるべきだと思ったのと、「悲憤の筆もて警鐘を打たむ」という感慨を深くしたからである。
「建設省国土地理院は米軍の要請によって、ひそかに旧日本陸軍の参謀本部さえも作らなかったような特殊な軍用地図を三十五年から五ヶ年計画で作成、米軍に渡すとともに、ひきつづき現在まで各種の測定資料を提供しつづけている。井上英二国土地理院測図部長は、“すべては金のためといえる。……”というが……」(前掲毎日紙による)。
同紙の記事によれば、日本占領中独自の手で日本の軍用地図をつくっていた米陸軍極東地図局が講和後に防衛庁に作業を委託しようとしたが、同庁にその能力がないので、「白羽の矢を国土地理院に立てた」という。
二重スパイのような売国奴はあまり珍しい現象ではないが、「独立国」の政府が組織的に国土の地図を売るほどの堕落あるいは政治的痴呆の減少は稀有のものだろうと思う。アメリカ軍が占領中独自の手で旧敵国――長恨をのんで降伏した好戦的支配者が依然政権をにぎっている日本なのだからなおさら――の兵要地誌をしらべるのはむしろ当然のことである。また講和の成立してない時期に強要せられて一定の資料の提供をなさざるをえない立場に日本の政府が立った場合に、控え目に資料の提供をしたからといって敢えて責めようとも思わない。もっとも降伏の「玉音放送」のあと、占領軍の進駐までに日本軍がいかに多くの軍事資料を焼却したかを思えば――戦後追及を予想して証拠物件を破棄しただけのものではあるまい――、占領中といえども要心深くてよかったといえようか。
しかし、ともかくも「独立」してから、旧敵国に自国の軍用地図を売り渡しているというのは、馬鹿か悪者か、いずれにせよ最低の政府である。それともアメリカ本土の軍用地図と交換しているのか。かつて岸首相が訪米してアイゼンハワー大統領とゴルフをやり、一しょに裸でシャウァーを浴びたように、お互いに国土の秘密をかなぐりすてて、裸を見せ合っているとでもいうのか。アメリカといわず、世界中の国に、そんな馬鹿な破廉恥なことに応ずる政治家はいるはずがない。たとえ軍事同盟を結んでいる国の間においても、共通の敵国について情報交換はするかもしれないが、自国の軍用地図の交換をするはずはない。日米支配階級の間には軍事同盟の如きものが存しているのだろうが、もとよりアメリカへの従属にほかならぬ。南ベトナムのキ政権の如く、日本の支配者たちも対米従属を望むのであろう。彼らは民族の矜持や国民大衆の生活と平和をすてても、独占資本の眼前の利益と権力の座とを守るために危険な核兵器の傘の下に、アメリカの支配の下に入ることを欲している。しかし、日本の被支配階級たる勤労大衆はあらゆる従属を否定する。それが国民の意思だ。
ところが、この問題についての矢山代議士の追及に答えて増田防衛庁長官は、「共同防衛の建前上米国が(こうしたことを=地理を)知っていることは政治上しかるべきことだ」と答え、佐藤首相は「日米安保体制上(このような地図作成は)やむをえない。」(いずれも毎日新聞5月10日夕刊)と答えている(参院予算委員会)。
「共同防衛の建前上」というが、一体誰に対して共同防衛するというのか。仮想敵国というものが日本国土に侵略したとき、あるいは悪政に抗して日本の勤労大衆が蜂起したとき(これも仮想敵国か)日本の支配者たちは米軍機によっていち早く家族ともどもアメリカへ待避し、アメリカ本土や太平洋上から核弾頭のミサイルを日本国土に――国土地理院の作成した精密な軍用地図によって――正確な射程でとばそうとでもいうのか。それしか考えられないではないか。まさかダイヤや蛇の目石だけをもって亡命するわけでもないとすれば、スイスかウォール街の銀行に預金でもあるのかもしれない。安保条約によってそこまでの――軍用地図を作って売るまでの――義務を負うていると解すべきかどうかは疑問だと思うが、もしそのように解釈運営せられているとすれば、そのような条約を締結したもの、その存続を願う者とは一体何者ぞや。
本書をみればわかるように、そもそも安保体制というのは狂っているのである。他国の戦略基地――“透明の壁”を含めて――を一方的義務として自国内に置いてそれによって戦争の片棒をかつぐなどということ――現にベトナム侵略戦に加担しており、ますます深みに入りつつあるのだ――は、戦争を放棄している国の政治家にはゆるさるべきことではない。それは誇りを持して平和に生きようとする国民の念願を裏切るものである。日本政治史上未曾有の堕落にほかならぬ。日本は、戦雲のなかにも知性と道徳をもって世界の平和を愛する人民に信頼しつつ毅然としてわが道をゆく決意をしたことを思うべきである。その途に進むべきである。帝国主義によってその途を進むを得ないならば、帝国主義を捨てるべきであり、平和をすてるべきではない。それでも平和を売る政治が強行せられるというならば国民はこれと闘うほかはない。ワシントンと東京とベトナムを結ぶキナ臭い硝煙と血の線は早くたち切らねばならぬ。ほっておけばそれは北朝鮮や中国にも延長される不吉な線となるかも知れない。この線を断ちきる闘いは、ベトナムにおいてはもとより、アメリカ本土においても行われており、日本の民主勢力もその闘いに参加している。その陣営は現存しているのであり、さらに世界中に深く根をおろしてゆくであろう。それは、侵略を打ち破ることによって帝国主義そのものを止揚する世界史的な役割を担う陣営にほかならない。まさに現在の課題である安保条約破棄、基地撤退、ベトナム侵略反対のための闘争とこの陣営の強化に主体的に参加することこそ日本国民が自らを破滅から救う唯一の途であるとともに、真に民族の誇りでなければならぬ。それは、平和のために努力する国際社会において名誉ある地位を占めたい、とする日本国憲法に示された念願(憲法・前文)を実現すべき国民的義務であるというだけではなく、世界史上に日本人民の輝かしい足跡を打刻する所以でもあろう。もとよりそれは犠牲の多い闘いではあろうが、軍事基地を認め、国土の軍用地図を売っている今日の状況のもたらすものを洞察しなければならない。
私は満州事変以後、日支戦争からさらに太平洋戦争へと向った時代に生きた人々がその闘いの犠牲が悲しむべき必要であり、しかし価値ある闘いであることを――もし自己をいつわる気の弱さを克服するならば――深い悔悟とともに痛感していると思っている。私をも含めてこの時代を体験した人々は、いま何よりも、現在の反戦平和の闘争の緊要性とその高い価値の自覚を国民大衆に普及しなければならないのではないだろうか。そして、太平洋戦争下に生きながらえてきた自己の生涯をふりかえりみ、アジアの民族に与え、また国民自らのうけた戦禍をいたみつつ、何をなすべきかを考えるべきであろう。もとより今日の政治現象は、思想や主義と不可分のものである。だが、真実はさまざまな虚偽のイデオロギーを破って自らを提示しているではないか。
(日本平和委員会編『日本の黒書』、1967年)
 |
未来を語りつづけて 広島県原爆被爆教師の会 判型A5並製 ページ数325 発行日:1969年08月 |
戦後世界の指導権を握るために、武装なく、ひたすらに平和を希求していた罪なき日本の市民の頭上に原爆を投下したアメリカの支配階級に対する終りなき憎悪と非難と、暴力的に国民を戦争にかり立てた日本軍閥に対する憤慨と、戦争に向う政治に対する人民の抵抗のあまりに弱かりしことへの無限の悔恨と、わが兄と嫂とを含めて広島市民のうけた悲惨へのやるせなさとに破れんとする胸に堪えながら、私は、はるかに深刻な苦悩と悲しみに堪えてこの原稿を書き綴った人たちの決心に動かされて、ともかくも本書を読み切ったのであった。
野戦から帰還して下呂の陸軍病院にいたとき私は原爆の報に接した。敗戦後、金沢の部隊に属していた私は、嫂を爆心地――彼女は勤労奉仕にかり出されていたのだ――に喪い、自分は負傷して辛うじて生きのびていた兄の切々たる手紙をみて、9月広島に向ったが尾道あたりで止められてしまった。10月の初旬、ふたたび広島へ向い、五日市から電車で20分位のところに仮寓して病床にあった兄にめぐり逢った。広島は惨とした廃墟であった。兄は翌昭和21年夏、京都にあった私の寓居にころがりこんだが、その夏、府立医大で不帰の客となった。この悲しみに堪えていた老父は翌22年の遅春に亡くなった。
社会にひとりほうり出された私は、そしてやがて妻も、ささやかながら反戦平和・反ファシズムの闘争に加わってきた。だが、広島にゆくことに躊躇を感じていた。おそらく悲憤に堪えられないと潜在的に感じていたからであろう。もとより幾度か広島を通ったし、その空をとんだ。瞑黙して被災者に祈りを捧げ、反戦・反ファッショの闘いの誓いを新たにした。
今年の2月に、私は菩提を弔いに広島に出かけた。そして本書の企画を知ったのであった。
私は広島に着いて広島の復興に驚かされた。あの廃墟は消え去って、大都市が築かれていたのである。しかし、鳩の飛ぶ原爆記念館からひとり街々を歩いて、処々の悲しい碑をみていると、この復興の都市の底にかぎりない悲しみが漂い、無言の抗議の渦捲いていることをひしひしと感じないではいられなかった。身を捨てて守り通さなければならない価値、平和と人生の価値を胸苦しいまでに感じさせられたのである。
読者よ、本書をつぶさに読まれたい、読めば、私たちが身を捨てて守るべき人の世の至上の価値の何物たるかが真実にわかるだろう。また身を捨てて闘うべき時機を洞察することができよう。
広島の復興はたしかに人間の逞しさを示すものだ。この逞しさが、数千年の闇い歴史を生きぬいて今日の文明をきずき、人間の優位を打ちたてた原動力にほかならない。そしてこの力は時間の魔法のなかで、動物的なおそれと怒りとを忘却せしめるものであるかもしれない。げんに、「被爆教師のかくれ切支丹的な努力」にもかかわらず、広島市および周辺の5中学校生徒を対象とする調査は、原爆投下をした国がアメリカだと答えられない者が10%前後もいること、原子爆弾は「カッコイイ」と考えている者が10%前後もいること、を物語っている。この調査を分析した教師は「広島に近づくほど“ひろしま”は知られていない」といい、あるいは「広島の子にしてこの状況であるから、まして全国的にはもっと“ひろしま”は知られないだろう」(本書11頁)ともいう。
おそらくこういうことではあるまいか。骨髄のなかにまで爆影を刻みこまれた広島市民の子弟が「ひろしま」を忘れるはずはないのだ、ただあまりに惨たる体験が父兄をして、「ひろしま」を忘れる努力をさせ、復興の希望を子どもたちに与えようとせしめているのではないだろうか。広島の子どもたちが、「ひろしま」を「知る」ことの深刻さは、全国の子どもたちがそれを知ることとは比較にならないのではないか。「知る」ことのちがいが分析されれば右の相反する分析のいずれもが同じことを示していることがわかると思う。広島の子どもたちはやがては必ず「ひろしま」を知るにちがいない。
教師の課題は、忘却の淵から過去の悲惨な運命の涙だけをすくいあげさせるのではなくて、そこから人間の憤りをたぎらせた現在の闘志の泉を湧き出させるのでなければならない。
昭和41年に広島、佐世保、福島、札幌の高校生それぞれ100名について行った調査によると(本書207頁及び230頁以下)、「アメリカが原爆を投下したことについてどう感じますか」という問いに対して、「A・理由がどうあったにしても原爆の使用は人道上許されない。」「B・戦争だから仕方がなかった。」「C・戦争を早く終結させるために必要だった。」の三つの回答が、広島と広島以外の生徒たちによってつぎのようになされている。すなわち、広島では、Aは60.8%、Bは25.7%、Cは13%であり、広島以外では、Aは64.3%、Bが22%、Cが10.7%である。この数字に私はがく然とした。広島の高校生の約39%(BとCの回答計)が憤りを失いつつあるのではないか、広島以外の高校生よりもより一層に挫折感があるのではないだろうか、と思われたからである。
もとより原爆は戦争悪の極致である。帝国主義戦争においては、市民の大量殺戮を伴うことは、アメリカのベトナム侵略において現在もなお見せつけられている事実である。しかも核戦争の脅威すら現実のものとして語られている。されば反戦の闘いこそ決定的に緊要なのである。戦争が政治の一形態であってみれば、戦争に向かう政治の性格を洞見して、これと闘うことなしには戦争を防止しえないのである。そしてかかる闘いは平和を志す日常的な闘いの広い底辺によって固められねばならないとともに、「原爆ゆるすまじ」という道義的な憤りをこめた抗議の決意のなかに鋭く打ち出される主体的運動によって推進せられねばならないのである。
広島への原爆投下は、戦争だから仕方がなかったわけでもなければ、戦争終結をとくに早めたわけでもなく、アメリカが戦後世界の指導権を握るための鬼畜の業であったことはいうまでもあるまい。にもかかわらず、原爆投下の理由を問うて、「戦争をしていたから」という答えを正解とする教育(174頁)が行われているとすれば、抽象的命題をかかげて主体的な平和運動をよび起こすような真実を隠蔽するものである。教科書も「ひろしま」をさけている(189頁以下)。それゆえにこそ「ひろしま」は現在の私たちの課題なのである。広島の先生たちが、生徒が批判力と、正しい歴史観をもつように教育する決意をもっておられることを本書によって見ることができる。その決意こそ、「ひろしま」の投げかける課題に答えるものである。
正しい歴史観に立つ批判力の涵養は、福祉国家などのイデオロギーにかかわらず、今日の権力的政治の方向が戦争への道にあること、わだつみ像を破壊する者どもの行動や一般にみられる暴力への不感症の傾向が、権力の政治とからみつく可能性を洞察させるにちがいない。だが、さらに願わくは根源的な人間の憤りと闘魂とを批判的と結合せしめる教育につとめていただきたい。
原爆ゆるすまじ、と叫ぶ青年こそ、ベトナム侵略許さずと憤り、安保条約撤廃を闘う青年であり、このような青年たちこそ、基本的人権を、平和を、民族の尊厳を未来にわたって担ってゆくものと信じて疑わない。日本の教育の原点はそこにある。
本書を世におくってくれた人びとに心から敬意を表するとともに、近来最も感銘をうけた迫力ある書物であることを述べずにはいられない。
(広島県教組・広島被爆教師の会編『未来を語りつづけて』、1969年)
6 運動の火をつぐ科学的作業
この書物は、昭和8年2月4日払暁、諏訪・上伊那・長野・上田など2市5郡下にはじまる日本教育労働者組合(教労)長野支部、新興教育同盟(新教)長野支部準備会など左翼組織に対する数次にわたる検挙、いわゆる二・四事件に関する警察・検察当局の取調をもとにして長野県学務部・視学がまとめた秘密文書『長野県教員左翼運動事件』という得がたい資料と、この運動にその20歳代の血を湧かせた活動家たち12名の「証言」――追憶検討の座談会方式による――とを柱として、大正末期から二・四事件にいたる間の長野県教育労働運動史を研究したものである。これらの資料や「証言」をふまえて、この運動を全協やコップなどの全国的な運動との関連の中でとらえ、また長野県の社会的・文化的な特殊性を統一的に考察した科学的研究というべきものである。本書を構成した編輯者たちの並なみならぬ力量をみることができる。
大正15年7月諏訪郡永明村(いまの茅野市)に東京外語を出た藤田福治が赴任して研究サークルを組織し、永明小学校の教師を中心に県下教育労働運動の火を点じ、その火は京大経済出――京大には河上肇がいた――の石川秀雄に受けつがれ、さらに京大文科出身の河村卓にひきつがれてゆくが、その間、運動は県下各地に波及し、さらに全国的組織に結びついて発展してゆく。二・四事件後の臨時県会(秘密会)において石垣知事がいみじくもいえる「教育ノ自由独立ト云フヤウナ固イ所ノ一ツノ伝統的頭」が信濃教育界の自由主義的風土をなしていた。また、農民運動や青年運動の足跡や製糸・交通・印刷などの労働者の組合運動の発展が、教師たちの社会的関心をひいた。このように教育労働運動の文化的社会的基盤はあった。ことに大恐慌による勤労者の窮乏、そして欠食児童、児童の欠席の増加、さらに町村財政の窮迫に伴い教員自身が減俸や強制寄付要求といった事態に遭着するにいたって、教育労働者の階級的運動は広まるべくしてひろまる条件――全国的な情況の一環として――が熟した。
本書が展開する長野県教育労働運動の生成と発展と、そしてほとんど一網打尽の検挙弾圧に至るまでの8ヵ年間の歴史は、組織論的にも運動論的にも教訓に富むものであり、少なからず今日的課題を提起している。だがそれ以上に、革命や解放という歴史的使命のために闘うことが、いかに人間を生き生きとさせ、情熱をもたせるものであるか、だが同時に、歴史的事業はいかに蕀の道をふみ越え挫折に堪えて打ちこまねばならないものであるか、を痛感させるのである。
* * *
いかにも教育労働者の運動にふさわしく、終始、思想ないしイデオロギーの問題と教育論への深い関心が貫いているのを見てとることができる。すでに自由主義的な信濃教育の伝統があったので、思想・教育について、教師は研究熱心であったと思われるが、それだけにオルガナイザーの文化的な水準は相当高いものであったと思われる。第3章の≪資料≫にみられるように、石川、河村とつがれてゆく哲学研究会のテキストや各地区文科サークルのテキストをみてもその水準の高さを思わせる。本書に附せられている藤原晃の木村素衛哲学批判の論文はその湧出物というべきであろう。これらのテキストや第4章の≪資料≫にある「被検束教員の閲読せる左翼文献調」をみると、私には懐かしさがひとしお深い。私はこの運動に参加していた教員の人たちより3,4年ないし6,7年ほどあとの年頃になるわけだが、昭和6年金沢の四高に入学し哲学書を漁っていて、その晩秋の頃からマルキシズム文献に親しみ、暗い雪国の下宿で少数の仲間と研究会――読書会といっていた――をひらき、熱っぽい議論をしていた。≪資料≫の示す「左翼文献」は懐かしいものばかりである。同時代人の共感をひしひしと覚えるのである。この人たちも、伏字の多いレーニン、ブハーリンなどの文献をめぐって、伏字埋めの議論を闘わしていたにちがいない。今日伏字は消え、「左翼文献」が氾濫しており、研究会・読書会などのサークルが自由となると、われわれの若き日は悪夢のように思われるが、それだけに今日の人たちにはなおさらこの運動史を読んでもらいたい気がする。
当時の運動を見ると、鋭さとギリギリの構え方とでもいうものが感じられる。第4章の≪資料≫にある「長野教労支部編纂ノ修身科無産者教授教程」は、当時の左翼教師像と彼等の初等教育に対する実践的姿勢とを浮きぼりにしている(第4章の≪証言≫をも参照)。小学校に入校するということは、「ブルジョワ的毒素」を強制的に児童に呼吸せしめ「骨の髄まで腐敗せしめんと用意されているところへ強制的に赴かしめられることを意味する」と規定し、尋常1年から高等2年までの修身教科書の取扱を示している。たとえば、修身1にある「ヨクマナベ」について、「大多数の困っている人のために尽くす人が本当に正しい人」であり「えらい」のだ、そういう「えらい」人になるために学べ、と教えることからはじめて、「ヨクアソベ」では集団のよろこび、規律等を、「ナマケルナ」では「この世の中になまけているもの――地主・金持及其の子」に「飽くまで抗争せよ」と教える。「チユウギ」については忠義・愛国心の階級性を暴露し「帝国主義戦争をあばき、反戦を闘う」ことの必要などを教え、「ジブンノモノト、ヒトノモノ」については私有財産制や法律の批判をなし、ジャンバル・ジャンの話をなし、「法律・警察・裁判所は誰のために」を説明するのである。尋常1年生を対象にである。修身2では、たとえば「オクビョウデアルナ」について神仏を含めて「迷信の打破と科学的態度」を、「ワルイススメニシタガフナ」について、「裏切反対・帝国主義戦争反対を徹底的に闘うこと」を語ろうとするのである。修身4では、「明治天皇」について「莫大なる皇室費とそれを出す人民の窮乏」等を話し、「靖国神社」については、戦死者は「資本家の利益のための犠牲」であり、「資本家との戦争こそ真に国民大衆のための戦争である」ことを教える。
このように反戦思想にせよ、無神論にせよ、階級意識にせよ、これを小学生の心にたたきこんでいこうとする構え方は、徹底的、激越かつ明確である。もとより戦後の運動の視点からは、このような構え方に対する批判もあり得ようとも思う。だが、労農運動のなかで社会革命を本気になって実現しようとしている主体的な――主体的であれば理想主義的なるは避けがたいか――社会主義者のみのもつ迫力を感じないではいられない。この気迫は、「昭和元禄」下の運動だからといって、活動家たちの失ってはならないものだ。
* * *
二・四事件において被告となった指導的役割を演じた人びとは、獄中で転向した。独房にあって獄中ニュースで女性の同志と励まし合っていた矢野口波子ただ一人転向しなかった。いま還暦に近いと思われる彼女は「そんなたいしたものじゃなかったのですが、自分の行きたい方へ行くのだと思っただけです」と謙虚に「証言」(第6章の≪証言≫)していられる。
転向は運動のなかでは裏切りであり、主観的には挫折である。だが、転向によって敵に魂を売った佐野・鍋山の徒と、転向によって権力の凄みに惨として敗北し、道義的自我の挫折に胸をいためた人びととは、運動のなかにおいてもその役割は異質のものではあるまいか。いまこの≪証言≫に参加した人びとの良心に敬意を表したいと私は思っている。第6章の証言は語る。
D「検挙はむしろ覚悟のまえでした。ただあれほどゴッソリあげられるとは思いませんでした。私たちは検挙されても根は残ると思った。……それこそ根こそぎやられてしまった」(出席者皆同感)
権力の凄さに愕然としたという感じであろうか。Gの証言にもあるように、共産党・全協・教労などのたんに影響下にあるということで検束されたものは、「羹に懲りてなますを吹く」という位臆病になったようである。革命的政治犯弾圧とはかようなものなのだ。しかも当時は、転向して世にかえっても待つものは生活苦と特高警察の絶え間のない監察とであったのである。そこまで覚悟した人びとには若い侠気やヒロイズムがあったと思う。だが、途中にして権力に敗れ屈辱と挫折に傷めつけられたとはいえ、その信念に一度は生涯を賭けた人びとの人生には詩があるというものであろう。要領よく時流を泳いで世渡りをしていくことの「幸せ」とは生涯無縁であることを覚悟していた教師たちの教育が、生徒の心に刻みこんだものは消え去るはずはない。当時の生徒は20代で敗戦をむかえているはずである。戦後の長野県労働運動にも彼等の活動が寄与しているのではあるまいか。
それにしても、転向による道義的自我の挫折は傷ましい。運動と教育に復帰して償いをしようとされている人もいるし、また、教員への復帰のすすめを、「私は検挙されて以後というものは、学校の先生の資格はないんだ、自分が教えてきたことに対し自分自身が挫折しているんだという気持でことわりました」と証言(Aの証言)されている人もいる。いずれにせよ≪証言≫に参加した人たちは、若き日の教育労働の実践が歴史的に意義のあることを確信し、その火を今後に受け継ぐことを期待しつつ、にがい思い出をも語っていられると思う。この書物が、現在の運動にむかって、また明日の世代にむかって、何を教え何を訴えんとするのか、それをかみしめて読むこと、あるいは本書をテキストにして、研究サークルを組織すること――本書に登場する教師たちが40年前にやったように――が、戦後の世代にとってわけても有意義であるといわねばならない。
過日私は、茅野から長野・上田・小諸・佐久と一周の旅をする機会があった。くしくもその間に本書のゲラ刷りを読んだ。二・四事件で検束され、起訴や退職その他の処分をうけた先生たちやその教えをうけた生徒たちに街々ですれ違っているのだろうと思ったりした。小諸、佐久のあたりははじめての旅であったが、藤村や牧水の歌碑もさることながら、ちょうど初秋の今頃の季節に「北信メンバー会議」の行われたという「ひっそりした茶屋」(第5章の≪証言≫)はどこだろうかと、懐古園に立って想像してみたり、佐久の鯉こくをすすりながら岩田校長と会ってみたい気持にもなっていた。そしてこんなことを思っていた。
「長野県教育労働運動史」のような書物は各地において編集されねばならない。それは運動の火をつぐ仕事の一つである、と。 (二・四事件記録刊行委員会編『抵抗の歴史』、1969年)
 |
明けない夜はない 村山ひで著 判型四六上製 ページ数331 発行日:1969年12月 |
労働旬報社の木檜社長と柳沢編集長とが、11月に入って一夜私に四方山の話をきかせに来てくれた。その夜は柳沢君はとくにある話を私にきかせる狙いをもってきたにちがいなかった。そのある話というのは、本書(『明けない夜はない』)の話だったのである。話す彼自身が感激していて、得意な印象的表現で話してくれた。予感していた通りゲラをよんで私も感動させられた。清純熱烈な愛情と真理への確信に基づく不屈の闘魂とによって、凄惨なまでの困難のなかで、たゆみない精進と闘いを貫いてきた夫婦の生存の記録をここにみるのである。さきに出た『抵抗の歴史』は長野県における昭和初期の教育労働者の抵抗運動をつづるものであるが、長野を襲った同時代の弾圧の嵐が本書のなかでも吹きまくる。その嵐のなかで結ばれ、嵐に抗して火の魂の如く燃えるところから本書は書きおこされるのである。
学童を愛し、詩を作る文学少女にすぎなかった最上川のほとりの若い女教師であった著者が、当時すでに社会運動に挺身していた村山俊太郎の詩の批評に教えられ、現実認識へのひたむきな関心をもち、ロマンチシズムからリアリズムへと進んでゆく過程で、彼に尊敬と愛情とのきずなで結ばれてゆく。母の悲しみや親戚の圧迫に結婚は難航するが、母を説きふせてついに昭和8年春結婚式をあげ、しばらくは村山に学びながら、彼の運動を助け、比較的落ちついた母の生活にひたることができた。
ところが四番目の子を妊娠したとき、村山の宿直の早朝に突然家宅捜査をうける(昭15.2.6)。村山は逮捕せられる。そしてこのときからきびしい試練の日々が村山一家をおそいつづけるのである。獄中との便りの切々たるは言うまでもないが、村山が保釈後――彼は肺結核で衰弱しきっていた――「板も敷いていない小さな小屋」を借り、喀血する夫、幼い子供たち、赤ん坊までをかかえて暮らすが、雪がふり、雪どけ水が小屋に浸みこんでくるなかで、「国賊」の一家は愛情と信頼と「明けない夜はない」という確信のみを糧に堪え忍んだ――この生活を誇張もなく語る著者は生涯忘れえないというが、読者にも生涯忘れ得ない印象を刻みつける。
戦後は病躯をおして村山は運動に立ちあがり、彼女も労働組合を知り、婦人部の結成などに従事するが、間もなくGHQの反動的な力が加わりはじめる。だが、二・一ゼネストの敗北後、この闘いに生命を燃やしつくした村山は病床に斃れた。そして苦痛に堪えて山形県教育運動史の筆をとりつづけ――高僧の如き精神力を感じさせる――雪深い師走9日、誇り高い「共産党員の死」を死ぬ。彼女は「死をむかえる俊太郎のそばで、死の旅の着物を縫いつづける。涙も落とさずに縫いつづける自分があわれでかなしかった」と書いている。
村山の死後、彼女は幼い子供たちをかかえ失業に堪え、好意ある復職のすすめ――それは権力への屈服を意味していたから――も拒否して、俊太郎とともに歩み来たった道をひたすらにすすむ。そして彼女自身が成長していっている。やがて教員組合の書記として働き、母親大会の運動にも参加し、この路を新しい時代のなかで太く広げてゆくのである。だが、何よりもひとはそこに、共産党員の愛妻であるとともに、すぐれた一人の共産党員をその生と死とを貫いて生涯愛しつづけている妻の不壊の心根の美わしさを見て人生の詩を感じないではいられまい。そして翻って、この国に新しい時代をきりひらいてゆく革命的人間に課せられた秋霜烈日の試練に堪えて、一筋の道をすてなかった夫婦の思想と愛との迫力に身のしまるを覚えるであろう。
(村山ひで『明けない夜はない』、1969年)
東海道新幹線が営業を開始したのは1964年10月1日、東京オリンピックに間にあわせるというので――意識操作でもあった――急がれたのであった。だが、新幹線のみならず主要幹線の複雑化・電化等のプランは1961年の国鉄第2次5ヵ年計画にはっきり打出されており、それは高度経済成長政策にとって緊要な交通運輸政策にほかならなかった。国鉄の「赤字」問題の根源は、高度経済成長に寄与――物資と労働力の安価な移動等によって――させるという体制側の政策ないし国鉄の「使命」それ自体のなかに伏在していたと私は思っている。国鉄労働者は過密ダイヤの下で疲労と危険をかえりみずに働かされたのであった。
実にすでに、労働強化を必至ならしめる情勢を展望して――安保条約改定への政治的対策の意味を含んでいたが――、1957年春闘に際して政府・当局は未曾有の大量処分と団交拒否とをもって国労と機労(現在の動労)に圧力を加えていた。しかし組合側はILO闘争をも含んだ権利闘争によって巻きかえし、団結の自主性を確立していった。その頃、国労本部は活動家教育を金沢文庫のあたりにあった国労学校で精力的に行っていた。いまは亡き額賀情宣部長がはりきって未明から生徒といっしょに駈走をやってきて、私をおこして朝食から講座と緊張したスケジュールを組んでいた。開校式には鈴木委員長がやってきたりしたものだ。私はドイツへ留学(1962年から1年間)するまで毎年国労学校へ出かけて、夜は額サンと一杯やった。おもしろい人物だった。
このような活性のある団結があるかぎり労働者の犠牲による生産性向上運動――「マル生」運動――を押しつけることはできまい。そこで対抗組合との結託による国労組織の切崩しが当局のポリシーとなる。二つの既存の第二組合の合同による新国鉄労組連合の結成――全労加盟・民社支持・マル生協力路線――をみたのは62年の晩秋であり、同労連が単一組織として改編し、鉄道労働組合(鉄労)と称するのは68年秋である。その直後、国鉄財政再建推進会議が16万人にのぼる要員の合理化と大幅運賃値上げの再建策を運輸大臣に答申、追っかけるように国鉄当局は数千駅の廃止、無人化などの計画を国労に提案するという運びになってゆく。そして翌69年5月、石田総裁退任のあと副総裁であった磯崎氏が国鉄総裁に就任し、7月職制強化のための全国行脚を開始し、国労に対する露骨な組織切崩し攻撃――いわゆる「マル生」攻撃の中心――の幕を切って落としたのであった。
およそ企業別組合にとって企業が赤字であり人員整理を伴う雇用調整の可能性が見透されるときほど運動の困難なときはない。国鉄の赤字が何ら労働者の怠慢や不均衡なまでに高い賃金や短い労働時間などに帰せられるべきでなく――国鉄労働者の生産性は先進諸国のそれに比してむしろ高いのである――、経営の巧拙をすらこえた国鉄の経済的・政治的使命――宿命といえる――によるものとみるべきであり、それ故にこそ当局が「思想攻撃」では組合の反論に押しかえされ、専ら差別待遇や支配介入といった低俗不法な手段による切崩し策謀に走らざるをえなかったのだといわねばなるまい。にもかかわらず、現実にはいわゆる合理化が必至であると、見透さざるをえない当局の居丈高な姿勢が、国労の組合員を動揺させたことは否定できまい。しかも直接間接に差別や圧力が加えられていたことはまぎれもないことである。その氷山の一角にすぎないのが、地裁や公労委の認定した事実というものである。
国鉄労働者は一般に生涯を国鉄にゆだねる気で就職している。その職場は彼らのほこりと生き甲斐とを感ずる職場であり、勤勉に務めれば助役の帽子を冠ってプラットホームを見まわれるようにもなるであろう。助役になると親類知人を招いて夜宴をはるという風習のある地方はいまも少なくないだろうと思う。職場の仲間と調和しながら勉強して試験をうけて昇進し、仲間に祝福されつつ年功を重ねてゆく、これが自然な労働環境なのである。国際人権規約のA規約(経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約)第7条にいう「公正かつ有利な労働条件を享受する権利」とは、このような状況で実現をみているものなのである。なお、同条は特に確保(ensure)すべき条件の一つとして、C項で次のように述べている。「すべての者がその雇用関係において、年功と能力(seniority and competence)以外のいかなる考慮も加えられることなく、適当なより高い地位(an appropriate higher level)に昇進させられる平等の機会」と。
「マル生」攻撃は、国労の団結に対する不当労働行為であったばかりでなく、その差別と支配介入とは個々の組合員に対する人権侵害であり、人生破壊的な行為――現に発狂者や自殺者まで出したではないか――であったのである。だからこそ、「ふところに辞表をいれて」一般組合員も立ちあがらざるを得なかったのであり、また立ちあがることができたのである。磯崎総裁から当局の手先として国労からの脱退を組合員に迫った末端職制にいたるまで、自主的団結の切崩しが組合員の人生破壊と人間侮辱を伴わずしては行われえないということに気がついていたと思われる形跡はほとんど見られなかった。国労の組合員であるということが、昇進の平等な機会を奪われる理由とせられるのは公然の秘密――「秘密」ですらなかった――であるような職場に封じこめられていたのでは、組合員はやりきれたものではない。
国労は1971年8月下旬、函館における第32回定期大会で「マル生」反撃の方針を決定した。中川委員長が「座して攻撃にさらされるより立って反撃を」と訴えたのはこの大会である。彼は、私がはじめて釧路地本を訪ねた――権利講座、昭和27,8年の頃だったか――とき同地本の委員長だった。毛蟹を新聞紙を敷いて食いちらかしながら一杯やって以来の友人であったが「マル生」闘争の指導に精力を傾けつくして斃れた。惜しい人物であった。彼の右の決意表明は、国労がこの大会以後に巻きかえして磯崎陳謝にまで追いこんだ「マル生」闘争そのものの発想の起点として、歴史に刻みこまれるであろう。この中川委員長の決意表明は団結に浸透していった。いや組合員一人ひとりのやりきれない気持ちにうったえたし、それに活性を与え、主体的な団結の構築への意欲と確信とを高揚したといえるであろう。しかしまた、中川委員長が「立って反撃を」と訴えることができたのは、やりきれない職場の雰囲気のなかでも、なお毅然として団結のモラルを守っていた人びとのいること、国労の団結が核心において堅固であることを知り、かつ仲間の自負と信義とを確信できたからであると思う。
国労が「マル生」運動にたえ抜き、さらに反撃を加え、脱落者のかなりの部分を国労組織に奪還しえたことは刮目すべきことである。周知のように、戦後の組合運動における共通した傾向は、一たび「第二組合」ができて経営者と協力関係が生ずるや、第一組合の失地回復はもとより絶望的であり、じり貧をまぬがれないということである。にもかかわらず、国労は少なからぬ脱退者を組織に復帰させたのである。そこにはさまざまな要因が働いていたと思うが、その一つには明らかに組合の闘争歴に対する組合員の自負心があったと思われる。
国労は国鉄が基幹産業であり、かつ公共的公益事業であるが故に、法律によるスト禁止ばかりでなく、政治的・社会的圧力を絶えずうけざるをえなかった。ストを打てば処分せられ――個人としての損害ばかりでなく、組合の財政を圧迫することは法廷闘争費用をみるだけでも明らかなことだ――、さらに「違法スト」だとか、「親方日の丸」だとか、政府当局やマスコミにたたかれる。その「親方日の丸」なるものが、違法な団結侵害やら人権侵害やらを執拗に行っていようとは、一般の社会人には知られていない。とまれ、運動に対するさまざまな圧迫にもかかわらず、波瀾変転はあったが、いつも組合運動の汽関車となってきた国労の闘争歴は、何といっても輝かしいものである。労働組合が日本の民主化の主体的な勢力であるかぎり、組合運動の推進力たる団結体は、民主主義の旗手だといってよい。その団結の威信を意識する組合員にとって、当局からの低俗不法な差別や介入に屈服するが如きは到底たえうるところではあるまい。
以上のように、国労の反「マル生」の闘争を内面的に考察してゆくと、帰するところは、組合員が自己の人間的尊厳を団結活動によって確認してきた闘争歴への自負と団結への求心的・道義的意識とがあって、指導部の意欲と確信とが呼応し、国労の主体的団結が構築せられ、権利意識の高まりをみた、ということであろう。そして、社会が「親方日の丸」の人生破壊的・団結否認的悪業の限りを見たとき、「マル生」闘争の民主的意義を見出し、国労の立場を支持することになるのである。世論の追風を帆にうけて、船体のしっかりした団結の船がまっしぐらに「マル生」攻撃の大浪をのりこえる。だが、世論の追風は、実に国労と国労の組合員の決意ある団結と闘争なしに生じたものではないのである。
マスコミ=世論の追風――「マル生」闘争をめぐる情勢の変化
もとより国労側には当局の不当労働行為の数々は自明の事実であり、救済命令が出るのは当然のことと思われていたであろう。だが、これを公労委において立証し、事実を法的に意味づけて審査委員会をして確信をもって当局に陳謝文を書かせるには、組合員が「ふところに辞表をいれて」証言に立つ決意をもつとともに、団結への信頼感を抱いていなければならなかったし、弁護団の優秀さも必要だったのである。この事件の審査委員長が峯村光郎教授であったことも、人権感覚、労働法的発想などの点でも、審査の進度・方法の面でも恐らくは法の正しい適用をみる要因の一つであったであろう。峯村さんは労働法学者でもあり、法哲学会の重鎮でもあった。外柔内剛型の人物であり、権力側の頤使に甘んずるような先生ではない。この事件のあとのことだが、当局のやり口には憤慨されたような話を私になさった。親しい先輩であった峯村先生も既になくなられた。
静岡地本の不当労働行為事件における国労側の勝利は、組合員の自信を深め団結への意思を強化したことはいうまでもないが、同時に闘争をめぐる情勢を変えた。1970年代にかかる頃には、国民の人権意識が高まっていた。だが、管理社会の重苦しい圧力を感じ、疎外感から人間性の復権への熱望が生じてもいた時期であった。しかもいわゆる情報社会ときているので、公労委が国鉄当局に陳謝を命じたという報道は――マル生調査団報告も寄与するところがあった――世論に訴え、共感をひき起こす状況が熟していたといってよい。さらに水戸鉄道管理局でのいわゆる録音テープの公開が国鉄当局の不当労働行為意思を露呈した。管理局の能力開発課長が駅長らを集めた会議の席上、「不当労働行為はうまくやれ」と訓示したことが録音せられていたことが、全国紙(昭46.10.10付)で報道せられたとなれば、世論が承知しないのは当然であった。
職制による差別的管理によって国労からの脱退を押しつけて、団結を切崩すという当局のやり口は、市民の人権感覚を逆なでするものであるばかりでなく、その当局を追及することが、雇用労働者がその60%にも及んでいた国民大衆にとっては、いくらかは、自己自身の雇用関係の場での疎外感を媒介として人間性の回復を叫びたい感情に共鳴するところでもあったと思われる。録音テープ公開の翌日には、磯崎総裁も「不徳のいたり、極めて遺憾」と社会的に陳謝せざるをえなかったのである。そして、国会では、社会、共産、公明の各党が、政府・当局の責任を追及し、いわば世論とマスコミに呼応したのであった(10月11日衆議院社会労働委員会、12日衆議院法務委、13日参議院社労・運輸合同委)。
かかる情勢変化のなかで、「追撃戦」が展開せられ、「マル生運動推進の最高責任者――真鍋職員局長・常務理事の更迭」その他の責任者処分、「マル生教育」の中止、紛争対策委員会と当局との間の覚書締結等々、「マル生」闘争が国労の勝利の形で「第一のやま場をこえ」たし、脱落を防止したばかりか、脱落した労働者の一部を国労の組織に復帰させることもできたのであった。国労はこの闘争によって、連帯のモラルと団結の力との自覚を深め、闘争のエネルギーを蓄積しえたといわねばならない。「マル生」闘争を闘いぬいた後の国労組合員は、いうなれば一味ちがってきたように思われてならなかった。国労が組織として試練をこえただけでなく、組合員もそうであった。
しかし、「第一のヤマ場をのりきこえ」たことに安住して組織力過信に陥っているわけにはゆかなかった。政府・当局が、国鉄合理化の意思を放棄したわけではなく、その後も着々と「マル生」を進めてきている。「マル生」闘争は当局側にも多くの対組合政策や労務政策上の教訓を与えたことを看過してはなるまい。さきに能開課長が駅長たちに期待したような“巧妙な不当労働行為”をつづけるのは眼にみえている、いな72年度の国労第33回全国大会では早くも「地方の職場ではあらたな“マル生”が始められてきている」(第7編7―7の資料)ことが報告せられているのである。団結の主体的力量はたえず錬磨されねば維持せられるものではない。
「マル生」闘争の勝利は国労の悲壮なまでの決意をもった闘争の構えなしには達成できなかったことはいうまでもない。だが、弁護団の活動、公労委の良識わけてもマスコミの寄与――「マスコミ共闘の積極的な協力」があった――を過小評価してはならないのである。情報社会――それは技術革新・経済成長とも大衆社会化現象や「大衆民主主義」とも相互関係をもって展開している――におけるマスコミの社会的・政治的影響力の大きさ――その過大なところに問題もあるが――を直視すべきである。それは総じていえば社会の意識状況を反映するが、同時に意識を形成してゆくことはいうまでもあるまい。
政府・当局は国鉄赤字を強調し、いかにも国鉄労働者の親方日の丸意識から行うストが赤字を生ずる非協力の表れであるかのようにマスコミ操作をつづけてきている。「マル生」運動の不法非道に憤ったマスコミも世論も、この慌しい社会変動のなかで、いつまでもそれを覚えているわけではない。生涯をかけた気持で闘った組合員や組織の命運を背負う気で緊張した執行部のリーダーたちには、いつもなまなましく興奮を喚起するような闘争経験であったにしても、マスコミも世論も移ろいゆき、当面の状況のなかで社会的に提起せられた問題視角から国鉄問題も国鉄労使問題もとらえてゆくのである。そして今日は政府・当局側が国鉄赤字問題を焦点にすえて、スト迷惑論と労使協力による合理化=「再建」の課題として社会的に関心を喚起しているといってよい。おそらく、「マル生」闘争の失敗――あまりに焦燥し、あまりに独善的であったから――から、不当労働行為の稚拙強引さの反省とともに、マスコミと世論への配慮不足を反省したからにちがいないと思う。そして、この側面では、国労、いな革新陣営の立ちおくれ、むしろ無防禦が気にかかるのである。
今日、国労の運動は「マル生」闘争期にも劣らない困難な条件の下で進められねばならないように思われる。というのは国鉄の輸送量のシェアが低下している、高度経済成長には回帰しない、減量経営に民間の労働組合が対抗できていない、完全失業者は100万人台を下らない、最高裁の全農林警職法判決以後は、裁判闘争によるスト権回復は当分見こみがない、「スト権スト」――未曾有の迫力ある政治的圧力ストであったが――以後は当事者能力論から公企体経営論へとスト権回復問題がいわばスリかえられてしまった、三木内閣の頃から革新陣営に乱れが生じ、中道路線が登場して保守陣営は再編強化に向かい、社会党の衰退と相俟って立法闘争も困難となった、春闘は75年以来「連敗」をつづけている、公労協の統一闘争も危くなってきたようだ、等々状況は60年代から70年代に跨る時期よりは遙かに国労にとって厳しい環境だといわざるをえない。
これからの実践的課題であるとはいえ、全逓の反「マル生」闘争に対して郵政省は懲戒免職(郵便法違反と暴行・傷害理由に国公法適用とみられる――1979.4.28、朝日新聞の記事から推測)58名、公労法18条による解雇3名を含む8,183名の大量処分を発表した。全逓は53件の不当労働行為を公労委に申立てている(同上紙同日夕刊)のみならず、当局側の電話発言の録音テープも証拠として提出されるようである(同上紙)。国労の反「マル生」闘争のパターンに似たところもある。果たしてこれからどのように展開するものか、民主的エネルギーをいかに蓄積し活動させるかにかかるが、必ずしも楽観できる情勢ではあるまい。
このような客観的情勢のなかで、当局側は巧妙な切崩し工作やマスコミ操作に対抗して自主的団結を維持してゆくためには、多面的、創造的な活動を必要とするといわねばならない。だが、それができるには、国労の団結を内面的に構築するという絶え間ない組織活動と組合員相互の錬磨が必要なのである。
「マル生」闘争は国労の組織をあげての闘争ではあったが、必ずしもすべての組合員が自覚的に取り組んだわけでもあるまい。「マル生」攻撃も地方によって鋭さにちがいもあったから、反「マル生」の意義のとらえ方も多様となるのはさけがたい。それでも「マル生」闘争期の組合員は直接間接にこの闘争を意識していたであろうし、その勝利によって団結の真価を多かれ少なかれ捉えたと思う。しかし、すでに7、8年の歳月を経ており、その間に国鉄に就職し、国労の組合員となった若い世代も少なくはあるまい。「マル生」闘争も忘れられてきているかもしれない。少なくも自己の実践的関心にひきつけて「マル生」闘争を意識しない世代が増えているといってよい。だからこそ、「マル生」闘争の記録が公刊されねばならないのである。
それにしても本書を通読しつつ、私は社会的に生きるということの厳粛さをしみじみ感じた。「マル生」事件のなかで、磯崎総裁から国労切崩しの尖兵となった末端職制までの人びと、また「脱退勧告」という圧迫誘惑に崩れて国労を去った人びと、さらに団結のモラルと人間の尊厳を守って抵抗した組合員たちも、果たして自分の名前と行動が抹消しがたく歴史的文書のなかに刻みこまれることに想到していたであろうか。本書は「過去」の書棚の片隅にほおりこまれたまま忘れ去られてはなるまい。いまこそ、若い労働組合員によって噛みしめて読んでもらわねばならない。社会に生きる者が、尊厳に値する生を生きようとするならば、自己の行動の社会的意義を考えないわけにはゆかない。その考え方を本書は教えてくれるであろう。個人としても、労働組合としても、人間の尊厳は自主的団結への意欲と信頼の下での主体的実践によってのみ実現されることを。
(国鉄労働組合編『国鉄マル生闘争資料集』、1979年)
『平和教育実践事典』というユニークな標題の共同作業に広島平和教育研究所が中心になってとり組んできたが、ついに刊行の運びにいたった。この企画は「日本の教師・国民が戦争の惨禍を二度とくりかえさず“ふたたび教え児を戦場に送らない”決意に立って積み上げ実践してきた」現場教師の平和教育・民主教育の苦心の成果を集大成したものである。「ヒロシマ・ナガサキの魂を深くこめ」て反戦・平和に徹した烈々たる決意を、凄惨たる戦争体験のなかから叫び上げている歴史的な書だといわなければならぬ。本書の真価はまさにそこにある。
およそ、反戦平和をめざす教育実践という課題は、戦争の悲惨ことに「人類共滅の危険性を現実のもとする」核兵器の「痛ましい犠牲」を「具体的にかつ切実に」認識し実感することを原点とすべきであるが、さらにそれを人間観や国家観などつまり思想として把えるのでなければ実効をあげうるものではない。のみならず、戦争体験がたえず現在化され、現実政治のなかでそれが自覚されるように運動を維持発展させるという社会的政治的課題とも結合されなければならない。人間の尊厳の理念をふまえて展開している国際的人権憲章――社会的人権及び市民的人権の保障を含む――と国連を中心とする国際平和への努力との相関を自覚して戦争否定に徹する国民社会を形成するという営為こそ平和教育実践というものである。そこには人間の努力によって戦争を克服できるという信念と克服するために闘争も犠牲も之を辞せずという決意とが結合しなければなるまい。その結合を歴史のなかから学びとるとともに、現在の主体的実践のなかでその結合を堅固にすること、そのために平和教育は国民的規模において展開されねばならないことがこの「事典」に具体的に示されている。
平和教育はむづかしい問題を少なからず含んでいる。正義の戦争、民族独立とか自衛のための戦争という問題があり、反面に人道に対する犯罪や平和に対する犯罪についての戦争犯罪者の訴追の問題がある。日本国憲法の交戦権放棄と自衛隊の法的評価の問題や安保体制と平和・自衛との関連の問題にわれわれは当面している。そのなかで現実的なものと理性的なるものとを如何に媒介させるかは、戦争否定への執念を宿した主体的実践にかかると思う。本事典の編集たちが、平和教育実践事典というだけでは汲みつくせない主体的契機を意識するところから、「平和教育実践事典」という標題をかかげたものといわねばなるまい。それ故にこの事典は厳粛な活力をもちつづけるのであり、反戦平和運動の真実を訴えるのである。
本事典は日本人の体験と苦悩と良心とが生み出したものであり、国民ことに「戦後派」世代に是非読んでもらいたい。だがこの事典が叙述し、訴えあるいは論じているところはひとり日本人のみに向けられている事柄ではなく、世界に向けられているのである。少なくとも先進国とくに核兵器保有国の国民には読んでもらいたい。日本の外務省に期待したいと思うが、それが困難なら、近来とくに人権と平和のために努力しつつある国連本部にたいしてまず、英、仏、露語によって本事典の訳文を出して国際的関心を喚起するよう私は切望する次第である。
(広島平和教育研究所編『平和教育実践事典』、1981年)
ところが、警察官による政治的盗聴事件というのは、盗聴という犯罪行為を担当した警察官なるものが、警察という組織の一環として行為しているわけで――よもや盗聴趣味があるからではあるまいし、公権力の計画的犯罪であるといわざるをえない。しかも、その公的任務が人権と民主的秩序を守ることに有する警察の意識的な背任なのである。
ところが、かくも由々しき問題にもかかわらず、検察庁(東京地検)は、盗聴に直接関与したとされる2名の警察官を起訴猶予にし、他の2名は不起訴処分にすることで捜査を打ち切ってしまった。警察庁も若干の幹部警察官の退職、異動と当該警察官に軽微な処分を行っただけであった。それで世間体を繕ったというわけであろうが、この検察・警察双方のやり方を見て、ますます由々しき問題だと考へざるを得ないのである。
ロッキード汚職事件では前首相までも正義の名において訴追し、「男をあげた」検察庁なら、いかに捜査のとき頼りにしなければならない警察だからといって、いやそれ故にこそその背任的な犯罪について厳しく鉄槌を下すべきものであった。その自覚を促すことは、民主主義擁護にとって不可欠の国民運動である。この盗聴事件は断じて有邪無邪に終わらせてはならない。「付審判申立」を支持するという形で当面は展開さるべき運動であるが、それを通じて秘密警察を見のがさない社会的風土を深く定着させなければならない。
(上田誠吉・佐野洋・塩田庄兵衛編『警察の盗聴を裁く』、1988年)
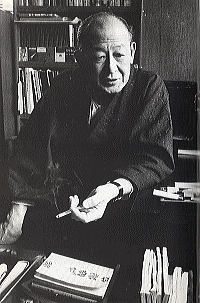
沼田稲次郎
1914年(大正3年) 5月25日、富山県高岡市に生まれる。
1952年(昭和 27年)8月、東京都立大学教授(人文学部)に就任。
1965年(昭和 40年)4月、東京都立大学法経学部長に就任。
1973年(昭和 48年)4月、東京都立大学総長に就任(〜81年3月、2期8年)。
1997年(平成9年) 5月16日、死去。享年82歳。
◇編 集:旬報社編集部
責任者 :木内洋育
編集協力:石井次雄
制 作:飯島信吾
UP:2014年3月25日
更新:2014年4月18日
更新:2014年4月20日
更新:2014年5月25日
更新:2016年5月23日