�g�o�̂t�o�F2014�N03��25��

�{��Ђ͍��H�n��65���N���}����B���Ђ����w�������������̏��c��Y�搶�́A�w�J���@���{��x����ɂ����Č��M��U����100�{����_���\�����ƂƂ��ɁA�w����W�x�S10�����܂�20���]�̒P�s�{�����s���ꂽ�B�����Ɂu���c��Y����ژ^�\�\�l�Ɗw��̕��݁v���f�ڂ��A�J���^���E�Љ�^���ƂƂ��ɕ���ł���ꂽ�����̑��Ղ��A�搶�̐l�ԂƂ��Ă̕��݁A�搶�̎v�z�̐��n�ƌ��������Ȃ���A���ƂÂ��邱�Ƃ��ł�����Ǝv���B
���D��k���m�点
�@�ߋ��̍č\��
�@
�@�u����W�v�S10���͗\���菭�������A12����{�ɂ͊������錩�ʂ����������B������9��20���̌��j���ɑ�7���̌��{���ł����B���N��5��25���A60�̒a���j���̂Ƃ��ɁA���ϔN������Ȃ��Ă���̂�����A�܂��܂��w��̓r�ɐ��i���ׂ��A�Ƃ�������̌��t��������Ղ����̂ł������B�����A�җ�L�O�_���W��ߐ{�攌�ɂ�鎄�̏ё�����A�Ԃ��`���b�L�ƖX�q�𒅂��Ė��̂悤�Ȓ�q��������ԑ�����������Ă݂�ƁA�������V���ւ̖�ɗ����Ă���̂�������������Ȃ������B�җ�Ƃ����Ɓu�Ⴂ�ҁv�Ǝv���Ă݂��鑷�c�搶�▖��搶����͏��邩������Ȃ����A����͎��̂����Ȃ��S���ł������B�j���̐ȏ�Ŏ��́u���ꂩ��͎c�������ɓ��肽���v�ƈ��A�������A���Ȃ����J���@�w�ɂ��Ă͂��ꂪ�{���ł������B
�@�u����W�v���o������ɂȂ����̂��A�������ɂ����炩�̋C�����������Ȃ������킯�ł͂Ȃ����A��͘J���@�w�Ƃ̌��ʕ��W���Ƃ������Ȃ���ՂȊ�������ł������B
�@�Ƃ��낪�A��������W�ɂƂ肩�����Ă݂�ƁA����͕��@�_�I���Ȃ�Ǝ��̍\�z�͂�v������V���Ȏd���ł��邱�Ƃ��킩�����̂ł���B��̒Z���N�\�ɂ����܂�30�N�̂킪���̗���ł͂��邪�A����������_�̎�������10���ɋÏW���A��ԁ����̓I�ɍ\�z���邱�ƁA���邢�͗��j�I�Ȃ��̂�_���I�Ȃ��̂Ƃ��ēW�J����Ӗ�������͂����Ă����B���ꂼ��̋ǖʂɂ����Ē�N�����ۑ��_���A���邢�͎���@�̉��ߗ��_��̌n�����Ƃ������]���̒����E�_���́A���Ƃ��u����W�v�̕Ґ����߂����ď�����Ă��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ނ��낻�̂Ǐ������ĂĂ��������̂��Ƃ���������B�������ɉߋ��̘_�e�͌��݂̎��̎v�z�ɔ}���Ă��悤�B�����A���ꂼ�ꂪ�Ǝ��̖��S�̉��ɏ����ꂽ���̂ł���A�ɒ[�ɂ������̂��̂̌p���ł���B�������j�I�ɔ��W���錻���݂Ɏ�̓I�Ɋւ�邱�Ƃɂ���āA�����������݂̏��_�@�Ƃ��ā\�\ ���ꎩ�̂��Ǘ��I�ɂł͂Ȃ��\�\ �c�����悤�Ƃ��Ă�������A�v�z�Ƃ��Ă͓���I�ɍ\���ł���悤�ȋC�����Ă��Ȃ��ł��Ȃ������B�������A����W�������ŕҐ�����Ƃ������Ƃ͉ߋ��̒��b�ł͂Ȃ��V�����\�z��Ƃł������B
�@��10���̊����ɕt�����u�����ɂ�����āv�̂Ȃ��ŁA�����S���犴�ӂ̈ӂ�\�������X�̌ە��������Â��Ă������炱���A���̍�Ƃ��ǂ��ɂ���肫�ꂽ�̂��Ǝv���B�������Ē���W��10���Ȃ�ԂƂȂ�ƁA�߂����������������݂��S�����悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��B�����A�������A�����g�Ǝ��̒���W�Ƃ��D�ӂ������ĂƂ�܂��Ă����������������Ƃ��琂Ƃ��̕������Ƃ̖�Ɋ������ɂ킽���Ĉ���Ă��Ă����[�����ɂ��̋M�d�������݂��݂Ɗ������̂ł������B
�@���E��������i�x�j�̎��M���啔���͘J���{��Ђ̔��ӂɂ���Ă��肢����i���ɂȂ����̂ł��邪�A���Ђ̎�]�w�́A���Ɛ[���������̏��N�Ȃ̂ŁA���Ȃ����@���w�҂�J���g���̃��[�_�[�B�Ǝ��Ƃ̏�I�ȂȂ���܂ł悭�m���Ă���A���̖ʂ���ƁA����ɂ����炩�͓��Ў��g�Ƃ̊ւ������l�����Ă��肢�������������̂����O�������Ă����B �����u����v�ł́A�搶�Ƒg���E�@�w�E�ȊO�̗F�l�ɂ��Ă͎��ɂ䂾�˂��̂ł���B
�@���̊w������̐搶�ŁA���̌h������搶�Ƃ������ƂɂȂ�ƍ����瘾�搶�ȊO�ɂ͎v���o���Ȃ������B�܂��搶�́A���̌������A�Ƃ����Ă��s�풼��A�t���̏���ӂ���ɉ����ΐ_�Ђŋ��s���A���[�̗��ł����₩�ȏj�����͂����Ƃ��̂��Ƃ����A�߂��e�ވȊO�ɗ��Ă����������B��̂��q�l�ł��������̂ł���B�J���@�w�E�ł͐�䐴�M�搶�ɂ��肢�����B�搶�͐�O�̘J���@�w�҂̂����Ŏ������ŏ��ɂ��߂ɂ��������搶�ł���B���̌���w�ʘ_���R���̎卸������ĉ���������A���܂��܂����b�ɂȂ��Ă��鋕�S�R���Ȑ搶�Ȃ̂ŁA�����w��̈�̌�y�̂��߂ɂ�崂�Ȃ��C�y�Ɍ䎷�M�������������ȋC�������̂ł������B
�@�w����R���̍��̗F�l�͌��e�p���Ɩ����̎Љ�Ŋ������Ă��鏔�N�������A�M���Ƃ�̂����������炵���̂��킩�����̂ŁA���ǁA�݂ɒ����̌��������Ă��鋌�w�F�ł���A�@���N�w�ɂ��Đ[���l���������ꂽ�����\���Ă��镐����Y�N�ƁA�[�����s�V������Ɏ��ʍ���g���^�����ꏏ�ɂ�����C���̂��������K�Y�̓�l�̐e�F��ς킷���ƂɂȂ����̂ł���B�����Ȃ�Ε����N�͖k�̓s�ɐt�������ɑt�łĈȗ��̗F�A�����N�͐��̌��_�ɋ��ɃX�N������g���Ԃł���B
�@�ȏ�̂悤�Ȏ���ŁA���Ȃ������̕�����͔��ɐe�߂��������Ă��鏔�搶��F�l�����ɐ��E����x�̎��M�����肢�ł����̂ł������B�����Ă��ꂼ��ɖ��킢�̐[���\�\ �����g�͏Ƃꂭ�����A�������������v�������\�\���͂������Ă����������B���ꂾ���ɁA�����Ɋ��ӂ̈ӂ�\�����ɂ��Ă��A����ŏI��ɂ���͉̂���������Ȃ��C���ł���A�]��Y���Ƃ���ł���B���K�˂��Ęb��������ŁA�����͂��ƂȂ����摜�̒f�Ђ⊴�z�ł��Ԃ��āA���߂ɂ����悤���Ƃ��v���Ă����Ƃ���A�K���ɘJ���{��Ђ��e���́u����v���W�ߞx�W�̂悤�Ȍ`�ɐ��{���āu����W�v�ɊW�̐[���������ɂ����肷����肾�Ƃ����Ď������ԓ��肳���Ă�������̂ł���B���ٕ̐����݂Ă����������͑啔���������Ⴂ�l�B�Ȃ̂ŁA���V�l���݂��b�ɌX����������Ȃ����A��搶���̌䊰�e���肤����ł���B���͎莆�̌`���Ƃ邩�A���ꕶ�ŏ��������Ƃ��v�����̂����A����ł͂܂��܂��V�l�������Ȃ肻���Ȃ̂ŁA�����ĕ���̂ɂ����̂ł���B�Ȃ��A���{�J���@�w�̊J��҂ł����鑷�c�搶�����Ƃ̂ق��u����W�v�̏o�ł����ʼn������āA�䐄�E��������������łȂ��A����ɐ��X�̖F��ӂ���z���������A��C�������肪�����K�^�����h�Ɋ����Ă��邱�Ƃ݂̂��̍ې搶�ɐ\���グ�邱�Ƃ������Ă������������B
�@���āA�M�̂܂ɂ܂ɏ����Ă݂悤�Ǝv���B�\�z�����Ă��Ƃ����킯�ł��Ȃ��A�������ӂƐe���݂̋C���̂Ȃ��ŁA�S�̒G�Ղ������Ȃ炷�@���ɑz�Ə�Ƃ̗����ɐ����ĂÂ��Ă䂫�����B����C�y�Ɉ�˂̏�A�Y�p�̕��ɕ���������悤�肤����ł���B
�@�Љ��`�ƗB���j�ς̎���
�@�Љ��`�ɋ�����l�X�͑����ꏭ�Ȃ���A����ɂƂ�߂��ꂽ���Ƃ��琶���闝�_�I��S��w�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B����̎l���ɓ��w�����N�̏H������}���N�X�̎Љ��`�Ɂu���Ԃ�v�͂��߂邪�A�������̓N�w�̓J���g�ɕ����Ă����Ǝv���B�}���N�X��`������ǂ�ł��A���̎Љ��`�ɔ�d���������Ă��āA�B���ُؖ@�̕��͉��ƂȂ��킩�����C�ɂȂ��Ă����B�B���ُؖ@��N�w�Ƃ��čl���邱�Ƃɂ��Ďh�������̂́A���炩�ɋ��s��w�ɍs���ĊԂ��Ȃ����×S�����搶�ɂ͂��߂Ă��߂ɂ��������Ƃ��ł������B���̕ɑ���킸��2�A3���Ԃ̐搶����̔ᔻ�I�������A�B���ُؖ@�̂ނ��������A���邢�͉��̐[�����v���m�炵�Ă��ꂽ�B���̌�A��w����A�B���ُؖ@�����^���ʂ�����Ńw�[�Q����c�E�c�ӓN�w�ɂ��ڋ߂��Ă݂��̂�����ǁA���ǂ͎Љ��`�ƕs���̎j�I�B���_���ӂ܂����B���j�ςɉ�A����������Ȃ������B�}���N�X��`�I�Љ��`�͂��̌�����̎v�z�̍���ɂ����āA�����܂ł��̎������������Ă͂��Ȃ��̂ł���B
�@���A�����Ŋw��I�Ș_�e�\����悤�Ȃ��ƂɂȂ������A�����Ȃ�ƎЉ��`�̘_�����Ȃ������̐^�������m�M���Ȃ��ł́A�ǂ��ɂ����͏����Ȃ��B�I�|�`���j�Y���Ƃ��������̌|�ɂ��Ƃ����́A�h���L�z�[�e�I�ɂƂ������������Ȃ�ɔ[�������B���j�ς����炯�o���ďo������ق��͂Ȃ������B�Ƃ��낪�Љ�I�����͐ӔC�������ɁA�ǂ����Ă����̔������S�����邱�ƂɂȂ�B�Ƃ����āA�B���ُؖ@�̐��E�ϓI�E�F���_�I���ȋᖡ�����ی��ɂÂ��Ă���킯�ɂ��䂩�Ȃ��̂ŁA�����ł͗B���j�ς��ƍl���Ă��闧��Ō����Ɍ����Đڋ߂�����������������Ȃ������B���30�N����ł���Ă��āA�����Ƃ̂Ƃ�g�݂�}��Ƃ��A�B���j�ς������̎v�z�Ƃ��Ē蒅���Ă������悤�ł���B���̔N�ɂȂ��āA�_���I�v���Ɋ����Ďv�z�]�����Ȃ���������Ȃ��ɂ͂Ȃ肻�����Ȃ��B
�@�Љ��`�͎��H�̖��ł���A�@���w�̗��_�Ƃ͕ʌ̖�肾�Ƃ��Ă��͂Ȃ����Ƃ́A�ꉞ���N�Ȏv�z�Ƃ�������B�����A���_�Ǝ��H�Ƃ̓�����������闧��ŎЉ�I�ɔ������Ă������Ƃ��ẮA�\���Ȏ��Ȕᔻ�̂ł��Ă��Ȃ������A���ՂɐV�J���g�h�ɌX�|����킯�ɂ͂䂩�Ȃ��B�܂��A���@�_�ł͎��Ȃ̎Љ��`����ϓI�Ȃ��̂ɑ����邱�ƂɂȂ炴������܂��Ǝv�����A�����݂͊ϏƓI����ł͔c�����Ȃ��Ƃ�����@�_�I���z�������͂Ȃ��Ȃ��̂ł���B
�@���܂�����Ă��邩�ǂ����͒m��Ȃ����A���Ƃ��Ă͗��_�Ǝ��H�Ƃ̓���Ƃ������Ƃ�O���ɂ����ĕ��������Ă����B����Ƃ����̂��A���_�Ǝ��H�Ƃ��s�ʂ�����ŁA���R�ɜ��ӓI�ɎЉ��`�̉��l�ς�I�����A����ɓK������悤�ɗ��_��g�ݗ��Ă�Ƃ����Ӗ��œ���Ƃ����̂ł͂Ȃ��B���j�I�Љ�̔F�������_�Ƃ������̂́A���Ƃ��Ɨ��j�I�Љ�I��̂̎��H�\�\�F���̑Ώێ��̂���̓I�S�ɂ���Č��肷��Ӗ����܂ށ\�\��}��Ƃ��Ă݂̂��̕K�R�����ѓO����Ƃ������j�I�Љ�����݂̑S�̓I�F���\�\�^�����\�\���u��������A�����ĔF����̂��̂��̂��u�ӎ���ʁv�ł��Ȃ��A�l�̎�ςł��Ȃ��A�܂��ɗ��j�I�Љ�̂Ȃ��ň��̎Љ�W�c�\�\���j�I�Љ�̍\���Ƃ��ɉ����\���ɋK�肳���\�\�Ƃ��Ă̂����I�Ɏ�̂��肤�邱�Ƃ����o���邩����A���H�̘_����}��Ƃ������Ă͐��藧���Ȃ��A���Ƃ���ϓI�ɂ͗��_�����Ǝ��H�����Ƃ���ʂ��Ă������ł����Ă��A���̐^���Ƃ��Ă͎��H�̘_����}��Ƃ��Ȃ����_�́\�\�Љ�I�ɈӖ��������_�Ƃ��Ắ\�\���肦�Ȃ��A�ȏ�̂悤�ȕ��@�_�I���o�������āA���_�Ǝ��H�̓�������ׂ����Ǝv���̂ł���B���ꂪ�j�I�B���_�Ȃ����B���j�ςł���A���j�I�Љ�ُؖ̕@�ł���A���ꂪ�^�����Ǝ��͍l���Ă������A���܂������v���Ă���B
�@�Ƃ��낪�A�����݂����j�I��̂̎Љ�I���H���_�@�Ƃ��Ă��邱�Ǝ��̂����j�I�Љ�̔F�������H�ƕs���ł��鏊�Ȃł���Ƃ݂鎄�̍l�����́A�����鎩�R�ُؖ@�ōs���Â܂�̂ł���B���j�I�Љ�܂�l�Ԃ̎Љ�̏o������ȑO�̒n���\�\���z�n�ł��F���ł��������\�\�A���邢�͐l�ԁ��Љ�ɑΒu���Ă����鎩�R�ɂُ͕ؖ@�͌�肦�Ȃ��̂��A�B���j�ς͗B���ُؖ@�̗��j�I�Љ�ւ̓K�p�ł͂Ȃ����A���Ƃ���Ύ�̂̂Ȃ����R�E�̔F���ɂ͎��H�͂ǂ̂悤�Ɋւ��̂��A�����Ɨ��p�Ƃ����ւ����\�\���j�I�Љ�̖�肾�\�\�Ȃ�A�@�B�_�I�B���_�ʼn��̂����Ȃ��̂��A���̂悤�ȋ^��͂��܂��]������������B�������R�Ȋw�̒m���̂Ȃ����ɂ͒��ق̂ق��͂Ȃ��B
�@�������A����Ɏ��R�E���@�B�_�I�ɂƂ炦����ɂ��Ă��A���ɂ͗��j�I�Љ�ُؖ@�I�Ɂ\�\�ُؖ@�I���o�Ƃ��Ă̔F�������̎�̓I�_�@�Ƃ��Ċ܂�Ł\�\���W���邱�Ƃ͂ǂ����^�����Ȃ����A����䂦�ɎЉ��`�̐^�������m�M����Ƃ�������ł���B���݂Ɖ��l�Ƃ��s�ʂ�����@�_�́A�����݂̈�ʓI���ۓI���o�����Ƃ�Ȃ��̂ł͂���܂����B�l�Ԃ̎Љ�́A���R�ՓI��ՂƂ��Ȃ�����S���V�����^���@���ɂ����j�I���E�ł���A�����ł͖ړI���邢�͉��l�����o����Љ�W�c�Ƃ��ĎЉ�I�Ɏ��H����l�ԑ�����̂��A���Ȏ��g���q�̂Ƃ��Č`���I�ɂ���ɓ��������A�������ċq�̂Ƃ��Ă̎Љ��l�Ԏ��g�̌����݂̈�_�@�Ƃ��ĔF�������o����̂ł���B������^���̂Ȃ��ł����A�ʂ��玿�ցi����Ȃ�`�ԕω��łȂ��j�A���ݍ�p�A���ݐZ���A�ے�̔ے�Ȃǂُؖ̕@�̏��_�@�����������\�\���j�̂Ȃ��Ł\�\�̂ł͂���܂����B�����Ă�����^���@���ɂ���Ĕ��W������j�I�Љ�Ƃ��Ă̐l�Ԃɂ����Ċ�̂ƂȂ�̂����R�i�����j�ł���A�����ɂ͌o�ώЉ�܂��ɉ����\���Ƃ��ċ����I�����I�ɂ͍����I�ȋK��҂Ƃ��Ă�����㕔�\���܂萭���A�@�A�����A�ӎ����܂߂��S�̂Ƃ��Ă̗��j�I�Љ���K�肷��i�B���_�j�ƍl����ׂ��ł͂���܂����B
�@���̂悤�Ɏ��R�ƎЉ�Ɋւ��鍪�{��ȍl�����̂Ƃ���Ŏ��͂Ȃ����h���Ă���B�����ȏ�̂悤�ɍl����ق��ɂ́A�Љ��`���v�z�̍���Ɉ��u�ł��Ȃ����A�@�A�����A�����Ȃǂ̗��_�Ɍ���ʂ킹�邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B������A���̗���ŏ�������b�����肵�Ă����킯�����A���ꂪ�}���N�X�̗B���ُؖ@�ł���ƒf�����鎩�M���������Ȃ��B��������������ł͎j�I�B���_���Ǝv���Ă���̂ł���B�����ď��Ȃ��Ƃ����̗���ŘJ���@�w���\�z���Ă����Ǝv�����A�^���Ȃ邪�̂ɐ��`�ł�����̂��ƍl���邱�Ƃɂ��Ă���̂ł���B
�@�Ƃ܂ꂱ�̐��E�ϓI���^�͕��܂Ŏ������������̂Ǝv���AHomo�@sapiens�ɂ�����i�v�́A���s�I�ȋ�Y�����ۑ�ł����낤���B�������A�ЂƂ͉��^��H���Đ����Ă�����̂ł�����܂��B�����A�܂����^�̂Ȃ��l�����A���C�Ȃ������肾�낤�Ǝv���B���̐��̘_�e���ӂ肩����ƁA�������j�I�K�R�����d�����Ă����A�܂�l�̜��ӂ������ĊѓO������j�I�Љ�̋q�ϓI�K�R�����w��̊�b�ɂ����Ă���̂ł���B���͂���𐳂����F�����Ǝv���Ă��邵�A������_���������Ƃ��ɂ͂����Ȃ�ɂ������Ȃ��Ǝv�����A����͘_�����d�ꂵ�����Ă����悤�ȋC������̂ł���B
�@���Ƃ��Ǝ��͗��j�I�Љ�̕K�R������̓I���H��}��Ƃ��Ă̂ݎ��Ȃ��ѓO���邱�Ƃ��������ė����͂��Ȃ̂ł���B��̓I���H����邩������j�ɂ�������R���̖�肩��V�����Ă͕K�R���̖�莩�̂��l���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��낤�B�q���f���u���N�哝�̂ɂ��������_���Ƃ��ɗD�ꂽ�Ƃ��낪����q�b�g���[�ɐ������Ƃ��邱�Ƃ͂Ȃ������ł��낤�A�ƃ}�C�l�b�P�́w�h�C�c�̔ߌ��x�ŏ����Ă���B�N���I�p�g���̕@���O���قǒႯ��Ƃ��������z�𗧂Ăė��j���݂邱�Ƃ��S�����Ӌ`�Ȃ��ƂƂ����͎v��Ȃ��B�������A�u�n��̐��E���_�v���Z���g�w���i�ɗ�擂���ꂽ�̂̓i�|���I���̖��^�̖��ł����āA�t�����X�̃u���W���A�v���̋A�������j�I�Љ�̕K�R�������ς����Ƃ͎v���Ȃ��@���A���j�I�Љ�̉^���ɂ�������R���̃������g�����܂�傫���c����̂́A�������Ď�̓I���H���̂��̗̂��j�I�Љ�I�펋�萫���̏ۂ��A�����݂̑S�̓I�F����r�����邱�ƂɂȂ�ł��낤�Ǝv���̂ł���B���̈Ӗ��ŁA�Љ�I���H�I����\�\���ꂪ���_�I�ȗ���Ȃ̂����\�\�ŕ�������������A���j�I�Љ�̕K�R�����ӂ܂��ā\�\�d�ꂵ���A�ދ��ł��炠���Ă��\�\�_���邱�ƂɂȂ炴������܂��Ǝv���B
�@����Ƃ���̐�������
�@���āA�E�̂悤�Ɉꉞ�l���Ă͂�����̂́A�Ƃ��Ă̐l�Ԃ̎������̎����͋��ۂ��������B�l�Ԃɂ�����s�����Ȃ��̌���I�Ȃ��̋��R�I�Ȃ��̓��A���������͏�̐��E�\�\�Љ�I��̓I���H�Ɩ����ł͂��Ƃ��Ȃ����A������̉e�ƂȂ鐶�̐��E���\�\�Ŏ��ꂽ���B���j�I�Љ�͌l�̐��U�ɂƂ��ċ��R�ł��邩�s�R�̖��^�ł���ꍇ�͌����ď��Ȃ��Ȃ��B���^��������̂͏�̐��ł���B�ё�������ɂ��u�V�v�̎v�z�\�\�Ƃ������͏�\�\�̕З���������̂��A�����l�̓`���I�S��Ƃ����ȏ�Ɋv���Ƃ̐S��ł���Ǝv����B���Ƃ�蓹���I�ȓV��Ƃ��_�A���Ƃ������`�ۉ����ꂽ���̂ւ̋A�˂ł��Ȃ��A����Ƃċ����ςł��Ȃ��B�����炭���j�I�Љ�ɂ�����̗L�����ւ̗B���_�I�Ȑ[����������̂ݐ�����B�ς̐S���Ƃł������ׂ��ł��낤�B
�@�����܂ł��Ȃ����͊v���Ƃł͂Ȃ��B�����A������20���I���t���Ă����\�\��r�I�g�p�̑��������\�\�V�����̈�l�Ƃ��āA���œV�ɖ₤�Ƃ������S���������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���Ƃɐl���̋�育�ƂɁ\�\��n�ɏo������D���ŁA��킩��A���čr��͂Ă��c���̓y���ӂ�ŁA�����Ĕs����ނ����āA�w���Y�Ǘ��_�x���o�ł��āA�����̋��������āA���邢�́w�^���̂Ȃ��̘J���@�x�������ăh�C�c�ւ̍q�H�ɔ����āA�җ���}���āA�����Ă��܂��B���̐S��͕K�������Љ�I���H����̓����ł��Ȃ��A����Ɩ���������̂��Ƃ��v��Ȃ��B
�@�ЂƂ͎Љ�Ƃ��Ă̐l�Ԃ̐��ɂ����ď[�����u�����Ȃ���́v�ɂӂ��Ƃ����Љ�I���H���ݏd�˂Ȃ�������A�B�ς̋��ɂ�����[�����m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��v���B�Љ�I��̓I���H�̖R�����w������́A�ɂ����Ď�ϓI�Ɂu�����v���ӎ����邪�A�����ꂻ�̎�ϐ��͐����̏�ŘI�悹��������Ȃ��B����͈�̍��܂ł��낤�B�������肱����̂͗��j�̍ق����o�債����̓I���H�ł���A����ɂ���ĎЉ�Ƃ��Ă̐l�Ԃ̐^�̖�������̓�������Ƃ������̂ł����낤���B�����āA���̂Ƃ��ɂ����I�X���鑓�V�����ŌƂ��Ă̐l�Ԃ̗L������������̐��E��B�ς̐S����܂��̂ł͂���܂����B
�@���Ƃ��Ǝ��ɂ́A�Ⴂ������Љ�I�������͂Ȃ�鎞�Ԃ̂Ȃ������͂܂��Ƃɖ��C�Ȃ����̂��Ǝv���Ă���̂ł���B�Љ�l�Ƃ��Ă̐l�Ԃْ̋��ƘA�т̐��ɂ�����Ƃ��Ă̐l�Ԃ̎��H���A���̐l�̗��j�I�s�ׂł���A���̍s���\�\���t�ɂ͋��炪�A�w�҂ɂ͗��_�I�������A�^���Ƃɂ͑g�D�Ɖ^�������̒��S�ƂȂ�\�\�́A���j�̖@��ōق���ׂ��ł���B��������͗��j�ɂ䂾�˂��ׂ����ł���B�����ɂ͗L���҂̐S���͖��p�ł��낤�B�����A�Љ�Ƃ��Ă̐l�Ԃ̗��ꂩ��ꉞ�͂Ȃ�Ă����V���ƒB�ς��āA�Ƃ��Ă̐l�Ԃ̐�����Ƃ��A���ꂪ�ǂ̂悤�ɉ߂�����悤�Ƃ��A���Љ�I�e���̂Ȃ�������͔ނ̎��R�E���ӂɋA�����ׂ��A�����ޓƎ��̍K�����Ƃ��S���ɂ�������̐��E�ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ȗ��j�I���Ԃ̊O�ɂ��鐶���Ŗ����e���Ƃ͎��ɂ͎v���Ȃ��B�v�`�u���I���ǂ����͒m�炸�A���ɂ͎Љ�I���H��Փ|��痂����l���͂�肫��Ȃ����A�Љ�ɋz������Ă��܂�Ȃ��������̂����Ă��������������Ǝ��o���Ă���B���Ƃ��]�T���l�Ԍ`���ɕK�v������Ƃ����悤�ȖړI�ӎ����������ދC�͂��炳��Ȃ��B������̗h�������Ԃł���悢�B�����܂��A�����Ȃ��l�Ȃ�A���̓I�ɂ����_�I�ɂ��L���Ȃ�l�₪�A���̗L���Ȃ鐶�̂��ׂĂ�茾���߁A�����@���ɕ�����������̂ł͂���܂��A�Ƃ��v�����肷��B
�@�Ƃ��������A�S���ɂ��������Đ�����]�T�����R���Ȃ��悤�ȎЉ�͐^����Ƃł���B�q�ϓI�ɂ������̎Љ�Љ��`���狤�Y��`�ւƐi�ނ��̂��Ƃ���A�ЂƂ͂��L���ȗ]�T�Ǝ��R�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂���܂����B�����Ȃ邱�Ƃɂ���āA�l�Ԃ͂��[���l�Ԏ��g�\�\�Љ�Ƃ��Ă��Ƃ��Ă��\�\��m�肩����A���Ȃ킿���ȑa�O���~�g����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���Ƃ�茻���̊��Љ�ʼnB������������ł���Ƃ͎����v���Ă��Ȃ��B�������X�ɗV�т̗]�T���Ђ낰�Ă䂫�����B�V�тƂ����Ă����ɂ͂���́A�z�C�W���K��J�C��������`���悤�Ƃ�����AAgon�i���Z�jAlea�i�T�C�R���V�сj�Ȃǂɕ��ނ��Ă݂�悤�ȉ��I�s�ׂ݂̂ł͂Ȃ��B�ނ���Љ�I���H�ɖ��S�ȗV�ѐS�Ƃ������A�v�ړI�I���|�ۂ���S���ւ̒^�M�Ƃł������悤���B�Ƃ��������ߗ��v�ړI�I�ɒm�肽�����Ƃ�ׂ��Ă݂������Ƃ����܂�ɑ����B���������̑啔�����J���@�w�҂Ƃ��Ă̎Љ�I�����Ƃ͕ʂ̐��E�����Ȃ�ΗV�т̐��E�̂��ƂȂ̂ł���B������������悢���A�����Ȃ���y����ł���B
�@��N8��15���A�s��30���N�ɂ������đf�Ă̒قɁu���^�H�`�x�����v�Ə����č����̖�Ԃ��������B���͂����炭�����ł��낤�A���͐��U�́A�����Č��݂̊�]�ł�����B
�@��z�I���摜
�@��w�����炵���Ȃ��ƂЂƂ̌����̂́A��낸�ɋΌ��łȂ�������u���킩��v �̈����A�u���Ȕᔻ�v�Ȃ��^�J�h�ł�������A�ׂ��߂�������k���فE���ف\�\����������܂�w��I�����̂Ȃ��������\�\���G�R�Ɠ���܂������蓙�X�ɋN������Ƃ��낪�����Ǝv�����A�����ł͎��̊w�⎩�̂��͌^�I�łȂ��̂��낤�ƍl���Ă���B�܂�A��w���������ƓI�Ȋw��ł͂Ȃ��f�l�I�\�\���{��`�I�Ƃ����Ă悢��������Ȃ��\�\�Ȃ̂��B��w�����\�\����҂̖ʂƊw�҂̖ʂ��I�[�o���b�v���Ă���\�\�炵����ʂ̂́A���̔��含����͌^���Əd�Ȃ��Ă��邩��̂悤�ł���B�ǂ��݂Ă����̘J���@�w�͓`���I�Ȗ@���ߊw�Ƃ��Ă̘J���@�w�ɂ͂����܂�Ȃ��B�S�����z�����Ȃ肿�����Ă���B����]�߂��O���@�̐��x��w���̏Љ���낭�ɂ��Ȃ��@���w�ҁA�C�f�I���M�[�ᔻ�Ƃ����������_�ɗ�ᎂ����A�Ƃ��ɂ͐����ᔻ�E�Љ�]�_�E�J���^���_�ɂ܂Ń��{�����Ă���u�Ԃ��v�w�҂Ƃ����ẮA�u�w�҂炵����ʁv�̂��A�����Ƃ����ɂ��B���͊G���D�������Acubis��e�̉�͓`���I�Ȕ��ς��͂ݏo���Ă��Ă��܂�D���ł͂Ȃ��B�ɂ��S�炸���̊w���̓L���[�r�b�N�Ȃ̂ł��낤�B�u�����ɐ^���ɔ���w����������邩�v������肾�Ǝ����ł͍l���Ă����B���������_�����������甭�z���Ă��闝�_�̂���ł���B
�@���͎����g�́A�����݂������I���S�̓I�ɖ₤�N�w�I�v�l��ʂ��Ȃ��悤�ȁA�@�Ɋւ���w��̐��ƂɂȂ邱�Ƃɂ͏]�����܂�M�ӂ����������Ƃ͂Ȃ������B����ƂāA�����݂̏��_�@�Ɩ@�I�_�@�Ƃ̏��W�̔F����}��Ƃ��Ȃ��u�@�N�w��ʁv�̐��ƂȂ���̂��u���C�ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@���Ƃ��ŏ�����f�l���̊w������A�L���[�r�Y���I�w�������Ă悤�Ȃǂƍl���Ă����킯�ł͂Ȃ��B�J���@�w�̏���B�₳�܂��܂Ȗ@�v�z���狳���������Ȃ�����䂪�܂܂Ȏ��͊S�̕����܂܂ɍl������_�����肵�Ă��邤���ɂ����������i�̊w��ɂȂ����̂��낤�B���邢�́A���Ƃ��ɑ�w���������ƂɂȂ낤�Ƃ����ړI�ӎ��������Ă͂肫���ďo�������킯�ł͂Ȃ�����ł����낤���B
�@�Ք��A�䗬�̊w��łƂ��������w�E�̈��������Ă䂯���̂́A�K���ɂ��Č��I�@�ւƂ��ɐ��{�@�ւɎg���Ȃ��������Ƃɂ��Ƃ��낪�����Ǝv���B�����Ƃ���E�����w�|��w�͍����A�s����w�͌����ł��邪�A���Ƃ����Ă���w�́A�����ƌ����E����̎��R�̑��݂����ł���B�������w�₷�邱�Ƃ��{�E�����猋�\���ɁB�Ƃ��ɒn�������̘̂J���u���Ȃǂɏ�����邪�A��������ɂЂ��邽�߂Ɂ\�\�Ȃ�ׂ������n����̋��ւ̗��\�\2�A3���Ԏ��p�@�w�̐��ƂƂ��ĉ���I�u���������ڂ͉������邱�Ƃɂ��Ă���B���N�̉ċx�݂ɂ͂��߂ĉ���ւ䂭�@��������B�Ђ߂��̓�����얻�̓��܂ʼn��V���Ƀn�C�r�X�J�X�̉Ԃ�����Ă܂��Ȃ���A���Â��Ɩ{�y�͉���ɕ����ڂ�����͂����Ǝv�����B
�@�Ƃ����������{�@�ց\�\�e��R�c���J���ψ���̈ψ��Ȃǁ\�\�Ɏg���Ȃ������������Ł\�\�����Ƃ����܂�Ă����₵����������Ȃ����\�\�A�w��E�����̎��R��\���̎��R�́A�Љ�I�ɂ��A�܂��u�`���l��v�I�\�\����ɂ͎ア�̂����\�\�ɂ��S������Ȃ��ł������A�����̃y�[�X�𗐂���邱�Ƃ��Ȃ������B�킪�l���ɂƂ��ċM�d�Ȃ��Ƃ������Ǝv���B��������A�u�ԁv �u�v���E���[�o�[�v�Ȃǂ̃��b�e�����͂�ꂽ���Ƃ̌����ł��낤�B
�@�u�ԁv�̃��b�e�����ŏ��ɂ͂���Ă��ꂽ�̂�GHQ�ł������B���Y�}���������Ƃ݂��Ă����u�[�����s�v�V���Ђ̘J���g�����ł����Ă݂�AGHQ���}�[�N�����̂����R�ł��낤�B�Ƃ��낪�A�V���L�ҁ\�\�����Ȓn�����ł��\�\�ŁA�V���J�g�̑g�����ƂȂ�Ƃ��Ȃ�Љ�I�ȉe�������炵���A�܂��w���{�J���@�_�x�̒��҂ŁA�V���̘_���������Ă���Ƃ����킯�ŁA�������猻���I�ȘJ�����Ɋւ��ču��������A���M����@��^����ꂽ�B������̎���ύX�̂��ߋ���̌������ɕ��A���Ė@���w�̓k��C�Ƃ����Ȃ����]�T���Ȃ��A����ƂĐV���Ђ̒�����d���̂ق��́A�Ђ�����Ǐ��ɒ^��J�[�h�����ȂǂƂ����{�i�I�Ȋw������Nj�����قǂɁu�w�ҁv�ҋƂɎ������Ȃ��A�܂����ق��Ă���ɂ͂��܂�ɂ����_�̎��R�ւ̋������傫�������B��킪����̐����ɂƂ��āA�ʗ_�J�Ȃ��ԌĂ����A���Ƃ�蕨�̐��ł͂Ȃ������B
�@���x�u����W�v�삵�Ă��āA�����̒���W�ɂ͂������Ȃ����A�ނ��뎞�オ���܂������Ƃ炦�ėL�������킳���ɏ������ė������̂��A���ܑQ�����Ȃ��Ƃ���ǂ����������R�ȋC���ŕҐ����Ă���Ƃ����A�����Ȃ�Α��҂ł���u���ȁv��f�ނɂ��āA���Ȏ��g���V���Ȓ�������Ă���悤�ȋC�ɂȂ邱�Ƃ������������B�ߍ]���N���c�ɂ���A�O�r�J�g�̑呈�c�ɂ���A�C���X�g�A�X�g���X�g�Ȃǂɂ���A����ɂ��ĉ�����������M���Ă��Ă��邪�A����͌������̓k��C�Ƃɂ����炸�A���������l�O�̘J���@�w�҂Ƃ��ĘJ���g���������Ă����ɕ��肱�܂ꂽ���̎��̉^���ɂ��Ƃ��낾�Ǝv���B�J�������ᔻ�⌠�������_�ɂ��Ă��Љ�^�����������肽�Ăď��������A�����Ď��̕��ł͎�̓I�ɎƂ߂��A�Ƃ����W�̎Y���ɂق��Ȃ�Ȃ��B�P�����������K�s�K���l����]�n�̂Ȃ��A�̂��҂��Ȃ�Ȃ����������̂��Ƃ��v���B
�@����ɂ��Ă��D���Ȃ��Ƃ������ĐH�킹�Ă�����Ă����̂�����\���Ȃ��ł���B��w�̗��v��АM���\���ēs���E�s�c��Ȃǂɂ������������˂Ȃ�ʗ���ɂ������Ă���́A���ɂ͎Љ�I�\���������������邱�Ƃ�����A���ԓI�S���������炩�͑������悤�ł���B��������ł͑�w�̊O�ł̔ς킵���t��������Ɩւ�̂��e�ՂɂȂ������Ƃ��������ł���B
�@�ԍ��Z�{������̗�����L���o���[�ւ͍s�������Ƃ��Ȃ��A�s�������Ȃ����A���̖������Ȃ��B��̂��ł��O���̗����ł����ގ��͎����悤�Ȃ��́A�������t�����킷�̂͗F�G�̐��E�ɏZ�ސ��ƁE��`�I�l�Ԃł͂Ȃ��A���܂ł��e��������łȂ���F�l�B���B�Ƃ��ɂ͊җ�A���Ƃ����ć����Ղ聍���y���ނ��Ƃ�����B���}�����A���������V�����Ǝv���B����ɂł�������炩�~�X�e���A�X�Ȗ��킢�[������������ƐS��厖�ɂ����G�X�Ƃ��ĕ����Ă݂����C�ɂ��Ȃ�B
�@�H��ɍ���
�@�v���������Ƃ��ނ����������Ƃ��菑���Ă������̂ł��邪�A���e����ړI�ɂ��ď��������Ƃ͂Ȃ������B��������Ȃ��{���肾���A���肪�������ƂɂƂ��Ɏ������킯�ł��Ȃ��̂ɂ悭���o���C�ɂȂ�o�ŎЂɌb�܂ꂽ���̂��Ǝv���B����ł��w���Y�Ǘ��_�x�̈�ł̈ꕔ�Œ����o�Y�̔�p���Ђ˂�o���\�\�ޏ��͂��łɑ���l�������炦�āA�ډ��f���b�Z���h���t�Ɋj�Ƒ��ŋ��������܂��Ă���\�\�A���[�͎����̌������Ƃ����āu����W�v��1�E
2 ���̈�ł������p�ƐV�����s�̏��g���Ƃɂ��Ă��B���n���ł̂����₩�Ȗ����Ƃł��������̂ł��낤�B�R�����Ƃ�����ɂ͂������Ȃ��̂��B
�@�����ē�l�̖��͊F���ꂼ��ɘV����̔ޕ��Œ���ƂƂ��Ɏ����̉ƒ�������A�l���̍q�H�𑖂邱�ƂɂȂ����B�������ɗ��Ă�������A���̎q���̍�����̋��F�����́A�{��Ђ̖���В��̊̐���Ŏ��̂��Ɩ锼�̍��c�n��ɐȂ�݂��Ď��������Ă��ꂽ�B�u�����̌������̖�̕��e���Ԃ߂���܂���v�Ƃ������Ƃ炵���B�Ƃ����������[�j���_�̃l�N�^�C�����߂Ĕ����̔t�����������B���������Ƃł������B
�@��ꂫ�������[���Q�����ƁA��K�̏��ւɍ����B�q�������͉ł��A�u����W�v���ǂ���犮�������悤�ŁA���܁A�X���킽��H�̖�ɁA�⛋���鎩�R�̏�ɂЂ���Ȃ���A���̕��͂�����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@1976�N�@�H�ފ݂̖�
�@�m�NjL�n
�@�u����ژ^�\�\�킪����M���̋O�Ձv�Ɂu���D��k�v�̏����Ƃ��āA�ȉ��̂悤�ɋL����Ă���B
�@�u����W�e���̌�����W�߁A���s�̎��A�����������A����ɐ��A�Έ�A����ƕ��q�̒Z���Ɖ�y�̂��̊��z����ҏW���āw�����c�R�x�Ƒ肵��100�ł̏����q��W�W�҂ɏ{��Ђ����悵���B�w�����c�R�x��12��15���t�B10����12��15���t�B����͂킪�����L�O��������ł���B��̏��N�ɂ͖ѕM�ŃT�C���������B���c�搶�̗�O�ɂ́u�ʗ��L�]��v�Ə������B���̂ق��u���]�������v�u�n��T���l�ԑ��@�\�z�v�z�O�v�u�V�ߖ��D��ہv�u���^�H�`�x�����v�u�`�C��H�v�u�@���V�v�ȂǁB���[�ɂ͉̈��w���̐e�̂Ƃ߂��I���đ����@���H�ɘV���Ȃށ@�������������āx���������B�v
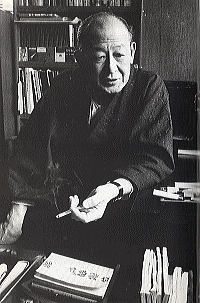
���c��Y
1914�N�i�吳3�N�j 5��25���A�x�R�������s�ɐ��܂��B
1952�N�i���a 27�N�j8���A�����s����w�����i�l���w���j�ɏA�C�B
1965�N�i���a 40�N�j4���A�����s����w�@�o�w�����ɏA�C�B
1973�N�i���a 48�N�j4���A�����s����w�����ɏA�C�i�`81�N3���A2��8�N�j�B
1997�N�i����9�N�j 5��16���A�����B���N82�B
���ҁ@�W�F�{����ҏW��
�@�ӔC�ҁ@�F�ؓ��m��@
�@�ҏW���́F�Έ䎟�Y
�@���@�@��F�ѓ��M��
�@�t�o�F2014�N3��25��
�@�X�V�F2014�N4��18��
�@�X�V�F2014�N4��21��
�@�X�V�F2014�N5��25��
�@�X�V�F2016�N5��23��