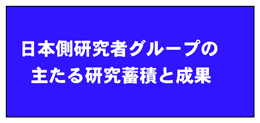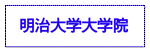社会的排除への日本とイギリスにおける社会的企業の取り組みの調査・研究

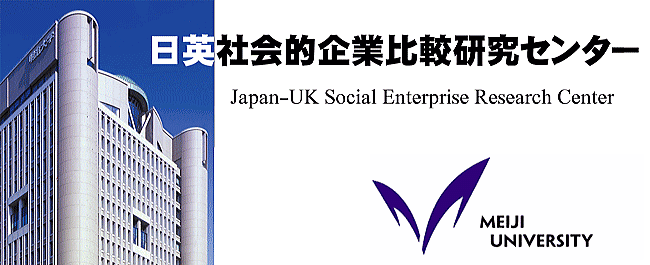
明治大学特定課題研究ユニット
「日英社会的企業比較研究センター」のホームページへようこそ。
1 日英比較研究の目的
1-1 研究の目的
本研究の目的は主として2つである。第一が、社会的企業に関する日英比較研究と、この研究を通じて得られた知見を世界に発信する日本のキーステーションの構築である。第二が、これらの調査研究と通じて実施する予定の本学を中心とする若手研究者の育成である。
第一に、日英の典型的な社会的排除問題に取り組み、地域社会に密着しながら、一定の仕事を生み出している労働統合型の社会的企業(WISE)に注目し、実践家との密接な協力関係の下、①社会的企業における社会的包摂過程を明らかにするためのミクロな研究と同時に、②社会的企業のサスティナビリティを可能にするための制度デザインを明らかにするための組織論的・政策論的な研究を行うことを目的としている。
このような調査研究を、日英社会的企業の国際比較調査として行うことで、日本における社会的企業の特質や抱えている課題を浮き彫りにし、かつ、日本における社会的企業を促進するための具体的な政策提言が可能となる。
加えて、③上記のような研究から得られる示唆を適用可能な社会問題の現場として、東日本大震災の被災地を捉え、被災地において活動を始めた社会的企業と連携しながら、被災地での「社会的企業による社会的包摂」のプロセスに参与観察の形で加わりながら、本研究を実践的な貢献へと結びつけることも課題としている。
なお、上記の①に関しては、社会的に排除されてきた当事者のヒアリング調査も行いながら、社会教育学等の知見も援用しつつ、社会的企業による社会的包摂のミクロなプロセス、すなわち、社会的に排除された人々のエンパワーメントのプロセスを実証的に明らかにすることを目指している。また、後者の「制度デザイン」に関しては、以下のようなことが想定されている。
社会的企業による社会的包摂を可能とするには、社会的企業における複数の目標(たとえば、単に量的に労働市場に何人送り込めたかといったことだけではなく、居場所の形成、福祉的なサービスの提供等、多様なエンパワーメント・プロセスの構築が重要な目標となること)を維持可能な「制度デザイン」(Bode et al.)が必要となる。
それゆえ、社会的企業が発展していく際の基盤条件として、①地域社会におけるネットワーク、②基盤となっている中間支援組織の有無や果たしている機能、③行政とのパートナーシップのあり方が明らかにされる必要がある。この観点から本研究は、社会的企業における社会的価値を評価する方法に注目し、どのような社会的・制度的条件が、社会的企業のサスティナビリティにとって重要な意味を持つのかを明らかにしていくことを課題としている。
第二に、上記の国際比較研究に本学の若手研究者ならびに大学院生を参与させることを通じて、近未来における社会経済システムについて考察する機会を提供し研究者の育成を図ることを目的としている。
1-2 研究の学術的背景
1-2-1 日本における「社会的排除」問題
今日、社会的排除の解決は、先進国共通の極めて大きな課題である。日本においても、急速な労働市場の二極化に伴う雇用レジーム(宮本太郎)の変容、少子高齢化、単身家族(晩婚化・非婚化)の増大といった趨勢の中で、企業や家族によるセーフティネットは弱体化し、リスクの個人化(自己責任)と同時に、「無縁社会」と呼ばれているように、社会的に孤立した人々が増大してきた。
このような個人化の進行の中で、障がい者(特に精神障がい者や知的障がい者)、ひきこもりの若者、ホームレス、高齢者等は、とりわけ脆弱な状態にあり、労働市場から排除されていると共に、地域コミュニティにおいても孤立し、社会参加が困難な、正に「社会的排除」と呼ばれる状況に陥っている。また、3.11以降、東日本大震災による地震・津波被害と原発問題により、住居や仕事、そして家族を失った被災者が数十万人規模で生まれており、こうした問題も、日本社会における社会的排除に一層拍車をかけている。
そして、日本においても、労働者協同組合やワーカーズ・コレクティブといった協同組合の系譜に位置する社的企業をはじめ、障がい者雇用、ホームレス支援、若者支援等の分野で数多くの社会的企業が形成され始めている。共生型経済推進フォーラムや社会的企業研究会といったネットワークも形成され、社会的企業のための法人制度(協同労働の協同組合、社会的事業所)を求める運動も活発化してきた。また、政策的にも、民主党の新成長戦略や「新しい公共」促進会議等で、社会的企業が、地域社会で雇用を創造する重要な担い手として注目を集めている。
こうしたなかにあって、隣国韓国において、2006年12月には社会的企業育成法が制定されただけでなく、2011年12月に制定された協同組合基本法の第4章に社会的協同組合が規定されたことも、わが国における社会的企業研究に弾みをつけるに至っている。
1-3 国内外の研究動向
日本における社会的企業の調査研究をめぐっては、理論研究と実証研究をめぐって二つの問題を指摘することができる。
第一に、社会的企業に関しては、国際的に見た時、二つの理論潮流の存在を指摘できる。一つは、社会的起業家を重視した米国の社会的企業論であり、もう一つは、欧州のEMESグループに代表される社会的経済・連帯経済論を基盤とした社会的企業論である。日本では、この内、前者のように、社会的企業を、端的に、社会的起業家の強力なリーダーシップに率いられた「社会問題をビジネスで解決する」事業体として捉える傾向が強い。とりわけ谷本寛治等、経営学者による研究や経済産業省を中心とした政策文書においては、社会的企業を強調しつつも、①市場からの収入によって財政的な自立を達成することの要請と②小さな政府を補完する新たな公共サービスの担い手としての期待を色濃く読み取ることができる。ここでの社会的企業とは、端的に言って、NPOの営利企業への制度的同型化を促進するロジックだと見なすことができるだろう。
しかし、こうした日本での社会的企業概念の導入のされ方は、実際の社会的企業の実態から考えると、問題が多い。なぜなら、そもそも、困難な条件を抱えた生産要素(労働力)と購買力のない地域市場という負の条件を抱えた社会的企業を、市場競争で生き残り可能な事業体として想定することには無理があり、また、過度の企業化は、大規模化・官僚制化等を伴い、ボランティアを含む多様なステークホルダーの参加、地域密着、幅広いネットワークといった社会的企業の「社会性」の重要な要素を掘り崩す危険性を有しているからである。
したがって、本研究では、社会的企業を過度に市場主義的に捉えるべきではなく、社会的企業が、その社会性と企業性のハイブリッドな状態を維持しながら、持続的に発展していくことが可能な制度的条件や中間支援組織(インフラストラクチャー組織)を含む社会的な基盤条件について明らかにしていくことが重要となる。
第二に、日本の社会的企業自体に関しては、アド・ホックなケース・スタディは散見されるものの、包括的な実態に関する調査研究は未だに手つかずの状況にあると言わざるを得ない。
そもそも、日本の場合、社会的企業という定まった法人格があるわけではなく、事業型NPO、コミュニティ・ビジネス、ワーカーズ・コレクティブ等、様々な名称が用いられ、法人格も、NPO法人、有限会社、企業組合、任意団体等、多岐にわたる。そのため、社会的企業の実証的な調査研究を行う際に、社会的企業をどのように操作的に定義すべきか、社会的企業の事例をどのようにして包括的に収集することができるのかといった問題にぶつからざるを得ない。
こうしたことから、本研究では、日本で社会的企業の実証研究を展開していく際に、①社会的排除が典型的に現れている領域(貧困問題、障がい者、ホームレス、引きこもりの若年者等)ごとに、②社会的企業として認識しうる諸々の運動の歴史的系譜(労働者協同組合、ワーカーズ・コレクティヴ、共同連等)についても認識した上で、③各問題領域や運動の系譜において、中核となっている中間支援組織で活動する実践家と協力しながら、共同で調査研究を行っていくことが肝要だと考える。
第三に、社会的排除問題の解決主体として社会的企業を捉えるなら、その主要な社会的機能は、社会的包摂(social inclusion)であり、逆に言えば、社会的包摂の実現可能性が社会的企業自体の正当化基盤だと認識できる。
しかし、そうした社会的企業による社会的包摂のプロセスが具体的にどのようなものなのか、すなわち、社会的に排除されてきた人々が、社会的企業において、どのようなエンパワーメントのプロセスを経て自信を回復し(心理的エンパワーメント)、社会参加の力を付け(社会的エンパワーメント)、ひいては仕事の場を得て自立していくこと(経済的エンパワーメント)が可能なのかといったことは、これまで欧州のEMESグループをはじめ、詳細に説明されてきたとは言いがたい。
したがって、本研究のなかで、社会的に排除されてきた人々の集合的学習(collective learning)や成長のプロセスをめぐるミクロ・レベルでの実証研究を行う必要がある。そして、ミクロ・レベルにおける社会的包摂を可能とする組織条件、並びに、組織評価のあり方についても検討する必要がある。
最後に、わが国における社会的企業研究は、海外での研究成果を日本に紹介する、または、日本に適用しようというものが多く、日本からの研究成果の発信が十分になされてきたとは言いがたい。このことは、本研究に携わる研究者たちが2009年から行ってきたイギリスの研究者との意見交換や、2010年EMESにおける日本報告パネルに参加したことなどから明らかになってきた。
本研究では、成果の国際的な発信を意図し、日英両国での論文執筆と研究報告、さらには国際インポジウムの開催を計画し、研究成果を広く世界に問うことも目的としている。
1-4 本研究の学術的な特色・独創的な点および予想される結果と意義
以上の諸点を踏まえるならば、本研究には次のような特筆すべき点がある。
(1)イギリスの社会的企業研究者並びに実践家との共同研究に基づいた「日英社会的企業の国際比較研究」を通じて日本における社会的企業の特質と課題を浮き彫りにするとともに、社会的企業の持続可能性を追究することにより、社会的企業に関わる国際的な情報発信のための日本のキーステーションを確立することができる。
(2)失業などによる労働市場からの排除に対応する社会的包摂に焦点を置いた、日本における社会的企業の初めての本格的な体系的調査・研究である。
(3)社会的包摂に関するミクロのエンパワーメント・プロセスと、それを可能とする組織的および制度的な諸条件を含むマクロのプロセスとを繋ぐ学際的研究である。
(4)日本とイギリス―さらにはイタリア、フランス、デンマークなど―における社会的企業の実践家とのこれまでの協力関係を基盤にして調査・研究をすることにより、東日本大震災によって惹起されたさまざまな社会的排除に直面している被災地の人びとが、雇用の創出と地域コミュニティの再活性をコアとする社会的包摂の実践活動に参加し具体的に関わるシステムを創り出す実践的な研究を展開する。
またこの研究は、その成果を通じて、被災地に限らず、さまざまな原因で社会的排除に直面している他の地域コミュニティの経済的、文化的、自然的、社会的、人的な諸資源を利用する社会的企業の研究と実践に大いに資するであろう。
(5)本研究プロジェクトは、本学並びに本学出身の若手研究者および本学大学院生を研究協力者並びに研究補助者として本プロジェクトに参加させることにより研究者の育成を図ることを重要な目的のひとつとしているが、本学および本学大学院を、イギリス、イタリア、デンマークなどの大学―例えば、イギリスのイースト・ロンドン大学、シェフィールド大学、オクスフォード大学などをはじめイタリアのソレント大学、デンマークのロスキレ大学など―の若手研究者と国際的な比較社会的企業研究を行う「国際研究拠点」となし、社会的企業の国際的な研究および教育の拠点とすることを可能とする。