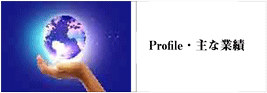住宅・マンション・土地のご相談は手島繁一のページへ
ようこそ手島繁一のページへ
手島 繁一(てじま しげかず) 1966年北大入学。北大教育学部卒。大学「紛争」時の北大学連委員長。元全学連委員長。法政大学大原社会問題研究所研究員および法政大学社会学部講師・協同総合研究所研究員などを務めた。
北海道にユーターン後、北大イールズ闘争や白鳥事件の歴史的分析につとめ、戦後の社会運動における学生運動史などを新しい視点で解明。
information新着情報
◇北大のイールズ闘争
蒼空に梢つらねて ― イールズ闘争・安保闘争、北大の自治
新着情報
 |
蒼空に梢つらねて イールズ闘争60周年・安保闘争50周年の年に 北大の自由・自治の歴史を考える 「北大5.16集会報告集」編集委員会 編集委員長 手島繁一 編集委員 大橋晃 河野民雄 國中拓 佐々木忠 白樫久 高岡健次郎 中野徹三 藤倉仁郎 森谷尚行 発行:柏艪舎/発売:星雲社 2011年2月 A5判並製 |
あとがき 手島繁一 2016.02.22UP
この本ができる経緯については、すでに本書の随所で語られている。だからという訳ではないが、最初に少しばかりこの本の発刊に至るまでの個人的な思い出を記すことをお許し願いたい。歴史が現前として甦る瞬間――わたしが「イールズ事件の首謀者」の一人である梁田政方さんと出会った瞬間は、まさにそうであった。二〇〇六年二月のことである。わたしにとって事件の当事者が、失礼ながら、「まだ生きておられる」ということがにわかには信じられなかった。というのも、わたしがこの大学に入学したのはイールズ闘争の十六年後であり、その当時のキャンパスでは歴史というより伝説としてその闘いが語り継がれていたからだ。
伝説は時の経過とともに初発にあった活き活きとした歴史的事実が褐色し、脚色され、神聖化されて神棚にでも祭り上げられるのがその運命である。だから、僅か二十年にも満たない時間の経過で歴史が伝説となるのなら、それが風化し忘却されるのもまた時間の問題であったかもしれない。わたしにとって、歴史を神棚からみずからの手に取り戻すきっかけとなったのは、梁田さんとの邂逅であり、そこから次々と広がっていった「イールズ世代」や「六〇年安保世代」の諸先輩との出会いであったが、それはまた歴史を遡及する旅の感動そのものであった。歴史を叙述する、あるいは語り継ぐという営為の源にあるのは歴史への感動である、とわたしは思う。
ところで、歴史への感動を呼び覚ますうえで、当事者の体験とその証言がもつ意味は計り知れなく大きい、と日高六郎は強調する。日高によれば、体験者の証言がもつ積極的側面は非体験者の知識と思想に「体験者が持つ独特の感覚と生気を吹き込むこと」にあり、その独特の感覚とは時代の全体的な雰囲気および個々人の時代認識についての感覚である、と述べている(『戦後思想を考える』岩波新書、一九八〇年)。
本書には四十人を超える方々から原稿をお寄せ頂いた。それぞれの原稿で書かれていることはそれぞれの人生の一断面でしかないかもしれないが、そのなかに「時代の全体的雰囲気と個々人の時代認識についての感覚」を読み取っていただければ、編者としてはこれにまさる喜びはない。E・H・カーの言葉を借りれば「人々の行為の背後にある思想を創造的に理解する」ことなしに歴史を甦らせることは出来ないのだから。
もちろん、体験や証言が常に真実を保証しているとは限らない。体験や証言によってのみ歴史を再構築することの危うさを充分承知のうえで、なおかつそれを単なる歴史のデータとしてではなく、それぞれのかけがえのない人生そのものが凝縮された作品として扱いたい、とわたしたちは願って編集作業を進めてきた。それゆえ、それぞれの証言原稿には誤字脱字の補正などの最低限の編集を加えるにとどめている。それがために読み手にとって何らかの不都合が生じたとするならば、それはひとえに編集の任に携わったわたしたちの責であって、ご事情を斟酌のうえご寛容を願うほかはない。
もとより、わたしたちは戦後北大の自由・自治・反戦・平和の歴史を掘り起こし、検証し、共有することを集会や報告集の目的としてきたが、わたしたちの作業はそのごく一部をなすに過ぎない。例えば、証言原稿を誰にどのようなテーマでお願いするか、ということですらそれ自体がそれぞれの歴史観、歴史認識に関わる大問題でそう簡単に結論を得られるような問題ではない。年代やテーマの選び方に偏りがあるとの批判は甘受せざるを得ない。しかし、考えてみれば、歴史は常にそれぞれの時代によって生み出されるとともに再定義されるものであるから、課題を積み残しておくのもそう悪いことでもない。
一年半ほど前、初夏の日差しが眩しい北大中央ローン脇での会合から始まった五・一六集会開催と報告集編集の営みも、ようやくここで一つの区切りをつけ、次の世代にバトンを渡すことができたように思う。
最後に、柏艪舎の山本哲平さんには大変お世話になった。編集委員会一同、心から感謝を申し上げる。
刊行にあたって 2014.03.15UP
世話人会共同代表 高岡健次郎
本書は、二○一○年五月十六日、北海道大学学術交流会館で開催された対話集会、「北大の自由・自治・反戦・平和の歴史を考える―イールズ闘争六○周年・六○年安保闘争五○周年の年に―」(略称「五・一六集会」)の全内容を広く世に問うことを第一の目的として刊行される運びとなった。
この集会を企画し呼びかけた「五・一六集会」世話人会は、「五○年イールズ世代」「六○年安保世代」「六九年紛争世代」などと互いに呼び合っていた、現在八十歳・七十歳・六十歳前後の学生運動のもと活動家たちと、北大教職員組合のもと役員たちという四つのグループを軸に、総勢四十名余りの人たちが結集した集団で、前年秋頃から組織的な活動をしてきた。
「五・一六集会」が目指す基本的な目標としては、何よりも先ず、北大一三○年の歴史の底流をなす教職員・学生の抵抗と闘いの歴史の掘りおこし、その検証と共有という大きな課題が掲げられていたが、それを可能としたのは、三世代の協力に立脚した世話人会の視野が持つ幅広い射程があったからであるし、同時にそのような世話人会だからこそ、この集いが、或る歴史的経験に特化した記念集会的なものにとどまることに、到底満足しえなかったからともいえるだろう。
また、この集会の賛同団体に北大教職員組合が加わり、集会の場では、諸報告の最後に神沼執行委員長が生々しい北大の現状報告を提起されたことは、集会の討論を、法人化後の大学が直面する諸課題に正面から向き合い、今日的意義をも併せ持つ内容に高めていく上で、極めて大きな力となったことを、是非書き記しておかねばならない。
もともと北大の自主的大衆運動は、札幌農学校時代の学風に淵源をもつともいえる、教職員・学生の密接な交流協力関係という流れの中で展開されてきたが、今回の集会の準備・開催に当たっても、世話人会を担っていたもと学生たちは、教職員組合と手を携えて活動できるという幸せな経験を、数十年の時を経て、またひとつ付け加えることができたのである。
本書の中身は、目次が示す通り、三部に分けられているが、その第一部「五・一六集会の記録と資料」には、既述のような集会内容(報告・討論等)の全体を基本に、その前後の活動経過の中で残された主要な文書類なども収録されている。
つづく第二部の「当事者の証言」は、「五○年イールズ世代」をはじめとするこの取組への参加者たちが、戦後北大の大衆運動の諸断面を、自分史の一部と重ね合わせつつ語り綴った貴重な証言・記録の集積であり、そのそれぞれが、これからも続く歴史の掘り起こし運動への、二つとない置き土産となるに違いない。
第三部「年表と文献・資料案内」では、紙幅の関係で、資料そのものの掲載は見送らざるをえなかったものの、従前には分散あるいは未知のものとして事実上眠っていた諸資料を含めて、今回、所蔵機関、所有者のご協力の下、相当数の関係諸資料をリストアップし、共同利用への道筋をつけたことは、今後の歴史への問いかけをあと押しする一助となろう。
「五・一六集会」当日には、会場の学術交流会館第一会議室を、二五○人ほどの参加者が、精一杯集めた補助椅子まで埋め、満員と知って引き返す方も出てしまうことになった。嬉しい誤算ではあったが、世話人会の不手際はお詫びしなければならない。十指に迫る報告とそれをめぐる討論、さらには終了後の懇親交流会に至るまでの、数時間にわたる熱気に満ちた対話と交歓の一部始終を、この報告集がどこまでお伝えすることができたかは心許ないが、本書を読まれた皆さんが率直なご感想ご批判等を寄せて下さり、この度の公刊が新たな対話と交流の広がりに資することができれば、これに過ぐる喜びはない。
目次
第一部 五・一六集会の記録と資料
第二部 五・一六集会の記録
Ⅰ 世話人会を代表して 高岡 健次郎
イールズ闘争―研究者の立場から 明神 勲
イールズ闘争と私――当事者の立場から 梁田 政方
イールズ闘争から大学の自治を問う 河相 一成
甦れ! 北大の抵抗精神 河野 民雄
六○年安保の思い出―クラス仲間とともに 大田原 高昭
北大における六○年安保闘争~その展開と特徴 森谷 尚行
「大学紛争」にかかわって 今野 平支郎
大学民主化闘争と「紛争」―「1968年論」を手がかりに 手島 繁一
国立大学法人北海道大学の本質~人を粗末にする「選択と集中の競争体」神沼 公三郎
Ⅱ 五・一六集会の資料
一 「集会からのアピール」
二 「趣意書」
三 「世話人会名簿」
四 「賛同団体・賛同者名簿」
五 「参加を呼びかけるビラ」
六 「報告と御礼」
Ⅲ 北大総長(理事)会見の経過と概要
第二部 時代と向き合って――当事者の証言
回想 北大キャンパス 一九四五― 一九五五 安井 勉
敗戦→労働組合づくりの中でディスカスが 栃内 信男
北大史をたどりながら思うこと 森 杲
イールズ闘争と民科のこと 高橋 進
イールズ闘争とその背景 渡邊 卓
イールズ闘争――その思い出と、今考えること 中野 徹三
イールズ闘争と私(人生の方向を決めてくれたあの日) 結城 千草
小窓からでも空は見える―「軍事アルバイト事件」が語るもの 中林 重祐
イールズ闘争から原爆展へ 和気 和民
付け加えておきたい幾つかのこと 濱口 武人
私にとっての「イールズ闘争」と「安保闘争」 桂川 良伸
“太田事件”―その再審と復職のための闘い 前田 満
終戦五年目(一九五○年)新制大学二期生の女子学生として 佐々木 梅子
北大女子寮設立記 川上 典子
文学部藤井教授事件について 大庭 幸生
北大職組青年部結成と六○年安保デモ暮らし 高橋 忠明
北大職組婦人部(現在女性部)の闘いの歴史 竹田 紀子
「北大女子学生の会」一九五八―六○年の思い出 伊藤 セツ
寮生活は縦糸、学業・アルバイト・女子学生の会等は横糸 岡部 清子
よりよき生活と平和のために――大学生協の活動 河村 征治
安保真っ只中世代として 大橋 晃
安保と女子学生の会と「どんぐり」―私を育てたもの 境 悠紀子
六○年安保の風に吹かれて 山本 俊子
雑誌『雄叫び』のことなど 小田代 政美
サークル・寮・自治会――安保直後から道学連再建にかけてのころ 國中 拓
一九六○年代の学生の平和運動 白樫 久
再建道学連の活動に関わって――六○年安保と七○年安保の狭間で 鈴木 徹郎
北大医学部における六○年安保闘争・インターン運動などの取り組み 中島 進
教育学部における「讒言・密告事件」と「全構成員自治」への民主的改革 神田 光啓
北大・七一年の明と七二年の暗 ~全国初の院生寮と農院生逮捕事件~ 佐々木 忠
「七二年北大事件」をふりかえって 山下 悟
〈特別寄稿〉一九五○年代前半期の早大学生運動の動向について 芹澤 寿良
〈特別寄稿〉イールズ闘争の今日的意義――イールズの大学管理法案と国立大学法人化 大藤 修
〈田辺先生ご遺稿〉 北大アルバイト事件 田辺 良則
第三部 年表と文献・資料案内
I 戦後北大学生・教職員運動史略年表(一九四五年~一九七○年) 手島 繁一
Ⅱ イールズ闘争詳細年表 河野 民雄
Ⅲ 文献・資料案内
あとがき
集会プログラム
開会あいさつ、司会者自己紹介 中野 徹三
世話人会を代表して 白樫 久
第一部
イールズ闘争とはなんであったか―研究者の立場から 明神 勲
イールズ闘争とわたし―当事者の立場から 梁田 政方
イールズ事件から大学の自治を問い直す―束北大学から 河相 一成
(小休憩)
甦れ!北大の抵抗精神 河野 民雄
自由討論
休憩
第二郡
司会者あいさつ 大橋 晃
鈴木 徹郎
村瀬 喜之
60年安保闘争の思い出―クラスの仲間とともに 太田原 高昭
北大における60年安保闘争―その展開と特徴 森谷 尚行
自由討論
(小休憩)
「大学紛争」にかかわって 今野平支郎
大学民主化闘争と「紛争」―「1968年」論を手がかりに 手島 繁一
法人移行後の北大の現状と教職員組合の運動 神沼 公三郎
自由討論
集会アピールの提案と採択 中野 徹三
手島 慶子
閉会のあいさつと事務連絡 手島 繁一
懇親会(18時~20時、北大中央食堂)
【報告者紹介】
高岡 健次郎(たかおか けんじろう) 一九四八年入学。北大大学院文学研究科修了。イールズ闘争時の道学連書記長。札幌学院大学名誉教授。
明神 勲(みょうじん いさお) 一九六〇年入学。北大大学院教育学研究科修了。北海道教育大学名誉教授。
梁田 政方(やなだ まさかた) 一九四六年入学。北大法経学部中退。イールズ闘争時の道学連委員長。元日本共産党中央委員。
河相一成(かわい かずしげ) 一九五七年東北大学経済学部卒業。東北大学名誉教授。東北大学イールズ闘争五〇周年記念事業元実行委員。
河野 民雄(かわの たみお) 一九五六年入学。北大文学部卒。元北大文学部自治会執行委員。元北海道立高校教諭。
太田原 高昭(おおたわら たかあき) 一九五九年入学。北大大学院農学研究科修了。北大名誉教授。
森谷 尚行(もりや なおゆき) 一九五九年入学。北大医学部卒。六〇年安保闘争時の教養部自治会委員長。元北海道民医連会長。
今野 平支郎(こんの へいしろう) 一九六一年北大入職。工学部、教育学部等の職員を歴任。元北大教職員組合書記長。勤労者山岳連盟道央連盟理事。
手島 繁一(てじま しげかず) 一九六六年入学。北大教育学部卒。大学「紛争」時の北大学連委員長。元全学連委員長。元法政大学大原社会問題研究所研究員。
神沼 公三郎(かぬま きんざぶろう) 一九六七年入学。北大大学院農学研究科修了。北大北方生物圏フィールド科学センター教授。北大教職員組合委員長。
【司会者紹介】
中野 徹三 (なかの てつぞう) 一九四八年入学。北大大学院文学研究科修了。札幌院大学名誉数授。
白樫 久(しらかし ひさし)一九六一年入学。北大大学院教育学研究科修了。北見工業大学・岐阜大学名誉教授。
大橋 晃(おおはし あきら)一九五九年入学。北大医学部卒。前北海道議会議員。勤医協中央病院名誉院長。
鈴木 徹郎(すずき てつろう)一九六三年入学。北大教育学部卒。元道学連委員長。元札幌地区労連議長。
村瀬 喜之(むらせ よしゆき)一九六三年入学。北大工学部卒。元北大教養部自治会委員長。元『赤旗』記者。
大学民主化闘争と「紛争」 手島繁一 2014.03.15UP
「1968年論」を手がかりに
だいぶ、プレッシャーをかけられましたが、どちらかと言うとプレッシャーには強い方なので、プレッシャーをものともせず私の意見を述べてみたいと思います。
この集会の名称を見ても分かる通り、イールズ闘争六十周年、六○年安保の五十周年が目玉商品であって、大学紛争について報告することはやや趣旨に外れるのではないかとの危慎から、私自身は相当に抵抗したのです。ところが、これまでの話を聞いてお分かりのように、六○年安保の世代の方も、イールズ世代の方も、その迫力たるやすさまじいもので、「わたしの目の黒いうちに聞かせてくれ」と迫るものですから、さすがに、そう断るに断れなくなって、こうしてしゃべらなくてはならないハメになってしまいました。
(1)「北大紛争」とはなんであったのか?
そんなことで、余り準備もしていないのですが、今野さんが北大の大学紛争について、具体的なことを話されたのですが、「紛争」という言葉を使うかどうかについても、世話人会でも相当な激論がありました。じゃあ、私自身どう考えているかということですが、様々な「紛争」論がありうるということを前提に、議論を活性化させるための置石として、わたしなりの「北大紛争」論を述べてみたいと思います。
わたしは、「北大紛争」、一般に「大学紛争」を大きく三つの位相(phaseフェイズ)で捉えています。
第一の位相とは、大学民主化闘争としての位相です。そして、この位相がことの本質であり、実はもっとも重要な位相であった、との理解にわたしは立っています。
第二の位相は、大学の自治をめぐる古典的かつ新しい脅威から、自治と自由を守るたたかいの位相です。古典的脅威とは、大学外の権力による大学自治圧殺の攻撃であり、新しい脅威とは、大学内に生じた一部暴力学生による文字通りの破壊行為であります。
第三の位相とは、この時代つまり六○年代末の「若者の叛乱」といわれる世界的な広がりをもったムーブメント(運動)としての位相です。
一般にいわゆる「紛争」として流布しているのは、もっぱら第二と第三の位相にのみ焦点を当て、しかもムーブメントの暴力的あるいは破壊的側面を強調するという、二重の偏向に陥っている、と言わざるを得ません。
さらに、そうした視点からは当然の如く、「あの時代」あるいは「紛争」の主役は全共闘だとする誤認が生ずるのも、論理的に必然でしょう。この点も加えれば、誤りは三重であるともいえます。ちなみに付言すれば、あの時代の若者たちを「全共闘世代」と表現し、括る用語法がこれまた一般に流通しているが、これも正確ではありません。小熊英二の論を引けば、「六五年の大学進学率は一七・○%、七○年は二三・七%で、この世代の約八割は大学に進学しておらず、全共闘運動とも無縁だった。また大学進学者全員が全共闘運動に参加したわけではない」。雑誌『世界』の東大生調査でも、東大全共闘への「参加」は、最高時点でも一六・九%であった。したがって、小熊は「同世代中多く見積っても四~五%しか『全共闘体験』がないなら、『全共闘世代』と言う呼称は当然不適切である。この呼称は、全共闘運動体験者が大卒のエリートで、後にマスコミ上で発言する機会を持てた人間が比較的多かったために、生まれた言葉だったと推測できる。」と述べているのです。
全共闘運動に親和性を感じている方には誠に申し訳ないのですが、わたしの全共闘運動に対する理解はこのようなものです。とはいえ、先に引いた雑誌『世界』の東大生調査では、全共闘への支持は参加も含めて約三一%から三八%という数字も無視することはできません。六○年安保闘争をピークに、社会は「政治の季節」から「経済の季節」へと舵を切り、労働組合ですら脱政治化が進展したこの時期に、学生たちだけがなぜ政治的意識を先鋭化させていったのかは、解かれるべき大きな問題ではあるのです。時間があればこの点についても述べたいと思いますが、どうでしょうか。
(2)基本底流にあった、大学民主化闘争の流れ
さて、話を戻しまして、わたしが「紛争」理解のうちで最も重要だとした大学民主化闘争の問題に触れたいと思います。現代の歴史学のなかで、戦前と戦後の「断続」と「連続」をどう見るのかは常にホットな論点であり続けているのですが、大学をめぐる問題についても同様なことがいえます。旧憲法体制から新憲法体制になって、大学の自治や学問の自由は法制度的な保証を憲法条文として勝ち取ったわけです。
わたしなど、戦後生まれで新憲法しか体験していない世代から見れば、そんなのは「あったり前だのクラッカー」となるのですが、本日の主役のイールズ闘争世代の方々からすると、大いなる感動と感激をもって戦後改革を受けとめたであろうことは想像に難くありません。私事の経験ですが、この三月に、占領期の学生運動や社会運動を研究するプロジェクトに招かれてお話をさせていただいたのですが、その席上、ある高名な歴史学者の方からこういう示唆を頂きました。「君ね! 大学の自治だとか学問の自由だとか言っているけれども、戦前は帝国大学と一部の旧制高校にしか通用しない概念であって、師範学校、高等専門学校はじめ大多数の高等教育機関は教育勅語が基本。つまり国家、天皇制国家に役立つ範囲でしかそういうものは認められんかった訳よ!」。この集会もそうですが、わたくしにとって、世代を超えて歴史を継承するとは、体験者の語りによって、次の世代の歴史的想像力を喚起することでもあるな、ということが実感させられる場面でした。
話が幾分それましたが、ともあれ戦後改革によって大学の自治と学問の自由の法制度的保証が実現しました。また、そのことは「国家のため」という自明の前提が消失したことを意味したのであり、大学あるいは学問や研究、教育が誰のために、何のためにあるのか、あるいは、あるべきなのかという問いと探索を、全ての大学構成員に課すものでもあったのです。とはいえ、問題は常に具体的なところから発生するもので、六○年代末の「大学紛争」は、民主的になったはずの大学内に残されていた信じ難い「格差」構造を告発するところから始まったのです。六八年あるいは大学紛争を象徴する二つの大学の闘争がそのことを明瞭に示しています。東大の場合は医学部に残る「徒弟制度」的慣行と前時代的なヒエラルヒ支配構造、他方、日大の場合は学生の自主的活動を一切認めない、これまた前時代的な大学の支配構造への反発が闘争の出発点でした。
運動の初発が、運動の性格や組織を決めることは良くあることで、日大闘争は学生自治会が大学当局の翼賛装置であったため、全共闘という組織形態を選択せざるを得ませんでした。東大の場合、日大とは比べものにならないほど学内の民主化は進んでいたのですが、例えば医学部の「徒弟制度」に見られるような各個人が被害を個別的に蒙るような問題に対しては、全員加盟制の自治会組織よりも機動的で個別的問題に即応できる組織が必要でした。つまり、全共闘です。「個別に立って共に討て」というロシア革命時のスローガンが愛用されたわけです
(3)認め合う関係の再構築から学生自治会の再建へ
先ほどわたしは全共闘に対する批判的立場を表明しましたが、他方全共闘運動に対する歴史的な理解をもつようにはなりました。先に述べた東大・日大の全共闘運動には、そういう選択肢しかありえなかったのです。また同時に、ギリギリの状態に追い込まれた若者が、その実存をかけて闘うとしたら、そこにはそれなりの心情があったことは理解できます。
ゼロ年代の論客の一人、北田暁大によれば、この時代の学生活動家に広く共有されていた「自己否定」という言説に触れて、この心情には、自己を絶えず否定的なものとして乗り越えていくことが実存の本質であるという実存主義的な観念と、自分たちが「革命」を志向しながら大学生という特権的な地位にいることを批判していこうとする誠実さが合流していた、と論じています。「自己否定」と「自己批判」は、言葉も心情もほぼ同一であり、確かに全共闘に批判的であったわたくしも含めて、多くの学生を虜にするマジックワードであったと思います。
しかし初発の誠実さも、否定、否定、否定を繰り返し、積み重ねて行くと最後は、逃げ場がなくなって、その究極の姿は何かいうと、ご存知の連合赤軍事件であったのです。連合赤軍事件は、七十年代における社会運動の一つの極北を示したものであったわけですが、その出発点は、六○年代末からの学生運動に旺胎していた、ということを確認しておく必要があると思います。私は六○年代末から、七十年代初頭の学生運動を経て、今の問題に繋げるとすれば、そういう否定し合う関係でない関係、お互いを認め合う関係を、どうつくって行くか、ということを考えなくてはいけないと思うのです。先ほど、文学部の学生の方が質問されましたが、学生自治会がないのでつくらねばならないという意見を、今回の集会への参加を訴えに恵辿寮に行った時に聞きました。今までの経験からいって、学生たちの自治会をつくろうという運動はもちろん学生当事者の問題ではあるのだけれども、大学と社会にも突きつけられた問題でもあるのです。
確かに、問題解決、昔風にいえば要求実現のためにはその問題の当事者、あるいは要求者、運動や闘争意思のある者たちが組織をつくり運動を展開することが必要です。しかしそれとともに、異質なもの、異文化が、お互いに認め合い、交流したり、時には激しくぶつかったりしながら、合意を形成していく「場」が絶対必要でしょう。言うところの「戦後民主主義」という名の下での同質化の強制ではなく、また「新自由主義」による個人化と競争への駆り立てでもない、連帯と友愛の組織として自治会を再構築することが求められているのでしょう。それは、「無縁社会」に立ち向かう公共空間をいかに構築するのかという現代社会に突きつけられた課題と通底する問題でもあると思われます。そういう意味で、文学部の森田君などの学生自治会をつくりたいという意思には、私自身の問題として、どういう風に支えるのか、ということを考えたいと、現在思っているところです。今野さんの期待には充分添えたかどうか、分かりませんが、時間ですので終わらせていただきます。
「北大の自由・自治・反戦・平和の歴史を考える」 手島 繁一 2014.03.20UP
着情
―イールズ闘争60周年・60年安保闘争50周年を迎えて―北大5.16集会世話人会事務局長 手島繁一
『労働運動研究』復刊26号、2010年8月号(PDF版)
予測を超える盛会となった集会
2010年5月16日、北大学術交流会館を会場に、「北大の自由・自治・反戦・平和の歴史を考える――イールズ闘争60周年・60年安保闘争50周年の年に」と題する集会(略称「北大5.16集会」)が開催された。集会を主催した世話人会は、便宜的に「50年のイールズ世代」「60年の安保世代」「60年代後半の大学民主化闘争世代」と名付けられ括られた三世代の北大の学生および教職員OB・OG、34人で構成され、賛同者は70人の個人と4団体であった。また、世話人会が集会の成功と『報告集』の発行のために募った寄付への協力者は210名に達した。
集会の主会場は150名の定員であったが、参加者は報道関係者を含めて250人を越え、主催者が事前に用意した配布資料も開会後1時間も経たないうちに無くなってしまった。すべてが、主催者の事前の予測を超える事態であった。
集会参加者の顔ぶれも多彩であった。もちろん、三世代の参加者が大多数を占めてはいたが、現役の学生や教職員の方々も参加し、積極的に議論に加わっていただいた。世話人会が学生寮で説明会を行ったり、あるいは大学構内でビラまきを敢行したり、またそれが格好の話題となってマスコミで報道されたりなども、集会の盛会につながる要因であったが、なにより昨今の大学と学生をめぐる困難な事態を打開しようとする意志的な参加であった、と見たい。
先に集会の趣旨とプログラム、および内容を紹介する。
集会の趣旨とプログラム
世話人会を代表して開会あいさつに立った高岡健次郎氏は、「北大130年の歴史の底流をなす教職員および学生の自由、自治、平和と民主主義を守る、抵抗と闘いの軌跡全体を視野に納めながら、本年がイールズ闘争60周年と60年安保闘争50周年という節目の年であることを踏まえて、二部構成の集会プログラムとした」と、集会の趣旨とプログラムの基本的視座を説明したが、実際の集会プログラムは以下のようであった。
第一部
世話人会を代表して 高岡健次郎
イールズ闘争とはなんであったか―研究者の立場から 明神 勲
イールズ闘争とわたし一当事者の立場から 梁田 政方
イールズ事件から大学の自治を問い直す-東北大から 河相 一成
甦れ!北大の抵抗精神 河野 民雄
自由討論
第一部
北大における60年安保闘争―その展開と特徴 森谷 尚行
60年安保闘争の思い出一クラスの仲間とともに 太田原高昭
自由討論
「大学紛争」にかかわって 今野平支郎
大学民主化闘争と「紛争」―「1968年」論を手がかりに 手島 繁一
法人移行後の北大の現状と教職員組合の運動 神沼公三郎
自由討論
なお、この報告では紙幅の都合上、集会で行われたすべての報告や議論に触れるわけにはいかない。イールズ闘争と60年安保闘争に限定して、報告と議論を紹介することになることをあらかじめお断りしておく。
イールズ闘争とはなんであったか-明神勲氏の報告に関わって
集会の企画を発案し最初に行動を起こしたのは、イールズ闘争に学生として参加し今は80歳前後の年齢に達した世代、「イールズ世代」の方々であった。北大におけるイールズ講演会の二日目、全学の抗議のなかで講演が中止された5月16日を集会の日取りに決定したのもこの世代の方々であった。したがって、イールズ闘争についてその事実と記録・記憶の掘り起こしと検証、継承と共有が集会の一方のメインテーマになったのは当然であった。とはいえ、もはや半世紀も前の闘争をメインテーマにすることの困難は確かにあった。筆者であるわたし自身が2歳の時の出来事である。集会で発言した現役の学生に言わせると、「自分たちの親の世代よりも、もっと上の世代の方の話で吃驚仰天(会場爆笑)」ということであるから、歴史の共有といい継承といっても、そう簡単なことではないということをあらためて考えさせられたのではある。
それはともかく、イールズ闘争に関する明神勲氏と梁田政方氏の報告は圧巻であった。
占領期レッドパージ研究の第一人者である明神勲・北海道教育大学名誉教授は、報告レジュメのほかに16頁に及ぶ資料を用意し、イールズ講演とそれに対する大学や学生の反応を詳細に明らかにした。それによれば、連合国軍総司令部(GHQ)民間情報教育局(CIE)高等教育顧問であったW.C.イールズはCIEの後援のもとに1949年夏から50年末にかけて、2名の同僚とともに、「共産主義教授の追放、スト学生の追放」を訴えて、全国30都道府県で30回、「約三千人の教授、二万人以上の学生を含む138の大学の代表者」が参加する講演会、懇談会を行った。いわゆる「反共十字軍全国行脚」である。これに対し、大学当局や教員の対応は、概ね消極的なもので「無事に終了させる」ことに腐心していたが、学生は当局の姿勢とは対照的に多くの大学で批判的行動を組織した。その一つの極点が5月2日の東北大、5月15,16日の北大のイールズ闘争であった。
明神氏によれば、なかでも北大におけるイールズ闘争は以下の点で特徴的であった、と指摘する。すなわち、(1)イールズの挑戦をかわすのではなく真正面から論戦を挑んだこと、(2)全国138の大学の責任者のなかで、イールズの面前で唯一、不同意を表明したのが、伊藤・北大学長であったこと、(3)伊藤学長のこうした行為を支えたものが、教職員組合、学生自治会、民科の三者を中心に組織された学内共闘の運動であったこと、である。また、東北大や北大における「イールズ反対」の声はその後の全学連の反レッドパージ闘争への展開に繋がり、大学における教員のレッドパージを基本的に許さなかった原動力になったという歴史的意義も確認された。
とはいえ、「残されたイールズ闘争」も存在している。その一つは、大学の歴史の認識と歴史に向き合う姿勢に関わる問題であって、例えば、闘争に関わって出された処分の理由や手続きの正当件を問い直す作業が残されていること、また、大学の公史にある明らかな誤りや闘争の位置づけに対する認識不足などが正されていないこと、また大学自身が自らの歴史を後生に語り継ぐべき役割を担っているにもかかわらず、歴史資料の収集や保存、公開などといった最低限の義務を十分に果たしていないこと、などの諸問題である。
もう一つは、イールズ闘争が課題とした大学の自治や学問の自由が、ことに国立大学の法人化に伴う環境変化によって、大きな困難と危機に直面していることの問題である。その意味で、イールズ闘争を60年後の今日、あらためて検証し、その闘いの記憶と記録を共有することは、決して過去の回顧にとどまらない今日的な意義をもっている、といえよう。明神氏は、「イールズ闘争は、学問の自由、大学の自治擁護の現在の課題と切り結ぶ、生きた歴史として語られることが、今求められている」と、それぞれの時代、世代を架橋する努力を呼びかけて、報告を締めくくった。
イールズ闘争とわたし-梁田政方氏の報告に関わって
梁田政方氏は、イールズ闘争当時の北海道学連委員長であって、闘争の責任をとらされる形で退学処分となった4人のうちのひとりである。2006年に『北大のイールズ闘争』(光陽出版社)を刊行され、その著作がきっかけで同世代はもとより、より若い世代とのつながりができ、5.16集会の淵源ともなったのである。ところが、集会の準備が始まった2月上旬に体調を崩して入院され、本人の懸命なリハビリと周囲の方々の支えもあって、ようやく体調を回復され集会に参加したという経緯があった。
梁田氏もまた、レジュメのほかに9頁もの資料を用意され、当事者の立場から、イールズ闘争の経験を語った。氏が特に強調したのは、第一に、「北大の民主的伝統を生かした誇るべき闘いが、逆に不祥『事件』になっている」ことの不当さを明らかにしたいということであった。第二に、北大の公の刊行物である『北大の125年』におけるいくつかの重大な記述の誤りを正したいということである。ことに、大学側が処分の理由とした学生側の行動についての記述、「(イールズ)講演の途中で学生が質問を求めて壇上に上がり講演が中止になった」との記述については、当事者ならではの具体的事実を指摘して反論を加え、こうした誤った歴史認識と記述を放置しておくことは大学自身の名誉を傷つけることになる、と強調した。したがって氏は第三に、2011年の北大開学135年に向け、これまでの公刊物の誤りをただし正確な「北大イールズ闘争」を書き記した北大の公史を編集・刊行すべきことを訴えた。梁田氏の、「今回の集会は、当時の事実を知る者にとっては、その誤りを乱す最後の機会になるだろう」との強い決意を吐露した報告は会場の共感を誘い、その提言は集会決議として結実することになった。
60年安保闘争に関わる2つの報告
集会のもう一方の主要テーマである60年安保闘争については、太田原高昭・北大名誉教授と森谷尚行氏から報告があった。
太田原氏は1959年入学のまさに安保世代で、「一般学生代表という形でお話ししたい」と、北大キャンパスにおける安保闘争のリアルな体験を中心に報告をまとめられた。例えば、教養部(1,2年生)の男子学生寮であった恵迪寮では闘争の最盛期は連日の集会とデモのため集会会場の大通公園まで寮役員がリヤカーで昼食を運んだこと、すべからく行動集会当日は沖縄で米軍普天間基地を包囲する「人間の鎖」行動が行われていたこともあり、報告や発言でも、半世紀前の列島を沸騰させていた安保闘争の意義を再確認しつつ、半世紀を経て沖縄の基地問題や核密約問題など、その危険な本質を露呈しつつある日米安保条約をめぐる議論や諸行動が再び必要になっていることが強調された。集会の決議はこうした議論と認識を反映したものとして、会場の熱い拍手で確認されたのである。
異なる時代・世代に架橋して歴史を語り継ぐということ
集会が主催者の予測を超えて大きな規模になったことの要因は、おそらく多様であろう。集会の趣意からして当然伺われることであるが、参加者の大多数は先に記した三世代の北大学生・教職員OB・OGであり、年齢階層で言えば、「80歳前後のイールズ世代」、「70歳前後の安保世代」、「60歳前後の大学闘争世代」の「連合同窓会」的な求心力が働いたことは確かである。それにしても、この世代間を架橋することだけでも、大変な努力を必要とする。それぞれがかけがえのない歴史を生きてきたわけであるから、時に語りが自己肥大的な傾向に陥りがちなことは当然のことでもある。世代間を架橋して歴史を語り継ぐことは、したがって、自己と自分たちの歴史や時代を相対化することからしか始まらないのかもしれない。それは、他者との語りを可能にする出発点でもあるし、またそのことによって自分の歴史や体験、あるいは語りの内容を豊かにすることでもある。歴史を他者とともに、掘り起こし、検証し、語り継ぐという努力は、同時に自らを豊かに再構成する、困難ではあるが楽しい作業である、とわたしは思う。
今回の集会がそうした楽しい作業になったのは、ひとえに集会準備の苦楽をともにした世話人や事務局の方々、そして集会にご協力いただいたすべての方々のおかげである。あらためて厚くお礼を申しあげたい。
[資料]「北大5.16集会からのアピール」(要旨)
1.イールズ闘争について
60年前の5月15,16日、当時占領軍総司令部民間情報教育局(CIE)の顧問であったイ-ルズ氏は、北大で共産幸義者の教授を追放するように迫った講演を行いました。これに対し教官有志は最初の日に質問と批判をおこないましたが、翌16日、学生の代表が当初から約束されていた質問を強く要求して抗議し、その結果講演が中止されました。
全国30の大学で行われたこの「イールズ講演」は、CIE当局とそれに盲従した文部当局が各大学に問答無用で押し付けたものであり、戦後ようやく日本が新憲法によって保障された思想・良心の自由と学問研究の自由、そして大学の自治とを頭から否定する暴挙でした。
イールズ闘争は、アメリカ独立宣言でも強調されている基本的人権と民主主義の根本であり、まさに大学の生命であるものを守るために立ち上がった闘いでした。そして北大を含む全国の学生のこのたたかいが、大学でこのレッド・パージを阻止した第一の力だったのです。
しかしながら、当時の北大当局が、占領軍当局とそれに盲従した文部当局のこの憲法違反の措置と、それに対応した大学自体の責任をまったく問うことなく、それに抗議した学生10名の処分によって事を済ませようとした責任は重大であり、しかもこの不当な措置が現在に至るまで反省されることなく継続しているという事実を、私たちは見逃すことはできません。
私たちは、現北大当局が、これらの経過を根源的に再検討され、不当処分によって長く多大の損害を受けつづけてきた学生の名誉を回復する措置を早急に取られることを、ここに強く要請します。一人の人権を守る事は、万人の人権を守ることです。当人たちはすでに高齢であり、漫然と時日の経過を待つ余裕はありません。
さらに私たちは、これまで極めてずさんであった学生運動などの貴重な資料の保存と管理、公開の基準などを早急に改善すること、今後刊行される大学の歴史書において、同窓生と協力して、この問題の記述の抜本的な書き直しを行うことを、合わせ強く要請する次第です。
2.1960年の日米安保条約改定反対の闘いと、その後の50年―沖縄普天間基地撤去の闘いに呼応して
50年前の1960年5月、安保条約改定に反対する声は、国民的大運動となっていました。北大においても、学生たちはクラス、学部、学寮などで、教職員は職場を基礎に議論を交わし、全国的にも高く評価された「安保改定阻止・大学自治擁護全北大共闘会議」に結集して、全国の闘いに先進的に呼応していました。
新安保条約は、「日本国の安全」のためといいながら、他方「極東における国際の平和および安全の維持」という名目でアメリカの軍事戦略のために日本全土に米軍の駐留を継続し、自衛隊を強化することを目的としていました。
この50年間、米軍はベトナム戦争、アフガニスタン、イラク戦争等の戦場に、沖縄をはじめとする日本の基地から自由に出撃していきました。そして日本政府は、表には「非核三原則」を云いながら、米軍の日本基地での核兵器の貯蔵や持ち込みを認める「密約」さえ結んでいたのです。 60年の安保闘争は、条約改定を阻止することは出来ませんでしたが、日本の民主主義を成長させ、安保条約のはらむ危険を押さえるうえで、大きな役割を果たしました。平和憲法の改悪や自衛隊の海外派遣がこれまでの日米支配層の思うように進んでいないことは、この国民の大運動の成果です。そしてわが北大でも、1963年の工学部での現職自衛官の入学に反対する運動が、64年以降の入学を認めないという成果を上げたのも、この力の現れといえます。
しかしこの間、安保条約は条約の枠をはるかに越えてアメリカのグローバルな世界支配のために利用され、米軍の基地面積はドイツに次いで世界第二位、支払った費用負担の累積はドイツの100倍を越えるといわれますが、とりわけ沖縄の皆さんは、基地のさまざまな負担と危険をもっとも重く長く負わされてきました。
そして現在、安保体制と国民の矛盾を端的に示すのが、普天間基地の移転問題です。鳩山首相は昨年、2006年の日米合意にあったその代替基地を辺野古に建設するという計画の見直しと、「最低でも県外」という方針を言明しましたが、アメリカ側の強硬な反対で腰砕けになり、今は辺野古案の手直しに戻って地元との板挟みでよろめいているように見えます。
しかし、普天間基地がある宜野湾市の伊波洋一市長は、去る4月23日に東京で開かれたアジア・ジャーナリスト会議で講演し、次のように述べています。すなわち、日米が2006年に合意した「再編実施のための日米のロードマップ」では、在沖縄の海兵隊1万2000名の大部分を占める要員8.000名が、2014年までにグァムに移転することになっており、その主力は普天間のヘリコプター部隊を含む第3機動展開部隊であること、その結果沖縄に残る海兵隊は4000名程度に縮小されること、したがってワシントンのシンクタンクも、「我々の見解は、米国は普天間飛行場やその代替施設がなくともやっていける」と記していること。そして伊波市長は、普天間基地は、その代替施設を建設することなく、廃止できる、と強調しています。それに反対しているのは、世界に700もの基地をもちながら、自分の縄張りを守ることに憂き身をやつしている軍部の勢力と、それに利害を持つ連中です。
私たちは、鳩山政権が、普天間基地の早急かつ無条件の返還を、オバマ政府に堂々と要求し、交渉することを求めます。
また私たちは、日米軍事同盟の必要とか、抑止力というあいまいなこれまでの通念を一度根本から考え直し、軍事同盟に依存することなく、アジア諸国民の友好と安全、新しい共同性の創造にもとづく国際関係の構築に、日木の政府が先頭に立つことを、強く要望するものです。
3.大学の自治の危機と「国立大学法人」化の現状について、北大の学生と教職員の皆さんおよび全国の大学人の皆さんに訴える
私たちは、1960年の北大での壮大な安保闘争を支えたものが、ほぼ全学部に組織された学生自治会と大学院学生会、そして教職員組合をから成る全学の緊密な共同闘争であった事実を、あらためて確認しました。
しかし、50年後の現在、学生自治会はほとんど全学部で消滅しました。学生のしっかりした自治組織がない大学に、大学の生きた自治は存在しません。もともと大学という名称自体、中世ヨーロッパの学生組合(UNIVERSITAS)を起源とするものだったのです。
今こそ現代にふさわしい学生の自治組織よ起これ! と、私たちは、大きな期待をこめて、北大生の皆さんに、全国の学生の皆さんに呼びかけます。
また、大学の教職員の労働条件と教育・研究条件を守る教職員組合の存在とその力量の発展は、大学の民主主義を支える大事な柱です。私たちは、北大と全国各大学の教職員組合の皆さんのたたかいに、心からの熱いエールを送ります。
しかし、2004年に「国立大学法人」に移行させられた国立大学では、大学の自治と民主主義とは、大きな危険に直面している、と感ぜざるをえません。
文科省より配分される予算は、毎年度1%ずつ削減され、そのため研究者は外部資金の獲得競争に追われ、教育研究上の格差、基礎研究と基礎教育の軽視はひどくなる一方です。また正規職員が減らされ、非正規職員が増え、いま北大で働く労働者の4人に一人は、非正規職員になっています。
さらに北大では、法人移行した直後、30余年続いてきた助手の学長選挙権が剥奪されました。
国立大学法人法のもとで学長の専決体制が著しく強化され、それに少数の役員会に強大な権限が集中し、こうして以前の「教授会の自治」も部局の自治も消滅した、といわれる有様です。
それ以上に私たちを驚かせたことは、おそらくすべての国立大学の事務局長が文科省からの「出向者」だと思われること、そして86法人のうちのおよそ70大学では、事務局長が理事に就いていることです。国立大学は、以前にも増して国と官僚に支配されるようになった、というべきです。
私たちは、等しく危機感を抱いている全国の大学人の皆さんに、この法人化体制を国民とともに抜本的に点検・批判し、構成員の主体的な参加と自治に支えられるところの、真に21世紀を担うにふさわしい大学に発展させるよう、大学での創造的な運動の展開と連帯とを、強く呼びかけるものです。
編集人:飯島信吾
ブログ:ある編集者のブログ
UP 2014年03月15日
更新 2014年03月20日
更新 2014年10月07日
更新 2015年09月20日
更新 2016年02月20日
更新 2016年02月22日
更新 2023年12月27日