社会的経済・社会的企業・協同組合研究の推進のために
○○○○○○○○○○○○○○○中川雄一郎
『いのちとくらし研究所報』(非営利・協同総合研究所いのちとくらし)―2
◆以下、ご自分のPCを「125%」に拡大して、読むことをお勧めします。
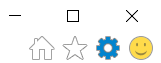 ←サイト右上部の「青印」をチェックして!
←サイト右上部の「青印」をチェックして!●2012年02月29日から2014年05月31日
●理事長のページ(No.46)●2014年05月31日 14.06.08更新
コメントノート 中川 雄一郎
はじめに
最近年、世界の協同組合人(co-operators)と協同組合研究者の多くが一斉に取り組んだイベントに「国際協同組合年」(IYC)がある。IYCは、周知のように、2009年の国連総会で「2012年をIYCとする」ことが決議されたことによるのであるが、その決議の背景には、国連が世紀の転換期に世界の国と人びとに呼びかけた、貧困撲滅のための「ミレニアム開発目標」(MDGs)に世界の協同組合組織が取り組んできた事実があった。国連が承認しているように、「貧困撲滅」といった人類的な問題や課題に――非営利組織(NPO)であり非政府組織(NGO)でもある――世界の協同組合が真剣に取り組んできたのには、国際協同組合同盟(ICA)をはじめとする世界の協同組合組織や協同組合人にそうすることの意味や意義を指摘した――ICA大会に提案・採択された――文書があったからである。A.F.レイドローの『西暦2000年における協同組合』(Co-operatives in the Year 2000)、言うところの「レイドロー報告」である。レイドロー報告は、1980年10月――この同じ年の1月に旧ソ連はアフガニスタンへの侵略を開始した――にモスクワで開催された第27回ICA大会に提出され、採択されたのであるが、それ以後30年以上にわたって協同組合人や協同組合組織に影響を与えてきた。そのことは、1992年10月に――ICAの歴史上初めてヨーロッパ以外の東京で開催された第30回ICA大会(「ベーク報告」)と、1995年にマンチェスターで開催されたICA100周年記念大会(「協同組合のアイデンティティに関するICA声明」)を振り返ってみればよく分かる。
これら2つの大会報告の内容は、まさにICAモスクワ大会の提案者であるレイドローがより多くの協同組合人と協同組合組織に明確に理解され、かつ承認してもらいたかった「報告の本旨」をかなりの程度認識したものであった。とりわけ後者のICA大会でリーダーシップを発揮した――レイドローと同じカナダの協同組合研究者である――イアン・マクファーソン(ヴィクトリア大学教授)はレイドロー報告の本旨を十分に理解し認識していた。
そのマクファーソンも主張しているように、レイドロー報告の最も重要な部分は、第V章「未来(将来)の選択」で提示された「4つの優先分野」(「世界の飢えを満たす協同組合」・「生産的労働のための協同組合」・「持続可能な社会のための協同組合」・「協同組合コミュニティの建設」)である。というのは、この「4つの優先分野」は、これまでの協同組合の事業と運動の枠や規範を超え出た協同組合の機能と社会的役割を思慮する「方法論」を明確にしていたからである。これら4つのリストは、まさに「協同組合事業の直接的なニーズ」から協同組合人の思考と志向を引き離して、もっと幅広く社会的、人類的に重要な目的や目標に彼・彼女らをして注視させるよう促すリストに外ならなかったのである。要するに、レイドロー報告の本旨の第1は、現代世界における協同組合の事業と運動のより重要な目的・目標が何であるかを協同組合人に理解させ、認識させるべく導こうとしたことである。本旨の第2は、本旨の第1を協同組合の事業と運動に着実に埋め込んで実質化させていくのに必要な経済-社会的な能力を創り出していくことである。具体的には、政府・公的機関によって構成される「公的セクター」(第1セクター)と多国籍企業や資本主義的大企業の「営利セクター」(第2セクター)との「二大権力」に対抗し得る拮抗力(countervailing power)となる「民衆の力」を支える「第三の力」たる「非営利セクター」(第3セクター)の支点あるいは作用点としての協同組合セクターの育成を遂行することである。レイドローは既に1974年の時点でこのような「協同組合セクター」論を提起し、それに基づいて協同組合セクターをコアとする第3セクターが「世界が抱えている重大な未解決の経済問題」の解決を図るための「4つの方法」を提言していた。「4つの方法」とは、(1)地球の諸資源を分け合う方法、(2)だれが何を所有すべきかという方法、(3)土地の果実(食料)と工業製品を分け合う方法、(4)各人が必要な部分を公正に取得できるシステムを整える方法、である。
こうして見てくると、レイドロー報告の本旨は、世界的な視野を以て現代協同組合の事業と運動を「特定の事業と運動から社会的に普遍的な事業と運動へ」と広げていくよう協同組合人を動員させることであった、と言ってよいだろう。レイドロー報告のそのような実践的指針は「未来(将来)の選択」として決して間違っていない、と私は考えている。協同組合の事業と運動が「特定なものから普遍的なものへ」と進化していくプロセスは、世界的、地球的な、したがって、人類的な課題や問題に取り組むことと、協同組合の事業と運動が拠って立つ地域コミュニティやより広いコミュニティの課題や問題に取り組むことの相補性を求めるからである。言葉を換えて言えば、「自治、権利、責任、参加」をコアとするシチズンシップが、人間的な価値や尊厳、自然的、環境的な価値、それに経済-社会的な価値を――「協力・協同する人間の本来的関係」に基礎を置く「協同の倫理」を育成していくことにより――相互に補完し合うよう確かなものにしていくのである。こうして、協同組合人は、協同組合の事業と運動を通じて、ますます開放的になり、閉鎖的で排他的な性格のあらゆる制度や権力・勢力と対立し、それらを克服しようと努力するのである。
2つの協同組合研究会
さて、前置きが長くなってしまったが、私は、IYCを挟んで、協同組合の事業と運動の未来を見据えた「協同組合の新たな指針」たるべきものの再想像・再創造を視野に入れた、極めて意欲的な2つの協同組合研究会に関わってきた。1つは全労済協会が主催する「協同組合新理論研究会」とそれを引き継いだ「協同組合 未来への選択研究会」であり、もう1つはJC総研主催の「新協同組合ビジョン研究会」である。‹全労済協会主催の研究会›
前者は、3月11日午後2時46分に生起したマグニチュード9.0の巨大地震と大津波、そしてそれによる福島第1原発事故が人間と自然と経済と社会を町や村やコミュニティごと吞み込んでしまった「東日本大震災」が起こるおよそ20分前に明治大学研究棟の会議室において研究会の主旨や大まかな研究計画などの打ち合わせを済ませた「研究会」である。じつは、研究会の予定された開始が危ぶまれたのであるが、むしろそのような状況であるが故に、予定通りの3月29日に全労済協会にて第1回研究会が開催され、第2回は約3週間後の4月22日に行なわれている。とはいえ、この研究会が本格的に始動するのは5月30日の第3回研究会からである。そしてこの研究会の成果が翌2012年5月に『協同組合を学ぶ』と題する書物として日本経済評論社より上梓された。それは、まる1年の時間を費やして作りあげられた作品である。この研究会は、「間、髪を入れず」にメンバーも同じ(第2次の)「協同組合 未来への選択研究会」に引き継がれた。「未来への選択研究会」では、「生協」を前面に出しながらも、協同組合の「普遍的特徴」をベースに協同組合の事業と運動の未来志向型が模索された。言うまでもないことだが、「未来志向」にはしっかりした現状分析が必要である。その意味で、この研究会は「地に足を置いた未来への選択」を追究してきたのである。本年5月末に当研究会の成果が『協同組合 未来への選択』を――同じく、日本経済評論社より――上梓された。全労済協会としては2011年5月から2014年5月までの3年間で『協同組合を学ぶ』と『協同組合 未来への選択』を上梓したことから、協同組合研究セミナーを開催することを考えているようである。
‹JC総研主催の研究会›
私は後者の研究会とは――「前史」、すなわち、JC総合研究所の前身である「協同組合経営研究所」時代の研究会を含めると――かなり長いお付き合いの間柄であるが、ここではそのことに触れずに、2010年9月に設置されたJC総研の研究誌『にじ』の編集責任(座長)を仰せつかってから現在までおよそ4年を数えることになる。また経営研究所からJC総研に名称を変更してからは――私の大学院ゼミをベースに――主に明治大学(駿河台)で公開研究会を開催するようになり、公開研究会での報告者が『にじ』にその内容を論文として提出する、という極めて合理的な方法が採られるようになった。JC総研はまた、協同組合研究史を含めた9つの研究テーマを決定し、各テーマに基づいて『にじ』編集委員により構成される「新協同組合ビジョン研究会」を立ち上げ、協同組合の「新ビジョン」と「協同組合研究史」を論究する作業を実施してきた。詳細は割愛するが、このおよそ4年に及ぶ新協同組合ビジョン研究会は、本年5月に2種類の研究成果を家の光協会より上梓した。1つは『協同組合は「未来の創造者」になれるか』であり、もう1つは『協同組合研究の成果と課題』である。特に後者は、日本協同組合学会初代会長の(故)伊東勇夫先生が中心となって仕上げられた『協同組合事典』(家の光協会、1980年)以後世に出ていないのであるから、その意味でも重要な研究成果であると言うべきだろう。
新協同組合ビジョン研究報告
2014年5月16日に明治大学の最新の校舎、グローバル・フロント(大学院専用棟)1階のグローバルホールにおいて新協同組合ビジョン研究に関わる講演と生協と農協の実践報告、およびそれらの講演と実践報告に対するパネルディスカションが行われた。講演者は、私の他に田中夏子さんと大高研道さんの3名である(3名とも「いのちとくらし」の会員)。田中さんは協同組合における参加の課題を、大高さんは協同組合における教育活動の課題を論じた。田中さんと大高さんの講演は、研究の跡がよく分かるじつに有意味な内容である。さて、私の講演であるが、「協同組合は『未来の歴史』を書くことができるか:協同組合運動の新地平をめざして」がその演題であり、演題からして何やら取っ付き難いと思われていたようである。その証拠に、私のレジュメはわずか2ページの、しかも内容にまったく触れない「小タイトル」を羅列しただけのものである。それに対して、田中さんはパワーポイントを駆使し、課題や問題点に説明を加え、論理の流れが分かるようになっており、大高さんも課題や問題とそれへの対応の骨子を聴く人に分かるよう丁寧に認(したた)めてあった。
私のレジュメは次のものである。
そこで私は、このようなレジュメに従って、私が用意しておいた「コメントノート」に沿って大方のところは話を進めることができたので、ここにそのコメントノートを記しておくことにする(しかし、持ち時間の都合で一部分触れることができなかったことを断っておく)。はじめに
- *いま、なぜ、新協同組合ビジョンなのか
- *協同組合の内と外・・・・・・協同組合運動の「弾みの概念」
1.レイドロー報告の本旨は何か
- *いま、なぜ、レイドロー報告なのか
- *「われわれ」と「『われ』と『われ』」
2.協同組合のエートス
- *「はじめに行為ありき」(ゲーテ)
- *協同組合のイデオロギー
- 協同の倫理・・・・・・人間の本来的な関係の構築
- 参加の倫理・・・・・・「承認の必要性」(ヘーゲル)
3.協同組合と「4つの優先分野」
- *世界をどう見るか
- 4つの未解決の経済問題の解決を図る方法
- (1)地球の諸資源を分け合う方法
- (2)だれが何を所有するべきかという方法
- (3)土地の果実(食料)と工業製品を分け合う方法
- (4)各人が必要な部分を公正に取得できるシステムを整える方法 *協同組合セクター論と「4つの優先分野」
- 4つの優先分野
- (1)第1優先分野:世界の飢えを満たす協同組合
- (2)第2優先分野:生産的労働にための協同組合
- (3)第3優先分野:持続可能な社会のための協同組合
- (4)第4優先分野:協同組合コミュニティの建設
4.コミュニケーション・コミュニティとしての協同組合
- *2つのコミュニティ
[地域コミュニティ]と[人間関係のコミュニティ]
- *コミュニケーションと協同組合
5.むすびにかえて
*レイドロー報告を「超える」ための「われわれ」の闘い
1.いま、なぜ、「協同組合の新ビジョン」を追究するのか
2012年は国連が決定した「国際協同組合年」であった。おそらく、各国の協同組合人は自国の協同組合の発展の重要なステップとして「国際協同組合年」を位置づけ、それに応じた試みを行なったことであろう。周知のように、日本にあっても、「現代日本の協同組合の経済-社会的機能と役割」を多くの人たちに正しく理解し認識してもらうことを目的に、「協同組合憲章検討委員会」を設置し、「協同組合憲章草案」の作成がなされ、以て政府に協同組合憲章の制定を働きかける、という努力がなされた。この「協同組合憲章草案」作成の全般的な努力のプロセスは、現在、「国際協同組合年記念全国協議会」に引き継がれている。ところで、私は、後者の全国協議会の努力のプロセスは、前者の憲章検討委員会のそれよりももっと幅広く「協同組合の内と外」を視野に入れる必要があると考えている。というのは、全国協議会の具体的な仕事(Duty)は、「レイドロー報告を乗り越える」、つまり、レイドロー報告をaufhebenする――レイドロー報告の本旨を現代に見合った、より高い段階で活かしていく――ことだと私は考えているからである。
レイドロー報告については、A.F.レイドロー自身をよく知る(故)イアン・マクファーソン教授の指摘が参考になる。彼は「レイドロー報告の特徴」をこう指摘している。
- (1)「協同組合の本質」について、ヨーロッパ中心の解釈を含めて北大西洋地域に共通する視点や考えを超越する、という課題に取り組んだ初めての文書である。
(2)協同組合の事業と運動に参加する市民の能力が協同組合の事業と運動を活発にすることを強調している。
(3)人びとに「普遍的利益」をもたらすのは、地域コミュニティのエンパワーメントであり、地域コミュニティの人びとによる能動的で創造的な活動である、とのことを明示している。
(4)その時代、その時期における主要な経済的、社会的および政治的な変化のなかに協同組合の事業と運動を位置づけている。換言すれば、協同組合の外部に関わる文脈が協同組合の「未来の発展」にとって重要であることを強調している。例えば、急激なインフレに起因する困難な経済状況、政府や企業における旧来型組織・機構への不信の増大、政治的信念の変容と政治的不安定、自然資源の危機の拡大、テクノロジー革新の影響、ますます強力になる大企業の力、そして発展途上国における急速な都市化などである。
(5)協同組合の事業と運動の創造的活力を再強化すること、新しい思想と行動の必要性、協同組合に「蓄積されている努力」と「新たな努力」のコラボレーション(協働)の促進に関心を払う。
(6)協同組合人は次のことに努力しなければならないことを示唆した。- (a)協同組合企業(事業体)の「本質」を再考する。
- (b)協同組合原則を再検討する。
- (c)協同組合組織の規模拡大と多様性を受け入れる。
- (d)協同組合における民主的管理の意識を育成し、高める。
- (e)協同組合が他の企業(営利企業)と明確に区別される「協同組合の社会的目的」に責任を負う。
- (f)協同組合と国家の関係の複雑さと不可避性とを認識する。
2.これらの「特徴」から現代の‹われわれ›は何を学びとるべきか
これについて、私は、いわゆる「ヘーゲル哲学における3つの基本テーゼ」、すなわち、「精神は‹われわれ›であり、‹歴史›であり、そして‹歴史のなかで自己を知る›」に基づいて説明してみよう(以下、これについては、城塚登『ヘーゲル』講談社学術文庫、1997年を引用、参照している)。しかし、ここでは、簡潔に、「われわれ」とは特定の集団(例えば、協同組合)を通じた生活によって創られる「共同性」=「協同性」を意味し、しかもこの「共同性」=「協同性」は多くの自立した「われ」が存在する「われわれ」によって成り立つ「共同性」=「協同性」であり、「『われわれ』である『われ』と、『われ』である『われわれ』」とによって為(な)される「『共同』(=『協同』)と『個の自立』との統一」であることを意味する。そこで次であるが、「『共同』(=『協同』)と『個の自立』とが統一されている」ことを確信するのは、「他者を介してである」ことが理解され、かくして、「自己意識」は「その充足を他者の自己意識においてはじめて達成される」ということになる。換言すれば、「自己意識」、すなわち――「他者を意識する意識」ではなく――「自己を意識する意識」、「自分は自分一人で生きているのではなく、他者との関係のなかで生きていることを意識する意識」が生み出される。こうしてヘーゲルは「自己意識は承認されたものとしてのみ存在する」と強調する。かくして、自己意識は「精神の概念が実現される場」となり、したがって、自立した個々人は「社会で生きる自覚」を明確に意識するのである。ヘーゲルの言う「承認」、すなわち、「承認の必要性」こそ「すべての人間の尊厳を承認する闘い」でもあるのだ。
ヘーゲルはさらに、「承認の構造」を明らかにして、こう論じる。「自己意識は自己自身を他者のなかに見いだす」ことによって、‹われわれ›は「自分‹われ›が他者と人間関係を結ぶなかでこそ、自分‹われ›に対する期待、自分‹われ›の果たすべき役割、自分‹われ›のなし得ることについて意識する」のであり、したがって、‹われわれ›は「人びとがお互いに承認し合っている」ことを「承認する」のである、と。
こうして自己意識は「‹われわれ›である‹われ›」を基盤とすることによって形成されるのであるが、そのために自立した個人一人ひとりが他の諸個人を自由な「自己意識」として相互に承認し合うことで「協同」(=共同)を実現するよう求めるのである。実際のところ、そうすることは‹われわれ›にとって「極めて困難な営為である」が、にもかかわらず、「人類は長期にわたる歴史を通じて、そのための諸契機を準備してきたのである」。「そうした歴史的営為のなかにこそ精神が存在するのである」。要するに、精神は「人間の歴史的営為のなかに、たとえ自覚されなくとも、自らを現わしている」のである(第2のテーゼ「精神は歴史である」)。
「意識、自己意識、理性を経て精神に達する」とされる第3のテーゼの「歴史のなかで自己を知る」の「歴史」は、世界史的には「古代ギリシア、古代ローマ、中世、啓蒙時代、フランス革命――そして‹われわれ›が生活している現代を加えて(中川)――」である。この歴史のなかで人間は「精神の存在」を自覚する、ということである。要するに、自己意識は「人間は共同性=協同性なしに、すなわち、社会から離れて生きることはできない」ことを教えているのであって、したがって、人間は、自らの生きる対象の総体が世界であることを認識するのであるから、世界史のなかで自らを理性的存在として自覚しようと努力し、自分を知ろうとするのである。まさに人間はそうすることで、意識せずとも、自らを普遍的な存在にしていくのである。これこそが、個々人が自分自身を社会の構成員として自覚していくプロセスなのである。このプロセスこそ、自立した個人一人ひとりが「個人的行為の社会的文脈」を確認するプロセスであり、また「自立した個人」と「社会の普遍性」との「共存」である、と「われわれ」はみなすのである。
このような「3つの基本テーゼ」を簡潔に見てきたのであるが、最後に次のことを付け加えなければならない。それは、「自己意識は行動しなければならない」、このことを理解することである。なぜなら、現実の、実際の行動が「精神」を生み出すからである。ゲーテが言うように、「はじめに行為ありき」なのであって、「はじめに言葉ありき」ではないのである。「‹われ›に対する期待、‹われ›の果たすべき役割、‹われ›のなし得すること」といった意識は、‹われわれ›がお互いに「‹われわれ›である‹われ›」を「自由な自己意識」として「承認し合っている」ことを「承認する」からである。
3.協同組合の「未来の選択」は「普遍的」でなければならない
協同組合の事業と運動の具体的な内容とヘーゲル哲学の抽象的な内容は、じつは、「協同組合のイデオロギー」、「協同組合のアイデンティティ」、あるいは「協同の倫理」と「参加の倫理」――「シチズンシップ」と言ってもよい――を協同組合の事業と運動に明確に位置づけるためのアプローチである。そしてこのアプローチに導かれて、協同組合人はレイドロー報告の「未来を見据える」鳥瞰図を描けるように行為し、活動し、思考しなければならない。そうすることによって、現代の協同組合人はレイドロー報告を乗り越えることができるのである。なぜなら、レイドロー報告が真に願っていたこと、協同組合人による「個人的行為の社会的文脈」が「協同組合の事業と運動の普遍性」の何であるのかを明らかにすること、このことを現代の協同組合人は「自己意識」として世界に向けて発信し、行為し、行動に移すことになるからである。協同組合人は「世界をどう見るか」、「協同組合の未来をどう俯瞰するのか」、すなわち、「協同組合に対する期待」・「協同組合の果たすべき役割」・「協同組合のなし得ることは何か」を世界に向かって明らかにしなければならないのである。4.コミュニケーション・コミュニティとしての協同組合は「未来の歴史」を書くことができるか
レイドロー報告の最も重要な部分は、第Ⅴ章「未来(将来)の選択」である。すなわち、協同組合の事業と運動が世界の人びとのために「果たすべき役割」、「実際になし得ること」、それに「彼らの期待に応えること」を実現していく実践的指針を創り出すことである。これは、「4つの未解決の経済問題」の解決のためのアプローチを踏まえた「4つの優先分野」での取り組みを事業と運動のなかで実質化させていくことを意味する。具体的には、(1)良質な食料の確保、(2)より良い雇用の促進、(3)持続可能な社会のために来たるべき諸問題に取り組む、そして(4)より良い地域コミュニティの建設、である。そこで、私としては、これら4つの優先分野での取り組み、すなわち、「普遍的で社会的な目的」の達成をめざす協同組合の事業と運動のアプローチは、私が提起した「3つのアプローチ」の関門を越え出ることができるのだろうか、と問うことになる。私が提起した3つのアプローチとは、(1)「制度のアプローチ」、(2)「成果(結果)のアプローチ」、(3)「過程のアプローチ」である。これら3つのアプローチはそれぞれ協同組合の事業と運動の「機能」・「目的(・目標)の到達点」・「協同の倫理と参加の倫理に基づく社会的潜在能力」を検証するのであるから、協同組合の事業と運動がこれらのアプローチに耐えられるのであれば、協同組合は――したがって、協同組合人は――「未来の歴史」を書くことができるし、それ故にまた、「未来の創造者」としてその名を付すことができるであろう。 このような「普遍的で社会的な目的」を有する協同組合は、「コミュニケーション・コミュニティとしての協同組合」であることを自ら立証し、「自立した個人と社会的普遍性との共存」を体現している、と言われるであろう。なぜなら、コミュニケーション・コミュニティとしての協同組合は「国民的に特有な形態の市民社会から国境を越えた言説に至るまで、社会のすべてのレベルで存在することが可能」であり、また「それが原則として合意によってのみ解決可能な真理への積極的参画を特徴とするからである」(山之内靖・伊藤茂訳『コミュニティ:グローバル化と社会理論の変容』NTT出版、2006年)。
●理事長のページ(No.43)●2013年08月31日
はじめに行為ありき 中川 雄一郎
今年の4月中葉に、大阪府保険医協会が発行している月刊誌『大阪保険医雑誌』の編集部から、「医院経営と協同組合」と題する特集を6月号(No.561)で組むので、協同組合の歴史や―昨年世界的な規模で挙行された―国際協同組合年(IYC)のことなどに触れながら、分かり易く「協同組合はいかなる事業体であるか」について書いてほしい、との依頼があった。大阪保険医協同組合は「中小企業等協同組合法」に基づいて1971年4月(正式認可は翌72年1月)に設立された事業協同組合である(設立時の組合員数は307 名、出資金500 万円。現在の出資金13億3、460 万円、事業高22億1、400 万円。なお詳しくは、保険医協会事務局参与の原文夫氏が同号に寄稿された「会員の経営と生活を支えるため:保険医協会と協力共同して40 余年」を参照してください)。
私は、事業協同組合の関係者、特に事務局の方々から「事業協同組合の組合員はどうも組合員意識が薄く、したがって、協同組合の成長や発展について思い巡らすことが少ないかもしれない」との声を耳にした時には、組合員と事務局員との間で意思疎通が充分に図れるシステムを構築しておくことの必要性を指摘するのであるが、それがどうもそう容易なことではないようである。しかし、容易なことではないかもしれないが、協同組合の事業の成長や運動の発展に何よりも必要なことは、協同組合のすべてのステークホルダー(利害関係者)が相互に意思疎通を図るよう努力することなのであるから、そのためのシステムの構築もまた不可欠なのである。私は、そのようなことも頭の片隅に置いて依頼原稿のタイトルを「協同組合とシチズンシップ:シチズンシップを育む事業体として」とした。私はしばしば言うのであるが、シチズンシップのコアである「自治・権利・責任・参加」は相互に補い合う特徴的性格を擁しているのであって―分かり易く言えば―例えば「個人による権利の行使が責任の履行となる」ということである。意思疎通のシステムは必ずや、「上意下達の承認受諾関係」を否定し、「参加の倫理」を自己意識化して組合員にも事務局員にも協力し協同することの意味をより明確にしてくれるのである。
このようなことを考えながら、私は、ロッチデール公正先駆者組合について、先ずその運動の思想的背景を説明し、次に「先駆者組合パラドクス」を取り上げて「近代協同組合の創始」の意味を論じてみた。そもそも1820年代初期に開始された近代協同組合運動は、ロバート・オウエンの協同社会主義イデオロギーを信奉するオウエン主義者たちが「共同の消費と共同の財産それに平等な権利」に基づく協同コミュニティの建設資金を確保し蓄積するために、産業革命の「疾風怒涛」(Sturm und Drang)の荒波に晒されていた熟練職人や熟練労働者たちによってそれまで試みられてきた、一般に「初期協同組合運動」と呼ばれる「生活防衛」のための食料品共同購入の形態を取った消費者協同組合運動、小麦粉の販売やパンの生産と販売を独占しその価格を釣り上げる地域の商人に対抗して展開された協同製粉所や協同製パン所などの生産者協同組合運動の経験をより効果的に活かし、より大規模化したものであった。ただし、オウエン主義者たちによって指導された消費者協同組合や生産者協同組合の事業はコミュニティ建設の資金を確保・蓄積することを目的としていたのであるから、協同組合の事業から得られる利益(利潤)を組合員個人の間で分配してはならないとする「利益(利潤)の不分配」の原則の厳守は当然のこととされていた。1832年4月にロンドンで開催された「第3回協同組合コングレス」は、この原則を逸脱した協同組合は「オウエン主義の世界」から排除されることを確認さえしている(協同組合コングレスは1831年5月から1835 年4月の8回にわたって開催されている。詳しくは、トム・ウッドハウス/中川雄一郎『協同の選択:過去、現在、そして未来』を参照してください)。1830年代前半から50年代後半におけるイギリス協同組合運動にあっては、一般に、オウエン主義者は「協同コミュニティの建設」を目指すとみなされてきたのであるから、オウエン主義者が指導するロッチデール公正先駆者組合(以下、先駆者組合)が協同コミュニティの建設を謳ったことは、何ら不思議なことではなかったのである。
ところで、(G.D.H.コールによると)組合員28 名のうち12 名のオウエン主義者のイニシアティヴで1844年に創立された先駆者組合は、一般に「1844年規約」と称される「ロッチデール公正先駆者組合の規則と目的」(Laws and Objects of the Rochdale Society of Equitable Pioneers)の「第1 条の前文」―この前文はその「創立趣意書」と総称されている―において、「本協同組合の目的と計画は、1 人1 ポンドの出資金で十分な額の資本を調達することによって、組合員の金銭的利益と社会的および家庭的な状態の改善のための制度を形成することにある。そのために次のような計画と取り決めを実行に移す」ことを謳い、1 項の「食料品、衣料品などの販売のための店舗の開設」から6 項の「禁酒ホテルの開設」までを記している。この1~6 項のなかでより重要な項目は1 項と5項である。5 項はこうである。「実行可能になり次第(9字傍点つき)、本協同組合は生産、分配、教育および統治の能力を備えるよう着手する。換言すれば、共同の利益で結ばれた自立的なホーム・コロニー(国内植民地)を建設し、またそのようなホーム・コロニーを建設しようとする他の協同組合を援助するよう着手する」。この5 項は、協同コミュニティの建設に着手することが先駆者組合の一つの目的である、と言っているのである。まさにオウエン主義者の「面目躍如」である。であれば、先駆者組合は「利益(利潤)の不分配」の原則を厳守して、利益(利潤)を協同コミュニティの建設資金として確保し蓄積しなければならないはずであった。オウエン主義者にとって協同組合運動の目的は何よりも「共同の消費と共同の財産それに平等な権利」を基礎とする新しい社会秩序の協同コミュニティの建設であったからである。
ところが、である。先駆者組合のその同じ「1844年規約」は、第22 条で「購買高(利用高)に応じた利益(利潤)の組合員への分配」(購買高配当)を明示し、さらに第21 条と26 条で仕入れも含めたすべての購買と販売に際しては「現金取引き」を要求したのである。要するに、先駆者組合は、第1 条の前文で「組合員の金銭的利益」と「組合員の社会的および家庭的な状態の改善」を謳い、その目的のために22 条で「購買高配当」を承認し、また21 条と26 条で「現金取引き」を要求して、「組合員の生活改善」と「協同組合経営の安定」の双方を同時に図ろうとしたのである。この「現金取引き」、すなわち、「掛買い・掛売り」の拒否は、実質的に、貧しい労働者を先駆者組合から排除することを意味した。もちろん、この「現金取引き」は先駆者組合以前の協同組合経営の失敗の経験から先駆者たちが学んだものであった。じつは、先に触れた第3 回協同組合コングレスも「蓄積された資本の不分割」、すなわち、「利益(利潤)の不分配」(「協同組合に関する諸規則・5 項」)と並んで「商取引における掛買い・掛売りの拒否」(同6 項)を強調しているのである。オウエン主義者たちの心情と信条は「はじめに協同コミュニティ建設ありき」であって、彼らの目指すコミュニティ建設に弊害をもたらすと思われた事業と運動の方策に対しては、次のように強い調子で戒(いまし)めた。「協同組合のすべての商取引きにおいて特に不可欠であると思われることは、信用掛けで貸し借りしないことである。この重要な原則からの逸脱こそ以前の多数の協同組合が崩壊した唯一の原因であったのであり、その結果、協同組合の全般的な発展を遅らせる弊害を及ぼしたのである」、と。このように強く戒めたとはいえ、コングレスは同時に、「この重要な原則が首尾よく効力をもつようになるために、組合員の間に雇用が不足している場合には、可能な限りまた地方の事情が許す限り、組合員に何らかの雇用を用意する手段を協同組合が手懸けるよう(コングレスは)勧告する。疾病の場合、他に救済の拠り所が無いのであれば、協同組合の募金からか、あるいは組合員同士の個人的な寄付金からか、金銭的な援助がなされるだろう」との「救済の自己意識」をオウエン主義者たちに求めている。
じつは、先駆者組合の「1844年規約」の第1 条にもこれと似たような(5文字傍点つき)「救済の自己意識」を求める項目がある。3 項と4 項である。
3 項:失業状態にある組合員あるいはくり返しなされる賃金の引き下げに苦しんで
いる組合員に仕事を与えるために、本協同組合が決定し得る品物の生産を
開始する。
4 項:本協同組合の組合員に対する一層の利益と安全のために、本協同組合は土地
あるいは土地の不動産権を購入もしくは賃貸して、失業している組合員ある
いは自らの労働に対し不当に低い報酬しか与えられていない組合員にその土
地を耕作させる。
見られるように、1844年規約の3 項と4 項は1832年の第3 回コングレスの5 項と6 項をある程度引き継いでいるのであって、その意味で、先駆者組合は、そのスタート時にはオウエンの協同社会主義イデオロギーを一つの重要な基本的要素としていたのである。
すぐ前で述べたように、先駆者組合は「現金取引き」の厳守を規定している第21 条および26 条を協同組合コングレスの「協同組合に関する諸規則」(以下、「諸規則」)の6 項と同じように重要原則として位置づけたが、しかし同時にその同じ先駆者組合が、「利益(利潤)の不分配」を厳守するよう謳った「諸規則・5 項」とまったく矛盾する購買高配当(第22 条)を重要原則の一つとしたのである。要するに、一方で、コングレスの「諸規則」も先駆者組合の「1844年規約」も共に協同組合事業における「現金取引き」を重要原則として承認しておいて、他方で、諸規則は協同コミュニティ建設の資金を確保し蓄積するために「利益(利潤)の不分配(傍点つき)」を承認したのに対し、1844年規約は組合員の金銭的利益と社会的、家庭的な状態の改善のために「利益(利潤)の分配(傍点つき)」を承認したのである。「協同コミュニティの建設」という同じ目的を目指した協同組合運動における両者のこの矛盾は何を意味しているのだろうか。思うに、それは、協同組合に対する協同コミュニティの位置づけについての両者の相異が言わせていること、これである。
実際、1832年4月の第3 回協同組合コングレスは、現行の経済-社会の枠組みとまったく異なる「協同コミュニティ」によって創出される平等・公正な社会秩序の基での安全な生活が組合員(メンバーシップ)に保障されるのだと主張することで「協同組合とコミュニティの一体的、一元的関係」を示唆したのに対し、先駆者組合の1844年規約は、協同組合事業が生み出す利益(利潤)が組合員(メンバーシップ)の「金銭的利益」として実現され、また「社会的、家庭的な状態の改善」として実質化されるのだと主張することで「協同組合とコミュニティの相対的、多元的関係」を示唆したのである。こうなると、協同組合とコミュニティは、遅かれ早かれ多元的な関係の下に置かれ、両者の関係に多様な要素が入り込むことになり、時としてそれらの要素が対立するようにもなる(協同組合アイデンティティとコミュニティ・アイデンティティの対立のように)。こうして先駆者組合は、協同組合とコミュニティとの関係を相対化し、多元化することによって近代的協同組合の創始になることができたのである。10年後の1854年の先駆者組合の「規約と目的」(1854年規約)からは―G.D.H.コールが強調したように―「コミュニティ建設という高邁な理想」、すなわち、「協同組合とコミュニティの一体的、一元的関係」は消え失せてしまっていたのである。では、左手(ゆんで)に「オウエンの協同社会主義イデオロギー」を掲げ、右手(やて)に「利益(利潤)の分配」を掲げた1844年規約の基で「協同コミュニティの建設」を謳った先駆者たちのパラドクスは、果たして、如何なるLogos であったのか。「言葉」なのか、「意味〔こころ〕(思い)」なのか、「力」なのか、それとも「行為(業)」なのか。
私の言う「先駆者組合パラドクス」とはそういうことなのである。しかし、私がここで強調したかったことは、この「先駆者組合パラドクス」が先駆者組合を「近代協同組合の創始」にせしめたのだということである。だが私は、先駆者組合を近代協同組合の創始にせしめた「先駆者組合パラドクス」の「説明の説明」にいささか苦労したのである。そこで私は「説明の説明」を次のように記した。「要するに、当時(飢餓の1840年代)の歴史的文脈の下で彼ら(先駆者たち)以前のオウエン主義の協同組合運動が厳守してきたルールを先駆者たちがいともた易く破ったのは、彼らには『先駆者組合パラドクス』は『絶対的矛盾(パラドクス)』ではない、とそう思えたからである。彼らが置かれていた歴史的コンテクストの下における彼ら自身の『相互救済の意識』は、彼らが『金銭的利益』と『社会的および家庭的な状態の改善』の双方を現実化させ、実質化させることによってはじめて自己意識化され自覚されるのであるから、彼らはその双方の実現を実行しただけ(2文字傍点つき)なのである。ゲーテが『ファウスト』で述べているように、『はじめに行為ありき』であって、(ヨハネによる)福音書の言う『はじめに言葉ありき』ではなかったのである。これも、先駆者たちの現実を知る自己意識が与えた『歴史的な仕事』であった、と言うべきなのである」。
さて、このように書いて「先駆者組合パラドクス」の「説明の説明」をした気になったのであるが、送付されてきた『大阪保険医雑誌』(No.561)の私の文章に目を通していくうちに、どうにも「はじめに行為ありき」というファウストの言葉が気になりだした。
新約聖書の「ヨハネによる福音書」の「はじめに言葉ありき」は「言葉は神と共にあった。言葉は神であった」、と言うのであるから、言葉は神であり、したがって、キリスト教徒の個人はそれに従わなければならないだろうが、私はキリスト教徒ではないので、「聖書」―特に「新約聖書」―には関心と興味があるものの、ファウストの「はじめに行為ありき」に「先駆者組合パラドクス」の「説明の説明」のための救いを求めたい気になったのである。
ゲーテの『ファウスト』は日本でもいくつかの出版社から翻訳されているが、岩波文庫の(学生時代に私が使用した独和辞典の著者である)相良守峯訳『ファウスト』は第1刷発行が1958年3月で、最近私が手にしたそれはなんと2013年5月で第74刷発行である。超長寿の名作・名訳なのである。
私が必要としている『ファウスト』は第一部の「書斎(一)」のほんの一部分である。ファウストが語るその箇所を記しておくと(pp.85-86)、次のようである。
われわれは超地上的なものを尊重することを学び、また天の啓示に憧れるが、その
啓示は、新約聖書に示されているものほど、貴く美しく輝いているものは外にはな
い。
あの原典をひもといて、誠実な気持ちでひとつ、神聖な原文を好きなドイツ語に訳
してみたくなった。
こう書いてある、「太初(はじめ)に言葉ありき。」
もうこれでおれは閊(つか)える。誰かおれを助けて先へ進ませてくれぬか。
言葉というものを、おれはそう高く尊重することはできぬ。
おれが正しく霊の光に照らされているなら、これと違った風に訳さなくてはなるまい。
こう書いてみる、「太初に意味(こころ)ありき。」(「意味」の代わりに「思い」とい
う他の訳もある)
軽率に筆をすべらせぬよう、第一句を慎重に考えなければならぬ。
一切のものを創り成すのは、はたして意味(こころ)であろうか。
こう書いてあるべきだ、「太初に力ありき。」
ところが、おれがこう書き記しているうちに、早くもこれでは物足りないと警告す
るものがある。
霊の助けだ。おれは咄嗟(とっさ)に思いついて、確信をもってこう書く、「太初に
行為(業)ありき。」(「業」の代わりに「行為」とする訳が一般的になっているので、
私も「はじめに行為ありき」としている)
ドイツ人であるゲーテは、この「言葉」に、すなわち、ラテン語のLogos(「言葉」の意)に拘(こだわ)ったようである。聖書の原典はラテン語で書かれていたので、Logos はそれこそもっと広義の意味を持っているはずだ、と。英語の聖書ではLogos は「神の言葉」であり、したがって、「三位一体」の第二位であるキリスト(神・<神の子>キリスト・聖霊)を意味するので、「はじめに言葉ありき」は”In the beginning was the Word”、となる。この「神の言葉」は絶対的真理を意味する言葉である(言葉は神と共にあり、また言葉は神である; and the Word was with God、 and the Word was God)。しかし、ゲーテは、Logos に「言葉や意味」以外のもっと広い概念、例えば理性、しかも神の創造的理性、あるいは精神を持たせようと考えたのではないか。このことは私の勝手な推理なのでどうでもよいのであるが、ゲーテが「言葉」ではなく、「行為」”Im Anfang war die Tat.” と書き記したのは、人間は、その直面する矛盾や困難に立ち向かい―結果的に、したがって、歴史的に見ると―それらの矛盾や困難を克服しようと努力するプロセスにおいて、それらの矛盾や困難の背後で蠢(うごめ)いているさまざまな物事の本質を照らしだす、これが人間のなす「業」であり「行為」であることを現在と未来の人間同胞に示したかったからではないか、と私は理解したい。
先駆者組合における「はじめに行為ありき」の「説明の説明」はゲーテというかファウストの「力」を借りての説明であったが、私としてはもう少しファウストの「力」と、今度はメフィストフェレスの「力」を借りて、先駆者組合の「説明の説明」について簡単に触れておこう。ただし、これも、もちろん、私の勝手な推理である。
ファウストが確信をもって「はじめに行為ありき」とするや、むく犬がメフィストフェレスに変身する。その後のファウストとメフィストの会話が大変面白い。そこで随時、協同組合に関わる私のno good な推理を[ ]で記しておきたくなった(網掛け部分)。
ファウスト:名はなんというのかね。[ロッチデール公正先駆者組合]
メフィスト:これはつまらんお尋ねですね。言葉[Logos]というものをあれほど軽んじ、
一切の見せかけを遠く踏みこえて、本質の深みへ迫ろうとなさる先生とし
ては。[われわれは「先駆者組合パラドクス」を追求するのだ]
ファウスト:だが君たちの場合は名さえきけば、たいてい本質が読めるものだ。蠅(はえ)
の神とか破壊者とか、嘘つきなどといえば、それではっきりし過ぎるくらい分
るじゃないか。[われわれの場合は「高邁な理想の消失」である] まあよい。
では君は何者だ。[近代協同組合の創始]
メフィスト:常に悪を欲して、しかも常に善を成す、あの力[Logos]の一部分です。[現金
取引きを原則化してそれを厳守し、一方で協同組合を必要とする貧しき人
びとを排除し、他方で購買高配当によって協同組合経営の安定と組合員の
金銭的利益とを実現する]
ファウスト:その謎のような言葉の意味(こころ)[Logos]は。[近代協同組合の原罪]
メフィスト:私は常に否定するところの霊なんです。[協同組合は、それ自身のうちに固
有の否定を、すなわち、矛盾を生み出すが、しかしまた、その矛盾を否定
することによって新たな理念や目標を創り出し、かくして、協同組合の発
展が生み出される] それも当然のことです。なぜといって、一切の生じ来
るものは、滅びるだけの値打ちのものなんです。それくらいならいっそ生
じてこない方がよいわけです。そこであなた方が罪だとか破壊だとか、要
するに悪と呼んでおられるものは、すべて私の本来の領分なんです。
ファウスト:君は自分で一部分と称しながら、全体としてここに立っているじゃないか。
[具体的存在としての協同組合は、動物や植物がそうであるように、自己の
各部分全体が成長することによって発展する]
メフィスト:私はただ掛値(かけね)のない真実を申し上げたんです。人間という馬鹿げ
た小宇宙は、通常自分を全体だと思いこんでいますがね―[先駆者組合もオ
ウエン主義あるいはオウエン派協同社会主義のコンセプトの基で育ち、そ
の一部を否定することによって近代協同組合の創始たる栄誉を得た]
私などは、初めは一切であったところの部分の、そのまた部分です。光を
生んだ闇の一部なんです。[ヨハネによる福音書は言う:言葉には命があり、
この命は人びとの光であった。光は闇のなかに輝いており、そして闇は光
に勝たなかった。しかし―とゲーテは言う―じつは闇こそが光を生むので
あるから、光が闇のなかで輝くためには、先駆者組合を創始とする近代協
同組合はその原罪を常に克服しようと努力しなければならない。協同組合
は「正気の島」になるよう努力しなければならない] 高慢ちきな光は、今
や母なる闇を相手に、古い地位と空間を争っていますが、うまくゆきやし
ません。どんなにもがいたって、光は物体にくっついたまま離れないから
です。光は物体から流れ出て、物体を美しく見せますが、しかし物体は光
の進路をさえぎるんです。だからたぶん遠からずして光は、物体と共に滅
びるでしょう。
ファウスト:それで君のえらい任務というものは分った。君はしかし大規模に破滅させ
るわけにはいかないので、こきざみにやり出しているというわけだろう。
メフィスト:それでも無論たいしたことはできんですよ。無に対立している或る物です
ね、つまりこの気のきかない世界というやつですね、こいつは、私がこれ
までやってみたところでは、なんとも手に負えないやつなんです。津波、
暴風、地震、火事、いろいろやってみますが、結局、海も陸も元のままに
平然たるものです。それにあの忌々(いまいま)しいやつ、動物や人間の
やからときたら、どうにも手のつけようがありませんや。これまでもどれ
ほど葬(ほうむ)ってやったでしょう、それでも新鮮溌剌(はつらつ)た
る血が依然として循環するのです。
こういう工合(ぐあい)だからわれわれも気が狂いそうになるんですよ。
空気から、水から、地面から、千万の芽が萌え出してくる、乾いた所から
も湿った所からも暖かい所からも寒い所からもです。[それでも今では、協
同組合は世界のどの地域のどの国にも、すなわち、東西ヨーロッパ、南北
アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアの諸国に、それに―忘れていたが
―ロシアとかつてソヴィエト連邦を構成していたいくつかの独立した国々
に多様な協同組合が設立されている]
あの火というやつを私が保留しておかなかったら、これぞという特別な武
器が何もなくなるところです。[協同組合人は、オウエン主義イデオロギー
を歴史的文脈の下で吟味することを通じて、協同組合の新たな理念や目標
を思考するのだ]
ファウスト:そこで君は永遠に休むことなく、恵みゆたかに創造をつづける威力[この力、
すなわち、Logos はまさに矛盾を止揚(アウフヘーベン)してより高次の
統一を創り出すための「行為」である]に対し、冷たい悪魔のこぶしを振り
あげているわけだが、その陰険に握りかためたこぶしも無駄なことだ。
混沌の生み出した奇怪な息子よ。何かほかの仕事をさがす方がよさそうだ
ぞ。
かくして、私はこのページを閉じることにする。
●理事長のページ(No.42)●2013年05月31日
経済学と倫理(2) 中川雄一郎
前号(No.41)の末尾で私は、昨年度の3年生ゼミナールで使用した外書購読のテキスト『市場を考える:経済学の倫理的考察』(Reckoning with Markets: Moral Reflection in Economics、 by James Halteman and Edd Noell、 Oxford University Press、 2012)の序論のほんの一部を紹介しておいた。それは、著者のホルトマン教授がロシア文科省からの依頼でMBA(経営学修士)のカリキュラム設置プロジェクトに関わった際に「ビジネス倫理グループ」のあるロシア人教授に問いかけた「経済と倫理」についての「質問」と「答え」のエピソードであった。ホルトマン教授は―市場経済は「人びとがお互いに信頼し合う」ことを前提とする、という意味で―ロシア的文化としての「経済と倫理」の問題についてロシア人教授に問いかけたのであるが、そのロシア人教授はそれを「(損得の)経済的な好機」のことと思い違いをして答えた、というものであった。
「経済学と倫理」という命題(テーゼ)は、しばしばこのような思い違いを起こさせるのであるが、その思い違いの主たる要因は、外でもない、これまで主流の経済学が「経済学は価値判断をしない」(value free)としてきたことに由来するのである。ところが近年、国や地域それに人びとの間での経済的、社会的な相互依存の観念の広まり、ゲームの理論や行動経済学の出現によって「経済学的考察」に心理学をはじめとする他の社会科学が浸透してきたことから、経済学に関わる思考はどのレベルにおいても「価値判断」(value judgments)を避けて通ることができない、との主張が次第に支持されるようになってきたのである。
そこで、私は、本年度のゼミナールでの外書購読では「経済学は価値判断する」という観点から、経済学の研究においてはどのように「倫理的考察」が展開されるのか、を理解するために『救済の経済学:アダム・スミスとヘーゲル』(Yong-Sun Yang、 Economies of Salvation: Adam Smith and Hegel、 Peter Lang、 2011)を使用することにした。だがじつは、私のゼミナール学生がどこまでこのテーゼを理解できるかは、今のところ私は何とも判断し難いのである。それでも、世界の近代史のなかの重要ないくつかのシーン、例えば、トマス・ホッブズ(1588—1679)、ジョン・ロック(1632—1704)、ジャン・ジャック・ルソー(1712-1778)、それに18世紀の啓蒙主義などの思想と運動の歴史的役割も合わせて学習することを通じて「経済学と倫理」の根本についてある程度の認識を学生が感じ取ってくれるのではないか、と私は密かに期待しているのである。
言うまでもないことだが、このようなテーゼはより慎重に扱われなければならないだろう。何故なら、経済学の主流がこれまで主張し続けてきた「経済学は価値判断をしない」との観念にある種の「風穴を開ける」ことになるからである。とはいえ、経済学は「持続可能な社会秩序を維持する」というシチズンシップで言うところの市民の「参加の倫理」にも大いに関係してくるのであるから、「経済学と価値判断」というロジックは市民社会における経済的、社会的それに政治的な諸制度を市民生活に有効に機能させることに寄与するだろう、と私は主張したい。その意味で、『救済の経済学』は経済あるいは経済学についての「倫理的思考」あるいは「倫理的考察」の現実的な有意義性をアダム・スミスとヘーゲルが「経済学とキリスト教神学の対話」を通じて語ってくれることを私は大いに期待しているのである。ましてや現代は、個々人の生活信条、価値観、宗教心といったものがますます経済や社会のシステムの歯車を動かす潤滑油として機能していく時代である。ホルトマン教授が、各時代には「物事を動かすことができる実体(existence)を形づくっておくためにさまざまな社会階級を結び合わせ合意させるような―権力構造に連動する―社会的、経済的な諸制度」が存在するのであって、「そのような社会的、経済的な諸制度や人びとの信条、価値観、宗教心といった諸力が相互に補い合うことで一つの束ねられた力となった文化は、それらの諸力が相矛盾しながら生き延びようとした文化よりもずっと長く持ちこたえてきた」と論じている意味が分かるというものである。その点でも、「経済と倫理」あるいは「経済学と倫理」というテーゼはまた、現代のわれわれの生活世界にとって大いに意義のある研究対象である、と言うべきであろう。
『救済の経済学』は何を追究するのか
さて、『救済の経済学』であるが、この著書は、「経済学の学問分野とキリスト教神学の学問分野には重要な繫がりや関連がある」ことを前提に論究がなされている。著者のヤーン博士によると、「実際のところ、二つの学問分野の大きなギャップは比較的近年の現象であって、ずっと以前の時代にあっては経済学と神学は極めて密接に絡み合っていたのである」。その証拠に、多くの経済用語や経済理念が「罪や過ちと救済といった神学上の問題や課題を説明するのに聖書のなかで使われている」のである。例えば、マタイによる福音書の「葡萄園の労働者」(『新約聖書』20:1~16)がそれであって、(葡萄園で働いた労働者に労働時間に関係なく1日1デナリの賃金を支払った)この寓話のように、「宗教的救済を説明するために経済用語を使うことは、一見別々の物事のように思える主題や対象の間に見られる関係を確証する可能性を示唆しているのである」。
では、このように、経済学とキリスト教神学(以下、神学と略称)との間に何らかの関係があるとするならば、「人間的な経済」(human economy)と「神の摂理」(God's providence)との間の正当な関係はどのようなものであるのだろうか。このことを追究するのが本書の論点であるが、同時にこの論点を追究することによって経済学と神学の関係は単なる神学的な倫理に関わる事柄を超え出ていることを、言い換えれば、経済思想は基本的に神学思想に基礎を置いており、また反対に神学思想も経済的側面を色濃く持っていること、これらのことを本書はアダム・スミスとG.W.F.ヘーゲルの「経済思想と神学(宗教的信条)」に論及することで明らかにし、以って「救済の経済学」の、したがってまた、現代における「経済の倫理」を考察しようとする、いわば「新倫理経済学アプローチ」とでも言うべき力作である、と私には思えるのである。
「アダム・スミスとヘーゲル」を知ることの意味
ところで、私が本書に当初興味と関心を抱いたのは本書のメインタイトル「救済の経済学」よりもサブタイトルの「アダム・スミスとヘーゲル」の方であった。「マニュファクチャーの時代」と称されるイギリス産業革命期の1759年にThe Theory of Moral Sentiments(日本語訳『道徳感情論』)を、また1776年にAn Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations(『諸国民の富』または『国富論』)を著したイギリスのアダム・スミスと、そのスミスに遅れることおよそ30年後の、しかも依然としてカントの言う「虚偽の国家」が存続し、ナポレオンによる軍事的支配を受けていた時期の―したがって、ドイツ・ロマン主義の最中にあった―1807年にDie Phänomenologie des Geistes(『精神現象学』)を著したG.W.F.ヘーゲルを比較して論じる試みに私は興味と関心を大いに抱いたのである。というのは、アダム・スミスとヘーゲルの両者を比較研究するのであれば、経済思想と神学について両者に共通する点と対立する点が論究されるだろうし、しかも両者の生きた時代背景の相異を考慮して論究される極めて興味深い経済思想研究である、との期待が私に湧いてきたからである。
こうして私は新学期のゼミナールが始まるまでに本書の論旨をある程度学生に要領よく説明できるように目を通しておこうと思い、毎日少しずつ読み進めていった。ところが、である。読んでいくうちにあることに気がついたのである。それは、私の知っているアダム・スミスは『諸国民の富』のアダム・スミスであって、『道徳感情論』のアダム・スミスではないこと、またヘーゲルに至っては彼の断片的な哲学思想を通じてのヘーゲルにすぎないこと、これであった。
そこで私は―「時間の余裕」がそう多くないこともあり―スミスの『道徳感情論』とヘーゲルの『精神現象学』とに関わる書籍を数冊ずつ読むことにして、本書と向き合うことにした。現在、本書を中程のところまで読み進めてきて分かったことは、アダム・スミスとヘーゲルの両者に共通する用語が「自己意識」あるいは「自己意識願望」であること、そしてアダム・スミスに特有の用語が「利己心」で、ヘーゲルに特有の用語が「理性の狡知」である、ということである。
そしてもう一つ両者の共通点をあげると、それはカール・マルクスである。若きマルクスは「青年ヘーゲル学派」であったし、ヘーゲルの弁証法を学び、またヘーゲルの『法の哲学』(1821年)に対する批判を通してマルクスは自らの思想を高めっていった。マルクスのヘーゲル法哲学批判には次のような有名な言葉があるが、その言葉は、われわれにとって、現在の「自民党・安倍政権」に対する厳しい批判であるようにも思えるので、ヘーゲルと「自民党・安倍政権」を同等に置くようでヘーゲルとマルクスには誠に申し訳ないが、ここに記しておく。
ヘーゲルは国家から出発して、人間を主体化させた国家にする。ところが、民主制は人間から出発して、国家を客体化させた人間にする。宗教が人間をつくるのではなく人間が宗教をつくるように、憲法が国民をつくるのではなく国民が憲法をつくるのである。
マルクスはまたイギリスに亡命して経済学の研究を本格的に始め、British Libraryの書籍や雑誌、政府資料などを利用して『剰余価値学説』をはじめとする経済学批判を研究し、『資本論』―『経済学批判』―を世に出した。その時期にマルクスが使用したLibraryの椅子は現在でも残っている。またマルクスはイギリスに亡命する前の1844年にパリにおいてスミスやリカードなど古典派経済学を批判的に検討したノート『経済学・哲学草稿』を書き、「私有財産」が「疎外された労働」の帰結であることを論じている。この「労働の疎外的構造」の究明は今日までその影響力を保持しており、世界の多くの人たちの知るところでもある。このような意味で、カール・マルクスは、現代のわれわれから見ても、アダム・スミスとヘーゲルの共通の人物なのである。
さて、締めくくりに、「なぜアダム・スミスとG.W.F.ヘーゲルか」を論じているヤーン博士の言葉を引用しておこう。われわれはヤーン博士の言葉をどう受け止めるだろうか。
道徳哲学者としてのアダム・スミスは人間の諸関係における道徳的側面の重要性を軽視しはしない。人間は唯我論的原子としての社会に生まれるのではなく、個々人が他者と関係を持つ社会に生まれるのであるから、われわれがそこで生活している社会はまさに単なる個人の総計以上のものなのである、と彼は考えている。彼の「利己心」の理念は、「自己中心」(selfishness)ではなく、むしろ個人的願望と社会福祉との間の緊張関係を調和わさせるのに必要な「自然な自己意識」(natural self-consciousness)である。それ故、なぜ彼が、個人と社会の双方にとっての「利益の伝動装置」として利己心の役割に注目したのか、という経済的、道徳的それに神学的な理由を理解することが重要なのである。(中略)
本書で論究されるもう一人の思想家はG.W.F.ヘーゲルである。ヘーゲルは彼の思想体系全体を貫いている循環論法や弁証法的論理でよく知られている人物である。彼は確かに現代的な意味での経済学者ではないとはいえ、彼が近・現代に及ぼしてきた直接、間接の影響力は無視できないものである。とりわけ、「理性の狡知」(cunning of reason)についての彼の理念にきめ細かい注意が払われなければならない。何故なら、「人間の理性的能力」(human rational ability)を彼が大いに強調していることを考慮すると、歴史に現れた「人間の情念」(human passion)の積極的役割を彼が承認していることは奇妙に思えるからである。では、「理性の狡知」という表現を以ってヘーゲルは何を伝えようとしているのだろうか。そこには人間の情念が理性の狡知であると断言するいかなる神学的根拠があるのだろうか。ヘーゲルはどのようにして(人間の)原罪(original sin)を自らの思想体系に持ち込むのだろうか。ヘーゲルの経済的理念に埋め込まれているキリスト教神学の教義とはどんなものであろうか。もし教義があるとすれば、その神学的背景によって彼の経済的理念はどのように影響を受けたのであろうか。これらの推論は経済学と神学との関係についてどのようなことを含意しているのだろうか。そして最後に、ヘーゲルの「経済生活の神学」における救済は何を意味しているのだろうか。これらのことが議論されるべき主要な問題なのである。
●理事長のページ(No.41)●2013年02月28日
経済学と倫理(1) 中川雄一郎
ここ数年、私は大学(学部・大学院)での講義や協同組合などの講演でできる限りフェアトレードについて触れることにしている。そうするようにした一つの大きな理由は「経済と倫理」について私なりに考えを深めてみようと思ったからである。
一般に私たちは、その日常生活のなかで時として次のような経験に出くわすことがあるだろう。かつて読もうと思っていたが、やがて忘れてしまったり、あるいは忘れかけたりした学術書や小説などの本―今では古本となっている本、あるいは他の著者や訳者によって深められたり読み易くなったりしている本、さらには相当数の「刷り」を重ねていたりしている本―に偶然に出会い、そしてそれらを手にしてからは「忘れてしまった時間を取り戻す」かのようにそれらの本を読む、これである。このような生活経験は「歳と伴に増えていく」ようであるが、私の場合それはなにも本に限ったことではないのである。じつは、「フェアトレード」がそのような経験の一つなのである。とはいえ、それは、私自身がフェアトレードに直接関わったのではなく、私の協同組合研究との関係でのことにすぎないが、それでも私にとっては「経済と倫理」について考えを深める良き機会を与えてくれたのである。
以前私は、1970年代から2000年初期にかけてのイギリス消費者協同組合(生協)運動について調べたことがあった。周知の通り、イギリスでは1973~4年のオイルショック以降90年代初期頃まで経済状況はいわゆる新自由主義政策を展開する「サッチャーリズム」によって総じて金融以外の経済は不安定で、とりわけ失業率は10~12%であり、若者(15~24歳)のそれは20%前後を推移していて経済的、社会的な格差の広がりが大きな社会的問題になっていた。このような経済状況は、労働者階級を主たる組合員や顧客とする生協に大きな影響を及ぼし、CWS(協同卸売り組合)を中心に生協陣営はその対策に追われ、「生協は崖っ縁」と言われもし、生協合併をその最後の対応策として進めていった。ところが、その生協が「崖っ縁」からやがて再生するのである。その生協再生の契機を与えたのがフェアトレードであった。
フェアトレードに私が関心を持つようになったのは1990年代中頃であった。私は、1985年から86年にかけてブラッドフォード大学平和研究学部(Department of Peace Studies)で「キリスト教社会主義と協同組合」のテーマを追究したこともあって、それ以後毎年のようにロンドンやマンチェスターそれにリーズとブラッドフォードを訪れては上記のテーマを追い続け、そのための文献・史料・資料を漁っていた。そんな時にマンチェスターにあるCWSの歴史的な建物「ホリヨークハウス」の協同組合図書館を訪ねて、イギリス協同組合連合会(Co-operative Union、 現在はCo-operatives UK)の初代会長でありキリスト教社会主義者のエドワード V. ニール(1892年没)に関する資料を漁っていたのであるが、ふとフェアトレードのパンフレットが目に止まり、それには確か紅茶、コーヒーそれにバナナのフェアトレードに生協が奮闘している旨のことが書かれていたようであった。そしてその時に私は「そう言えば、私のイギリス土産はコースターと紅茶(主にティーバッグ紅茶)の代わり映えしないものであるが、紅茶はフェアトレードの認証マーク付きである」とのことに気づいた。私はこれらの土産を(現在は存在しないが、当時はリーズ駅近くの大きなビルの一角を占めていた)リーズ生協の店舗とマンチェスター、ヨークそれにロンドンなどにある有名なスーパーマーケット「マークス&スペンサー」で買い求めた。今でも私のイギリス土産はコースターとフェアトレード紅茶と決め込んでおり、日本のそれらと比べると安価で良質であると私は思っている。
さて、私は、1990年代末から2000年中葉にかけて「(合併が一段落したこともあって)イギリスの生協は立ち直り、前進しつつある」との声を聞くようになり、その立ち直りと前進の大きな要因の一つ(あるいは二つ)が「フェアトレード」と、そのフェアトレードと密接に関係する―あるいはフェアトレードに影響を受けた―「倫理政策」とである、と聞き知らされるようになった。そこで私は、2007年の秋に―あの時のことを思い出しながら―ホリヨークハウスにある協同組合図書館のMrs. Gillian Lonergan(Librarian)にイギリス生協運動とフェアトレードの関係を教えてくれる資料を送っていただくようお願いした。彼女が送ってくれたのは単なる「資料」ではなく「本」であった。それがCo-operation、 Social Responsibility and Fair Trade in Europe (Edited by Linda Shaw)、 Co-operative College、 2006.である。そこで私は2008年度の3年生ゼミナールのテーマを「フェアトレード」とした。ゼミナール生たちはよく学習し、また積極的に経験した(その成果は、ゼミナール生による論稿「フェアトレード:オルタナティヴ・トレードの経済-社会的役割」(明治大学政経学部『政経セミナー』第37号、2008年度に記されている)。彼らはフェアトレードの学習のために映画「フェアトレードの真実」を学内で上映し、またフェアトレードのクッキーを販売する活動も展開した(この活動は現在、学内の「ボランティア・サークル」に受け継がれている)。フェアトレードを学習していくなかで、元フランス大統領ジャック・シラクが「フェアトレードを広げていけば、消費活動と倫理的価値や人間の尊厳の保護とが両立するだろう」と述べたことを知って、同じ保守的政治家でも(日本の)政治家と大分違う、と一人のゼミナール生が呟いていたことが思い出される。
ところで、イギリス生協運動であるが、組合員教育を通して組合員に生協がフェアトレードに取り組む経済的、社会的な意義と意味の双方を理解させると同時に、フェアトレード商品の販売を促進するイベントに多くの組合員を引き込み、組合員にそのための活動に時間を割いてもらうよう働きかけた。その結果、「生協に加入して組合員になることが、フェアトレードに参加することになる」との意識を市民の間に醸成することになったのである(一般にヨーロッパでは―日本と違って―生協に加入しなくても、すなわち、組合員でなくても、生協の店舗を利用することができる)。イギリス生協運動のフェアトレード運動へのこのような取り組みは「協同組合の価値をビジネスの実践に組み入れる一つの主要な手段」となっていき、生協の全般的な発展をもたらしたのである。
こうして、生協運動とフェアトレード運動とは相互に影響を及ぼし合い、後者が生協の再生・再活性化に寄与し、また前者がフェアトレード運動に対する市民の認知度の向上に寄与しているのである。とりわけフェアトレード運動は発展し続けており、2006年にはイギリスでは「人口の50%以上がフェアトレードを認知している」という大きな運動を展開するまでになっている。マンチェスターをはじめイギリスのいくつかの都市や町は「フェアトレード・タウン」としてフェアトレード組織から認証されているほどである。日本でほぼ同じ時期の2007年に「チョコレポ実行委員会マーケットリサーチ」が「日本でのフェアトレードの認知度」を調査したところ、わずかその認知度は2.9%にすぎなかったとのことである。因みに、イタリアは34.5%(2003年)、スウェーデンは47%(2004年)であった(調査機関が異なるので日本と他の国々とでは対応可能な数値ではないけれど、相対的な傾向を読み取ることは可能であろう。その証左として、日本でフェアトレードを小規模でも事業化している生協は本当に数少ないのである)。
イギリスでのフェアトレード運動の発展は、フェアトレードが「営利企業に利益をもたらす」ことを学習したテスコ(Tesco)、セインズベリィズ(Sainsbury's)、マークス&スペンサー(Marks & Spencer)それにモリソンズ(Morrison's)など大手企業のスーパーマーケットのフェアトレードへの進出の機会をつくり出した。私は、このこと自体は大いに歓迎するところである―というのは、私は常々、「生協の経済-社会的な一つの重要な役割は、スーパーマーケットなど大手小売流通資本に生協の『運動を真似させる』ことである」と強調しているからである―が、しかし、大手企業のフェアトレードへの大規模な参入は、「大手企業が利益追求のためにフェアトレード・ラベルを利用する危険性が出てきた」という「フェアトレード運動内部の論争」を引き起こす要因をもまた生み出しているのである(このことについては、次の機会に譲りたい)。
再び"ところで"、であるが、イギリスの生協運動は、フェアトレード運動を展開するなかで「一つの転機」を創り出した。生協の店舗にはフェアトレード・コーナーが設けられ、そこに置かれたフェアトレード製品を「ユニーク・セリング・ポイント」(Unique Selling Point)と位置づけて、生協の「重要な市場コンセプト」とし、生協が「フェアトレードのコンセプト」を遵守することを通して生協の事業(経営)スタンスを「倫理スタンス」と明確に位置づけたのである。大手小売流通資本との競争によって「低価格」を強いられてきた生協陣営は、かくして、大手小売流通資本(大手スーパーマーケットなど)との差別化を図ることができ、他の生協商品も文字通りの「公正な価格」(fair prices)で組合員や他の人たちに供給することができるようになったのである。
再び"さて"、であるが、「経済学と倫理」の「まえがき」をと思って書いていたら、だいぶ長くなってしまった。したがって、この続きは次号の「理事長のページ」に回してもらいますが、多少の予告篇を記しておきます。
本ゼミナールの「2012年度外書講読」のテキストはReckoning with Market: Moral Reflection in Economics(by James Halteman and Edd Noell、 Oxford University Press、 2012)であった。日本語に訳すと、『市場を考える:経済学の倫理的考察』とでもなるだろう。この本はオクスフォード大学の各カレッジの経済学専攻3年生のための一種の教科書である。この本の最初の部分でホルトマン教授はロシアでのMBA(経営学修士)のカリキュラム設置プロジェクトに参加してロシア人教授陣と関わったエピソードを記している。その箇所を引用することで次号の予告篇としておくので、皆さんには想像逞しくしていただければと思います。
われわれの(プロジェクトの)仕事が捗っていくにつれて、私は悲観的になり始めた。何故なら、彼らは、市場理論には人びとがお互いに信頼し合うようになることが求められることなどまったく考えていないのだ、とのことを私は悟ったからである。私はビジネス倫理グループのロシア人教授に、「人びとがお互いに信頼し合わない」という点について、こう問いかけてみた。すなわち、ロシア市民は、ロシア的文化としては、セルフサービスのガソリンスタンドでは誰も見ていなくてもガソリン代をきちんと支払っていくのか、あるいはガソリン代を支払わないで立ち去っても捕まる心配がないがまったくないのに、眠っている店員を起こしてガソリン代を支払っていくのか、と。彼は、しばらく考えて、「ノー」、つまり「支払わない」と答えた。彼は、私の筋書き(シナリオ)を、倫理的な問題を論及しているのではなく、経済的な好機について論及しているのだ、とそうみなしたのである。
この本は、アダム・スミスやマルクスにも論及しており、「経済学と倫理」という点で中々興味を覚えるのであるが、本ゼミナールの3年生には難しかったようである。そこで私は、2013年度の外書講読はオクスフォード大学経済学専攻学生(3年生)―イギリスでは一般に、経済学など社会科学専攻や文学専攻の学生は3年生で卒業である、と聞いている―向けの別の教科書を使用する予定である。この本も中々インタレスティングである。原書名はEconomies of Salvation: Adam Smith and Hegel(日本語訳を私は『救済の経済学:スミスとヘーゲル』にしようと考えている)。
これら2つの教科書は「経済学にはあるいは経済には倫理がその基礎にある」ことを強調しているのである。
●理事長のページ(No.40)●2012年12月31日
シチズンシップ再考 中川雄一郎
私は以前2度ほど「理事長のページ」でシチズンシップに関わる拙文を書かせていただいた(2010年7月31日付「『シチズンシップと地域医療』補遺」、2011年5月20日付「原子力発電(原発)のリスク認識とシチズンシップ」)。前者は、アマルティア・セン教授(現在はハーバード大学教授)の「新自由主義批判」と「人間の安全保障」の基本認識は「福祉を基礎とする社会」を形成していくための「人間的な経済と社会にとっての中心的戦略」であり、「社会的平等と公正の確立と普及に貢献し、広く人間的な経済と社会の発展に役立つ運動を展開する」シチズンシップに基づく協同のアプローチである、とのことに言及した内容である。
後者は、2011年5月13日付の朝日新聞(「オピニオン欄」)に「原発事故の正体」と題されて掲載された、著名なドイツ人の社会学者であるミュンヘン大学のウルリッヒ・ベック教授へのインタビュー記事である。そのなかでベック教授は「これはとても重要なことですが、近代化の勝利そのものが私たちに制御できない結果を生み出しているのです。そしてそれについてだれも責任を取らない。組織化された無責任システムができあがっている。こんな状態は変えなければならない」と強調し、また「原発を受け入れてきた政治家たちに責任を取らせることなど期待できないのではないか」とのインタビュアーの質問を受けて、こう答えている。「ドイツには環境問題について強い市民社会、市民運動があります。緑の党もそこから生まれました。近代テクノロジーがもたらす問題を広く見える形にするには民主主義が必要だけれども、市民運動がないと、産業界と政府の間に強い直接的な結びつきができる。そこには市民は不在で透明性にも欠け、意思決定は両者の密接な連携のもとに行われてしまいます。しかし、市民社会が関われば、政治を開放できます」。この時私はベック教授のこの言葉を「市民による参加の倫理」に基づく「シチズンシップの実践力」と理解した。そしてベック教授はこう締めくくった。「産業界や専門家たちにいかにして責任を持たせられるか。いかにして透明にできるか。いかにして市民参加を組織できるか。そこがポイントです。産業界や技術的な専門家は今まで、何がリスクで何がリスクでないのか、決定する権限を独占してきた。彼らは普通の市民がそこに関与するのをのぞまなかった」、と。彼のこのような主張こそ、「自治・権利・責任・参加」をコアとするシチズンシップの真髄を表現しているのである。
ところで、年の瀬も押し迫ってきた12月16日に投票が行われた衆議院議員選挙であるが(同時に行われた東京都知事選挙については別の機会に譲ることにする)、周知のような結果に終わった。「シチズンシップの目」から見ると、この選挙結果は政治的、経済的それに社会的に大きな危険性を内包した議会構成と政府の登場だということである。というのは、私が見るところまた聴くところからすると、この議会の3分の2を構成する議員の―すべてではないが―多くは、自由主義が平等と個人の権利を擁護することによって市民の権利の侵害や不公正に異議を申し立てる「シチズンシップの理念」の及ぶ範囲を広げていった「自由主義の理想」など到底語りえないと思えるからである。むしろ彼らは、シチズンシップが内包する社会包摂的性格を「排他的アイディア」に基づいた権威主義的性格に代えてしまったり、シチズンシップの民主主義的特質を単なる多数決や道具主義に基づいた競争的な「原子論的性向」に代えてしまったりするかもしれないのである。したがって彼らは、市民の権利と政治的コミュニティの密接な関係、すなわち、「政治的コミュニティが権利を支えてくれるが故に、市民は自らの権利を行使する」とか、あるいは「市民の権利は政治的コミュニティの利益に欠くことができない」とかいう意味を理解し得ないかもしれない。だがもし彼らがこれらのことを理解し得るのであれば、彼らは―ベック教授が述べているように―市民社会が、すなわち、「健全な政治形態には積極的で活動的な一般市民」が必要とされることに気づくかもしれない。そうであれば、彼らはまた、権利と責任は対立するのではなく、相互に依存し支え合うことに気づくかもしれない。しかし、そうなるのには彼らは依然として市民的、政治的な想像力に欠けている、と私には思われる。
「市民の責任」の目的の一つは「個々の人たちを結びつける紐帯を強固にすること」であり、そうすることによって「自由主義の原子論的性向を相殺すること」である、としばしば言われるが、しかし、現代の自由主義社会は、シチズンシップを行使する機会があっても、そうすることができない組織構造―もっと言えば、社会構造―になってしまっているのである。この点についてはヨーロッパ諸国での「政治的参加」についての研究が示唆しているが、例えば、「小選挙区制」の下では「市民の責任」が果たせない、という声に見られるように、市民がその政治システムや代議制に対して次第に信頼を失っていき、投票率も年々下がってきているし、政党もその党員数を減らしてきている大きな要因になっているのである。とりわけ若者の投票率の低さについて各国政府はその対策を急いでいる。
EU(ヨーロッパ連合)加盟国ではそのために「シチズンシップ教育」を小学校高学年と中学生には必修教科(高校生には準必修科目)としているそうである。何のための「シチズンシップ教育」かと言えば、若者が「政治文化を変えていく」役割を果たすためである。だが、この「政治文化を変える」という主張の背景には「差し迫った脅威」があるのだ。それは、社会の高齢化に伴ってますます明らかになる「世代間の衝突」という現象である。G. エスピン‐アンデルセンがその著書『アンデルセン、福祉を語る:女性・子ども・高齢者』(京極高宣監修/林昌宏訳、NTT 出版)で述べているように、「平均的有権者が高齢化するにつれて、選挙民はますます退職者の利益のために投票する。実際に、ヨーロッパの平均的有権者はすでに50歳代に近づいている。高齢な市民ほど政治活動に関心があるとすれば…政治状況は明らかに高齢者の政治圧力団体に有利になる。…子ども、学校、家族に対する投資は控えて…高齢者には寛大な政策を施すというシナリオである」。もっとも、橋下徹大阪市長は「若者(子供、学校、家族)にも高齢者にも徹底して冷たい」ようであるが、今回の総選挙の投票率はアンデルセンの言葉に一層の信憑性を持たせるかのようである。
すなわち、(1)投票率は戦後最悪の59.32%(先回69.28%より約10%減)、(2)全有権者数・約1億396万人、(3)投票者数・約6167万人、したがって(4)投票棄権者数・約4229万人、(5)全有権者に占める20 歳代と30歳代有権者の割合と有権者数:約31%、約3223万人((6)このうち何%が投票したかの統計結果はまだ出ないが、先回の約56%に合わせてみると投票者数・約1800 万人、棄権者数・1420 万人となるが、したがって投票率が10%減の今回は1800万人より少ないだろう)となる。形式的にはマスコミは「自民党と公明で3分の2の安定多数を確保」と言うのであるが、約4229万人もの市民が投票する権利、政治的意思決定の権利を棄権したこの状態をマスコミも「安倍内閣」もどう説明するのだろうか。「世代間の衝突」を避けるために日本でも「シチズンシップ教育」を実行することが求められるのである。
●理事長のページ(No.39)●2012年08月31日
少子高齢社会と雇用問題(2) 中川雄一郎
本「研究所ニュース」(No.39)の発行が大きく遅れてしまったことを―冒頭のこの場をお借りして―会員の皆様に深くお詫びいたします。前回の「研究所ニュース」(No.38)の発行が2012年5月31日なので、およそ3カ月が経ってしまったことになる。誠に以て申し訳ありません。何しろ、「理事長のページ」から始まる「研究所ニュース」なのであるから、突発事故や緊急事態を別にすれば、日常の予測される事態や物事に備えておかなければならないのに、そうすることを怠ってしまいました。重ねてお詫びいたします。
前号の「理事長のページ」は、世界的に著名な福祉研究者であるG.エスピン・アンデルセン教授の(フランスの一般読者に向けて書かれた)著書『アンデルセン、福祉を語る:女性・子ども・高齢者』(京極高宣監修/林昌宏訳、NTT出版、2008年)を引用することで「少子高齢化と雇用問題」について考えるきっかけを得ようとしたものである。すなわち、前号の「少子高齢化と雇用問題(1)」は、この著書の「レッスン1・家族の変化と女性革命」の一部を紹介することで、「少子高齢化」という21世紀初期における経済-社会的な状況を踏まえ、「公正」あるいは「公平」の原則を旨とするいかなる福祉制度が追求されるべきか、を考える示唆をわれわれは期待したのである。そこで、本号の「少子高齢化と雇用問題(2)」であるが、これは、『季刊労働法』(第236号)に掲載された拙論「高齢者の雇用・就労と社会的企業」に基づいて、日本における「年金受給年齢と定年退職年齢のギャップ」による高年齢者(高齢者)の雇用・就労について思考するきっかけとなれば、と考えて簡潔に述べたものである。ところで、本ページでは今述べた主旨に即して「高年齢者の雇用」について思考する訳であるが、ここでも―前号程でないが―アンデルセン教授の「レッスン3・高齢化と公平」の一部をベースに言及することをお断りしておく([]は中川による)。アンデルセン教授のここでの理論もまた大いに説得力を持っているからである。
高齢化と年金改革について
アンデルセン教授は、高齢化が及ぼす経済-社会的な影響についてこう論じる。「少子高齢化こそ人口の高齢化の原因である。合計特殊出生率の低下により、人口に占める高齢者の割合は増加する。平均寿命の伸びは、高齢者がさらに高齢者になることを意味する。低迷する合計特殊出生率が([高齢者化の])『第一推進要因』であるとすれば、高齢化は人口の減少と同時進行する。この減少が急速である場合、GDPや生産性の低下を余儀なくされる」(103頁)。「高齢化にはもう一つの差し迫った脅威がある。世代間の衝突である。平均的有権者が高齢化するにつれて、選挙民はますます退職者の利益のために投票する。実際に、ヨーロッパの平均有権者はすでに50歳代に近づいている。高齢な市民ほど政治活動に関心があるとすれば、(そして少子化が続き、若年層が縮小すれば)政治は明らかに高齢者の政治圧力団体に有利なものになるだろう。……こうした状況において、年金改革は政争の論点となった。……すなわち、新自由主義者は民営化を唱える一方、労働組合や退職者団体は何としても現状を維持しようと訴えている。(じつは)こうした態度は現実的でもなければ公平でもない。……これまでの経験から言えることは、改革に正当性をもたせるために目指すべき改革は何よりもまず、公平の原則に基づいていなければならないということだ。改革が社会正義をまっとうするためには、まず(65歳以上の)老年人口と(15歳~64歳の)生産年齢人口との間で、高齢化から生じる費用を公平に配分する必要がある。この点について異議はないであろう。しかし、……([一般に])金持ちは貧者よりも長生きであることから、これは同世代の退職者間に著しい不平等を生み出す」(104-105頁)。
「高齢化自体は歴史上新たな現象ではない。前世紀を通じてわれわれの社会は高齢化し続けてきた。しかし、今回の高齢化には、われわれの時代だけのこれまでにない3つの特徴がある。まずは、高齢化のテンポが急速に加速したことである。先進国では、老年人口は現在から50年後にかけて平均して2倍になる。……2つ目のあらたな特徴とは、われわれは今後、非常に健康な日々を過ごすことになるということだ。これは平均寿命の大幅な延びを意味する。……現在、平均的退職者には、男性で80歳まで、女性で85歳まで生きられる希望がある(日本では男女共にそれ以上である)。(したがって)退職者が増えるばかりでなく、増加した年金受給者がさらに長期にわたって年金を受けとることになる。……3つ目の、(「しかも」)これまでにない特徴とは、高齢化によって年金問題が発生するということである。われわれ全員が年金を受けとるというアイディアは社会にしっかりと根づいているが、実際には、これは最近になって発明されたアイディアである。かつては、就労者の大部分は退職を決断できなかった。その主な原因は、年金(存在していたとすれば)の受給額がわずかであったからだ。引退(退職)するとすれば、一般的には就労が不可能になったか、解雇されたかであった。だからこそ、1960年代までは、「超高齢」と貧困はほぼ同義であった。しかし、ここ25年で状況は様変わりした。高齢者の所得は上昇し、退職時期の年齢は下がった。大部分の先進国では、高齢者の貧困撲滅は、完全に現実的な見通しとなった」(105-106頁)。
「加速する高齢化、寛容な年金支給額、早期退職という状況下において、高齢者向け費用は増加の一途である。将来の退職者の安楽が、現在の退職者の安楽を下回ることを拒否するのであれば、年金の総支給額を約50%増やさなければならないだろう。ところが、こうした新たな負担を背負うことになる生産年齢人口の減少を忘れてはならない。(その上)年金負担額の増加に加え、われわれは高齢者の介護需要の増加に備えなければならない。というのは、80歳超の高齢者の人数が急速に増加するばかりでなく、家族という従来の非正規介護要員が消滅しつつあるからでもある。(中略)結局のところ、今後数十年で急増する高齢者向けの福祉費用はGDPの約10%に達することを、われわれは覚悟する必要がある。では、公平を担保しながら、こうした費用の急増に対して、どう対処したらよいのであろうか。これこそが、われわれが直面する挑戦である」(107頁)。
ここまで読んできて、私は、「高齢化」の意味を果たして野田政権は十分に理解しているのだろうか、ひょっとすると理解していないのではないのか、と思うようになった。別言すれば、野田政権の「政治的センス」の狭さに改めて思い及んだ次第である。野田政権は、われわれがしばしば目撃した自公政権時代―特に安倍内閣時代―の「年金問題の不明なる政策」も含めて、これまでの年金改革の政策には―アンデルセン教授が強調している言葉―「(年金)改革に正当性をもたらすためには、目指すべき改革は何よりもまず、公平の原則に基づいていなければならない」ことをしっかり認識していないのである。それだから、野田政権が「社会保障と税の一体改革」と言い張っても、われわれはそのスローガンを「社会保障と消費税の一体改悪」と正しくも言い換えるのである。アンデルセン教授が言うように、「高齢化自体は歴史上、新たな現象ではない」のであるが、これまでの「高齢化」とどこが違うのかと言えば、「年金問題が発生する」ということであり、また年金の他にも介護費用とそれに伴う医療費などを含めると近い将来における福祉費用がGDPの10%に達するとの予測は、日本においても遠からずして直面する経済-社会的な挑戦課題になることを示唆しているのであるから、われわれはそれらのことを今から社会的、国民的な議論に載せていかなければならないのである。ただしその際に注意すべきは、特に年金に関する議論については「一つの角度(歳入の面)だけから公的財源の問題を論じていると、われわれは誤った結論をくだす可能性がある」ということである。というのは、「(政府が)福祉に関する公約を果たすために、公的費用を金融商品(保険商品など)や家族支援に振り向けたからといって、財政に余裕が生じるわけではないからである。つまり、将来的に高齢者に注がれる公的資金は減るかもしれないが、それがGDPに占める割合は小さくはならない」からである(111頁)。
「レッスン3・高齢化と公平」の章には、「イントロダクション」の他に「世代間の公平」と「今日の子ども世代のための年金改革:世代間契約を超えて」があり、双方とも大変興味深い論考である。しかし、紙幅の都合で、本書の監修者である京極先生の「アンデルセンの福祉国家論と家族政策論について」と題する「解題」を援用させてもらいながら、それぞれ簡潔に言及していくことにする。
アンデルセン教授は、「高齢者の福祉を世代間で公平に分配するには、単なるマスグレイブの原則の年金への適用にとどまることなく、さらに人びとが『より長く働く』ことが求められる」として、こう論じる。「高齢化に対処するための群を抜いて最も効率的な政策とは、年金支給開始期の延期である。就職時期と平均寿命の長期化を考慮すると、この戦略は完全にマスグレイブのルールにあてはまる。つまり、年金支給開始期の延長は世代間の公平を保障 できる。OECDによると、10ヵ月の延期で財政上、年金費用の10%を削減できる」のである。ここに出てきた「マスグレイブの法則」あるいは「マスグレイブのルール」とは、「相対的な地位を固定する原則」のことであって、それを京極先生は次のように説明している。「従来の賦課方式で現役世代のみに追加費用金額の負担を課するシナリオを採用したり、逆に年金受給者の年金を引き下げて追加負担を高齢世代に課すシナリオを採用したりすることは、公平性の視点と副作用の点から、どちらもよくない」というものである。
アンデルセン教授はまた、「今日の子ども世代のための年金改革」を主張する。この主張は、単なる「世代間の公平」を超えた「年金改革」でもある。「正しい年金政策」は「現在の高齢世代はもちろん、現役世代の社会保障制度改革にとまらず、乳幼児から始めるべきだ」と彼は論じる。その主たる理由の一つは次のものである。「われわれが([脱工業社会における])知識経済へと移行すれば、学歴の低い者や認知能力が十分に備わっていない者は、低所得や雇用不安にさらされることになる。職業上の困難が老年期の貧困となって現れる確率は数十年後に高くなる」。したがって、われわれは「高齢者の安楽は、まずは本人のライフスタイルの結果であることを忘れてはならない。これは将来も同じである。ところで、個人のライフスタイルは、良くも悪くも、劇的変化に見舞われた。そして以前よりもかなり不均質になった。特に学習到達度、専門能力、能力全般から、職業上の成功を明確にしようという要求が高まっている。こうした資質は、かなり幼い時期に植えつけられる」からである。アンデルセン教授のこの「世代間を超えた年金改革案」は傾聴に値する、と私は思うが、どうだろうか。前号で述べたキース・フォークス教授の「市場から切り離された、社会的権利としての市民所得(ベーシック・インカム)」あるいは「社会的権利の脱商品化」という主張に近似している、と私には考えられるのである。
高年齢者(高齢者)の雇用・就労について
私が『季刊労働法』(No.236)の「高齢者雇用の課題を解く」と題する特集に拙論を載せるよう依頼されたのは、厚生労働省の「今後の高年齢者雇用に関する研究会」(座長・清家篤)が2011年6月20日にとりまとめ公表した報告書「生涯現役社会の実現に向けて」のなかに次のような一文が認(したた)められていたことによる。すなわち、高齢期は個々の労働者の意欲・体力等に個人差があり、また家族の介護を要する場合など家庭の状況等も異なることから、それらに応じて正社員以外の働き方や短時間・短日勤務やフレックス勤務を希望する者がいるなど、雇用就業形態や労働時間等のニーズが多様化している。このため、このような高年齢者の多様な雇用・就業ニーズに応じた環境整備を行うことにより雇用・就業機会を確保する必要がある。また、定年退職後の高年齢者は、生きがいや社会参加のために就業している者が多いことから、このような高年齢者のために雇用にこだわらない就業機会を確保することも重要である。
私は、この文章の特に後半部分に関連して書くよう依頼されたので、「高年齢者の雇用・就労と社会的企業」というタイトルでその依頼に応じた訳である。厚労省の研究会は、日本社会の少子高齢化に伴う「労働力人口の減少を跳ね返し、経済の活力を維持するためには、若者、女性、高年齢者など全ての人が可能な限り社会の支え手となることが必要である」とのコンセプトに基づいて、現在義務化されている定年年齢の「60歳定年」に達した高年齢者のうち雇用の継続を希望する全員に「65歳までの雇用」を確保することについて議論・検討してきたのであるが、それは公的年金の支給年齢を65歳に引き上げたことによるものであった。したがって、この報告書のポイントは「65歳以前に定年退職等により離職する場合に、年金支給開始年齢までの間に無年金・無収入となる者が生じることのないよう、雇用と年金を確実に接続させる必要がある」、ということなのである。
すぐ前で見たように、アンデルセン教授は「高齢者の福祉を世代間で公平に分配するには、……さらに人びとが『より長く働く』ことが求められる」とし、また「高齢化に対処するための群を抜いて最も効率的な政策とは、年金支給開始期の延期である」と主張している。アンデルセン教授のこのような観点からすれば、研究会の報告書のポイントは、それはそれで一応の筋道をつけているようである。しかし、問題もある。何故なら、年金支給開始年齢の引き上げと定年退職年齢の引き上げの組み合わせは、遅かれ早かれ限界にぶつかるからである。65歳を超えてなお働こう―しかも、「他人に雇われて働こう」―とする高年齢者(高齢者)が多数いるとは考えられない。いわんや70歳をや、ということになる。その意味で、年金問題は現状の若者、女性それに高年齢者(高齢者)の雇用・就業のあり方全体を構造的に捉え、改革しなければならないのである。不安定雇用の多数者を占めている若者や女性が安定した生活を送ることができ得る雇用の機会を創出する、公正な労働市場が求められる所以である。
ところで、研究会の報告書もそうであるが、日本では一般に、「雇用」とは主に「企業に雇われる」という意味での「雇用」であると想定されている。確かに、日本では「労働者」は「雇用主」に雇われている「被雇用者」(雇われている人)を意味するし、おそらく、労働基準法での「労働者」のコンセプトもそうであろう。労働者とは、企業であれ公務員であれ「雇用主に雇われている者」、すなわち「被雇用者」であり、被雇用者であることによって労働者はその地位を保護されるのである。言い換えれば、被雇用者としての労働者は間接的に労働者としての地位を保持されるのである。にもかかわらず―われわれ日本人は当たり前のように思っているのであるが―株式会社である企業の大多数の労働者はしばしば自らを「(会)社員」と称するのであるが、じつは、労働者が自らを「(会)社員」と称するのは一種の矛盾なのである。何故なら、株式会社の「社員」は本来、「株主」を意味するからである。それはさておき、したがって、ヨーロッパではしばしば目にし耳にする「自分で自分を雇用する労働者」という意味の「自己雇用」(Self-employment)というコンセプトは、日本ではほとんど馴染がないかもしれない。イギリスをはじめとするヨーロッパにおいて展開されているワーカーズコープ(worker's co-op)や社会的企業(social enterprise)が自己雇用の典型で、それらは地域コミュニティのさまざまなニーズを満たす事業を展開し、地域コミュニティに雇用を創り出し、したがってまた地域コミュニティの再生を図る活動に従事している。イギリスではこのような社会的企業が約6万2、000も存在していると言われている。
EU(ヨーロッパ連合)メンバー諸国のなかでも西・北ヨーロッパ諸国ではワーカーズコープも雇用の創出と地域コミュニティの再生に重要な役割を果たしている。とりわけ、スペイン・バスクの(4つのグループから成る120の協同組合の企業体である)モンドラゴン協同組合企業体(MCC)は工業、農業、漁業、住宅、小売り流通、金融(銀行、保険、社会保障)、教育(大学・大学院)などの各部門で8万4、000人の組合員・従業員を擁する大規模な事業を展開している(イギリス、フランス、メキシコなど海外に設立されている77の協同組合工場の従業員は含まれない)。また教育、保健・医療、農業、サービス、障害者の自立支援などさまざまな領域・分野で事業を展開し、雇用の創出と地域コミュニティの再生に貢献しているイタリアの社会的協同組合も大きな注目を集めている。
イギリス、フランス、イタリア、スペインそれにスウェーデンなどのヨーロッパ諸国の社会的企業やワーカーズコープが基本としている「自己雇用」のコンセプトは次のようである。すなわち、自己雇用とは、「雇う・雇われるという関係」を超えて、一人の事業者あるいは複数の共同事業者が「自治的で高い専門的資質を有する労働者」としてその能力を発揮し、地域コミュニティのニーズや(障害者の自立など)特別のニーズに応える労働(仕事)のあり方を意味する。したがって、自己雇用に求められる労働の革新性と労働の質は、その労働を遂行する労働者の専門的な資質と創造力に左右される。
さて、われわれは、このように「雇用」あるいは「雇用の機会」のコンセプトを広くかつ深く捉えることによって、アンデルセン教授が提案している「最低保障年金制度」に注目する必要がある。彼の「最低保障年金制度」は、先に触れた「今日の子ども世代のための年金改革」以上にフォークス教授の「市場から切り離された、社会的権利としての市民所得(ベーシック・インカム)」により近いかもしれないからである。アンデルセン教授の「最低保障年金制度」は、(「貧富の差」のために)年金支給開始期の延期によって公平性が脅かされる可能性があることから、年金制度の公平性を保つために「年金支給開始を各自の生涯所得によって決定する」というものである。われわれはこの「最低保障年金制度」に注目したいと思う。そこで最後に、アンデルセン教授の「最低保障年金制度」の導入理由を記して「理事長のページ」を閉じることにする。
ニューエコノミー(脱工業化社会における知識経済)がさらなる格差や機会不平等を生み出す恐れがあることから、将来の退職者は、年金受給権や貯蓄に関してもさらなる格差を強いられるだろう。そこで、すべての年金レジームは、すべての国民に対して国家財源による最低保障年金制度を構築する必要がある、という意見には正当性がある。民間の年金プランが増殖する一方で、将来の年金給付に関連した不安感は増すばかりである。これは全員を対象とした最低保障年金に賛成する2番目の議論である。最低保障年金支給額を貧困ラインよりほんの少し上に設定するのであれば、その費用は財政上、驚くほどわずかである。マイルズによると、最低保障年金を今日フランスで導入すると、公的財源に対する追加費用はGDPの0.07%に過ぎないと試算している(133-134頁)。
アンデルセン教授の社会生活全般における「公平」を旨とするこのような提案を日本のわれわれが受け入れるのには、フォークス教授の言う「シチズンシップ」の一層の広がりを必要とするであろう。その意味で、日本社会が「成熟」していくためには、「自治、権利、責任そして参加」というシチズンシップのコアをわれわれが自らの日常生活のなかに深く埋め込んでいくことが求められるのである。日本社会がシチズンシップをしっかり理解し認識し、それがわれわれ自身の生活の当然の基礎となるようになれば、「年金制度は『人間の尊厳』を追求する闘いでもあるのだ」ということをわれわれは難なく理解し認識するようになるだろう。
●理事長のページ(No.38)●2013年05月31日
少子高齢社会と雇用問題(1) 中川雄一郎
早いもので、5月も過ぎようとしている。まさに「少年老い易く、学成り難し」を地で行くようである。それ故、この老頭児(ロートル)にとっては「一寸の光陰、軽んずべからず」でなければならないのに、日頃の不摂生が祟(たた)って、5月初めのゴールデン・ウィークは床に臥せっていなければならなかった。風邪に罹ったのである。
これまでの私であれば、「風邪の前兆」が顔のどこかの部位に現れていたので、その時に市販の風邪薬を一服飲めばほとんど治っていたのであるが、今回はその「風邪の前兆」がどこにも現れなかったのである。私の「風邪の前兆」は、先ず「右あるいは左の頬の皮膚の一部が少しカサカサあるいはヒリヒリする」、次に「泪が出やすくなる」、そして「外耳のどこかの部位でキーンと神経に触るような痛さを覚える」、といった具合である。この3番目の「耳のどこかの神経に触ったような痛さ」が風邪に罹る直前の「前兆」なので、この時に医師に診てもらえば、本格的な風邪に罹らないのである。しかし、今回はこのような「風邪の前兆」もなしに風邪に罹ってしまったのである。
かくして私は、床に臥せってしまったのであるから、ロートルの私にできることと言えば、本を読むことと音楽を聴くこと位である。で、床に臥せって音楽を聴きながら思ったのであるが、最近のDVDは音質も良く、あたかも生演奏の如くに制作されているので聴き甲斐があり、したがって、最後まで聴いてしまい、なかなか眠りに入れないのが珠にきずなのである(因みに、私の最も気に入ったDVDは、伊藤恵のピアノによるロベルト・シューマン「子どもの情景・幻想曲Op.17・森の状景Op.82」である)。
これに対して、床に臥せって本を読むのはいささか疲れる。読み始めて20~30分もすると次第に眠くなってきて、やがて眼を擦るほどになり、そしていつの間にか目を瞑ってしまう。そしてハッと気づいて再び字面を追うが、読もうとする気が次第に失せていく。で、「20~30分睡眠をとり、眠気を追い払ってから読もう」と考えて本を置くや、そのまま深い眠りに入ってしまい2~3時間後に眼が開くのである。このような「眠気との闘い」が3日間続いたのである。
じつは私は、連休に入る直前に―朝日新聞の書評欄に掲載されていた―G・エスピン‐アンデルセンの『アンデルセン、福祉を語る:女性・子ども・高齢者』(京極高宣監修/林昌宏訳、NTT出版)を連休中に読もうと思って手に入れておいたのである。しかし、私の体調が上記のごとくであったので、それを読み終わったのは連休後数日経ってからである。
私が新聞の書評欄を見て直ぐこの本を読もうと思ったのには―後で言及するが―二つの理由があった。一つは、私が翻訳した『シチズンシップ』(日本経済評論社、2011)のなかで著者のキース・フォークスが彼の提起する「市民所得」(いわゆる「ベーシック・インカム」)について、エスピン‐アンデルセンの主張を採り入れていたからである。もう一つの理由は、先般、『季刊労働法236号』(2012年3月)に掲載された私の拙論に関係している。この季刊誌の【第2特集:高齢者雇用の課題を解く】に掲載された私の拙論のタイトル「高年齢者の雇用・就労と社会的企業」が示唆しているように、この拙論は、日本において喫緊の社会-経済的な問題となりつつある「年金受給年齢と定年退職年齢のギャップ」による高年齢者(高齢者)の雇用・就労に関わるそれである。
「市民所得」というコンセプト
前者について言及すると、次のようになる。先ずフォークスは、社会的権利としての「市民所得」とは「成人市民の雇用状況に関係なく、各成人市民に(おそらく、児童にはより低い率で)支払われることになる最低保証金額」であり、「この最低保証金額は事業体と個人に対する課税によって調達され」、その点で、この市民所得の第1の利点は「市民所得が普遍的な社会的権利である」ことなので、シチズンシップの向上・促進という観点からすれば、「市民所得の意義は、市民所得が所得と労働を切り離すというよりもむしろシチズンシップを市場の制約から自由にする」ということになる、と主張する。そして次に彼は、「社会的権利の重要な尺度は、それが人びとの生活水準を純然たる市場の力から切り離すことを可能にするその度合いでなければならない」と強調するアンデルセンの主張を紹介して、市民所得を「社会的権利の脱商品化」を可能とする政策だと論じるのである。フォークスは、このように論じることで、彼の「市民所得」を「労働市場の力」から引き離し、公共政策の目標を「市場に奉仕する社会的、経済的な政策」の立案ではなく、「適切で公正なシチズンシップを促進する諸条件を維持する」政策の立案に向かわせなければならない、と言うのである。
フォークスが「市民所得」というコンセプトを用いてどうしてこのような「シチズンシップ論」を投げかけたかと言えば、「コミュニティ(すなわち、政治)の義務はその構成員の基本的ニーズを満たすことである、とのことが認識されてはじめて市民所得が支払われる」ことを人びとが承認する必要性を強調したかったからであり、したがってまた、市民所得は「コミュニティ(政治)の優先権が市場のニーズではなく、その構成員の福祉にあることを明確に示すことで、この両者(すなわち、個人とコミュニティ)の関係の上に築かれる」ことの重要性を明示したかったからである。その意味で、市民所得は、「コミュニティ(政治)と個人の相互依存」と「個人の自治」の双方を認識させかつ高めていくことから、雇用パターンの変化と関係する他の社会的権利よりも明確な利点を持っていることを彼は訴えたかったのである。
そこで、フォークスのこのような主張とアンデルセンの主張がどこでどう繋がるのか、ということになる。その繋がりは『シチズンシップ』の次の件(くだり)を読めば理解できる。というのも、アンデルセンが「女性革命」あるいは「男性の女性化」を社会に訴えていることは周知のことだからである。
従来の社会的権利に関わる問題の一つは、社会的権利が労働(仕事)と密接に結びつけられているだけでなく、「有用な労働」があまりに狭く定義されていることでもある。このことは、女性が従来の福祉計画からどうしてわずかな給付金や手当しか受け取れなかったのか、その理由を部分的に語っている。女性が無償の家庭内労働と社会的ケアに費やす(男性とあまりに)不釣合いな時間数は、まったく正当に認識されないままに過小評価されてしまうのである。さらに言えば、女性は、労働市場の不平等な構造のために、所得に関連する給付金や手当を要求することに十分貢献できないでいるのである。……その点で、市民所得は、女性の社会的貢献を暗黙裡に認めることによって、多くの女性たちの運命をかなりの程度改善するであろう。また市民所得は、(女性が)政治活動や市民活動に参加するのに必要な時間を確保するために使われる大きな資力を女性に与えるであろう。さらに市民所得は、女性を、結婚しているか否か、性別あるいは家族関係といった観点からではなく、独立した、自律的な個人としてみなすであろう。一家の稼ぎ手としての夫たる男性一人が優位な地位を占めるような核家族がますます一般的ではなくなっていくにつれて、市民所得は家族構造の社会的変化に敏感に反応する社会政策になっていくのである(180頁)。
「女性革命」と「男性の女性化」というコンセプト
アンデルセンはフォークスによるこの件(くだり)の内容を次のように言い換えている―少々長い引用になるが、我慢して読み解いていただければ、「なるほど」と肯けるようになるだろう([]の言葉は中川による)。
女性革命は社会の基盤に根源的変化をもたらす。女性のライフスタイルは短期間のうちに信じられないほど激減した。変化に要した時間はほんの一世代([30年])である。戦後([第二次大戦後])数十年間の典型的女性像とは、主婦として家庭に納まることであったが、彼女らの娘の世代では、自ら働いて経済的自立を手に入れる生活を選択できる機会が増えた。この世代に急変をもたらした決定要因は、教育水準ときちんとした給与であった。こうした意味で、女性は自らのライフスタイルの選択において「男性化」を体験したのである。大部分の先進国では、今後、女性は男性よりも高い教育水準を得ることになる。いち早く女性革命が始まった北米や北欧では、出産による仕事の中断は最小限に抑えられ、女性の大半(ほぼ75%)は生涯にわたって職を持ち続けることになった。(中略)
女性のライフスタイルの変容は、良くも悪くも、著しい社会的「ドミノ現象」となった。夫は外で働いて稼ぎ、妻は主婦に納まる、という伝統的な家族形態はあっという間に凋落することになった。しかし、女性が新たな役割を得たことにともない、同じ社会階層に属する者同士の結婚は増え、第一子の出産時期は遅れ、出生率は人びとの希望よりかなり低くなり、夫婦仲は不安定となり、「変則的な」家族が増えた。ちなみに、こうした「変則的な」家族の多くは経済的に脆弱である。女性化傾向は長期的な人口推移に悪影響を及ぼす。社会が急速に高齢化するのは、女性革命の副産物といえよう。(中略)[だが]女性革命はいまだに未完成である。[それでも]女性革命がわれわれの福祉制度に深刻な挑戦状を叩きつけていることは想像に難くない。というのは、女性革命は福祉制度を機能させる柱の一つに根源的な影響をもたらしているからである。その柱とは家族である。
福祉国家に叩きつけられた挑戦状を解読するためには、福祉レジーム(広義の社会保障をめぐる基本的枠組み)という用語に検討を加えることが必要不可欠となる。社会と同様に、個人は家族・市場・公的社会給付を混ぜ合わせた福祉を得ている。しかし、大部分の人びとにとって主要な福祉の源泉は、家族と市場である。つまり、われわれは主に市場を通じて所得を得ており、一般的にわれわれの家族がわれわれを社会的に支援している。ライフサイクルの観点からすると、福祉国家が市場や家族を超えて、本当にわれわれを支援するのは、われわれの幼年期と老年期だけである。
こうした福祉の三つの柱は総合に影響を及ぼし合っている。市場が失敗する場合、われわれは家族と行政サービスで我慢する[実際には、価格や情報の非対称化のために、われわれは市場によってわれわれの基本的要求をしっかり満たすことはできない]。医療[サービス]や教育サービスは、市場化の失敗という古典的な例証となっているが、女性革命により、さらに二つ要求が浮上してきた。すなわち、乳幼児の保育と高齢者介護の問題である。……民間ケアサービスを享受できるのは、ある程度裕福な世帯のみである。同様に、家族が失敗する場合には、われわれは市場や行政を頼みとすることになる。これまで女性に割り当てられてきた介護の役割から女性が身を引くようになり、また親世代と同居することがなくなると、家族の「失敗」は増加する。したがって、市場または家族によっても、われわれの社会的要求には適切に対応できていないという点において、現代社会には失敗が蓄積しているといえよう。高齢者介護問題がまさにその例証である。……[こうして]皮肉なことに、家族主義政策にしがみつくことで、社会福祉の対象から外された領域は拡大する一方である。(中略)
こうして、ほとんどの先進国社会では、採用する政策が女性革命にきちんと対応してこなかったことから、社会の不均衡が拡大していった。家族主義に基づいた社会政策が家族の形成を妨げているというのが、われわれの時代のパラドクスである。合計特殊出生率の激減、特に教育水準の高い女性の間で子どもを産まない女性が急増したという事態は、ヨーロッパの大部分で観察されているが、これは保育サービスの不在と関連がある。(中略)
家族政策を再考する必要性があるのは明らかである。育児に関する福祉の機能を「脱家族化」させない限り、育児と仕事の両立を図ることはできない。低い合計特殊出生率は、子どもが欲しくないという人びとの意思の表れではなく、むしろ彼[・彼女]らにのしかかる重圧が高まったと解釈できるのではないだろうか。家族は今後も社会のカギとなる制度であり続けることから、家族を支援する政策を打ち出すことが必要となってくる。また家族は、ますます多様化していくが、子どもの幸せにとっても必要不可欠である。[それ故]子どもを経済的窮乏から保護する政策が必要不可欠となってくる。……われわれは子どもにかかるコストと、子どもが社会にもたらす利益の公平な分配を構想する必要がある。(中略)
[少子化]政策を実行するうえで、われわれは少子化の背後に隠れたものを突き止めなければならない。これまでの少子化対策は二つの要因を強調してきた。第一に、子どもをつくるという決定にあたっては、世帯主(父親)の所得に依存するという点。第二に、女性の生涯所得という観点から、女性にとって出産が重要な機会費用(女性が出産のために仕事を犠牲にすることで失う所得など)をともなうのであれば、女性の産む子どもの数は減るという点である。……しかし、現代社会においては、こうした説明では不十分である。各国のデータを分析してまず分かることは、就労率と合計特殊出生率との間で、今後は相関関係が成り立つということである。女性の就労が広範囲に普及した国では合計特殊出生率は最も高い。この逆もまた真なりである。(中略)
現代において、合計特殊出生率のカギは女性の新たな役割にあり、特に女性の生涯を通じた職業の選択にある。これはすべての研究者の一致した見方である。職業キャリアは必ずしも出産と両立しない訳ではないことは、北欧諸国が例証している。したがって、女性の就労を思い止まらせる少子化対策では、いずれ重大な副作用を引き起こすであろう。……貧困は子どもの発達にきわめて有害である。母親が就労している場合は貧困に陥ることが少ないことから、子どもの貧困も減る。また母親の就労には他にも大きな効用がある。高齢化社会の財源確保である。そのためにも、女性の就労率を最大限に引き上げる必要がある。……したがって、少子化対策は女性の新たな役割を考慮に入れて実行する必要がある。合計特殊出生率に関して、女性の決断と夫の所得の繋がりは薄れている。今後、合計特殊出生率は、主に女性が労働市場に安定的に地歩を固めることができるか、という能力に左右される。(中略)
われわれの目的が仕事と育児の両立を最大限に支援することであるとすれば、この両立という問題の二面性を考慮すると、デンマークの政策がベストということになる。第一のポイントとして、デンマークの政策はすべての小さな子どもを持つ母親に就労継続の可能性を保障している。デンマークの母親の就労率は78%である(フランスは63%)。また研究者によると、母親の生涯獲得所得に対する影響も比較的軽微であるという。これは主に、産休後にほとんどすべての女性が復職しているからである。第二のポイントは、保育サービスの利用がほぼ普遍化していることである。最新の公式な推定値によれば、一歳児から二歳児の保育サービスの利用は85%であるという。(中略)
女性革命が未完であるのだとすれば、それは女性のライフスタイルにおいて女性が「男性化」したほどに、男性のライフスタイルが「女性化」していないからでもある。[それでも]男性のライフスタイルに目を向けると、かなり大きな変化が確認できる。アンケート調査によると、男性における家事参加がここ10年から20年の間に急上昇した。……[このように]こうした傾向には著しいものがあるが、革命的とまでは言えない。家事・育児に関する男女間の隔たりは依然として大きい。……男性の家事・育児への参加は社会階層によって大きく異なっている。というのは、男性の家事・育児への参加が増えているのは、家庭内において女性が強い権力(権限)をもつ世帯や、高学歴の男性の場合であるからだ。最も学歴の高い男性と最も学歴の低い男性の育児への関わり方の違いから、格差が生じているし、この格差は拡大する一方である。つまり、男性のライフスタイルが女性化することは、主に社会階層のトップに関する話なのである。
男女間の対称性は社会行動においてさらに大きな役割を演じている。すなわち、夫の参加の度合いが働く女性の合計特殊出生率の決定要因なのである。また夫の家事・育児に対する貢献は、別居や離婚のリスクを軽減することも分かっている。(中略)
経済的自立を手に入れ、そして子どもを持つ女性の願望は、私的利益ばかりではなく、コミュニティに大きな価値を生み出す。これは公共政策を打ち出す際の論拠でもある。両親の出産休暇、育児、高齢者介護に関する福祉国家の役割は単純で、主にこうした福祉政策にかかる費用と、それがもたらす便益が問題となる。しかし、家族間の不平等がバランスのとれた社会を目指す上で大きな障害となっているとすれば、福祉国家としては何をなすべきであろうか。……[それ故]だからこそ、われわれはカギを握る経済的インセンティヴや社会的拘束を突き止める必要があるのだ。
シチズンシップ論を基礎とするキース・フォークスの「市民所得」を、社会福祉政策論を基礎とするエスピン‐アンデルセンの「福祉社会」をもって具体的に論及すると、このように長丁場になってしまう。それでも、私としては「シチズンシップと福祉社会」を結びつけるカギを見いだした思いがして、ある種の研究の広がりを覚えたような心境に至っている。ところで、もう一つの私の「拙論」についてであるが、これについては、紙幅の都合で次回の「理事長のページ」で多少詳しく述べることにさせていただくことにする。
●理事長のページ(No.37)●2012年02月29日
「無言国ニッポン」の深層心理 中川雄一郎
先般、朝日新聞の「声」欄(「無言国ニッポン」)に載っていた二つの投書に興味を覚えた(2012年2月17日付朝刊)。一つは「ひと声かければすむものを」と題する84歳の男性の投書である。もう一つは「『こんにちは』は客から言おう」と題する13歳の少年の投書である。
前者の内容はこうである。電車が駅に止まると、降りる人は「あたふたと、ひたすら前の人をかき分けて扉に向かう。ものも言わずに」。「ちょっとごめん」とか「降ります」とか、何でもよいから声をかければ楽に降りられると思うのだが、黙って降りようとする。また混んでいる回転寿司屋でも「横の男性の腕が私の前にニューッと突き出てくる。醤油差しを取ったのだ」。ひと言「失礼」と言って取ればすむのに。「そうすれば『どうぞ』と私が返す。それだけのことなのに、無言国ニッポン、嗚呼……」。
後者はこう書いている。父親の仕事の関係で約7年間フランスに滞在し、1年ほど前に帰国したばかりで、「フランスの習慣」がまだ抜けていない。「フランスでは、買い物でお店に入る時に『こんにちは』と挨拶するのが当たり前でした」ので、「日本で先日、コンビニに行き、僕はいつも通り『こんにちは』と言って店に入りました」が、一緒にいた母親に「恥ずかしいからやめなさい」と小声で注意されてしまった。以前から「周りの人が何も言わずに店に入るのに気づいていましたが、僕は、こういう場合、日本では挨拶しないということを改めて知りました。 後から自分が恥ずかしいことをしたのではないかと不安になりました」。(そして少年はこう続ける)「それにしても、日本ではなぜ、お客は挨拶しないのでしょう。僕はすべきだと思います。その方が気持ちよく買い物ができそうです。『客と店員』である前に『人と人』として挨拶できる国になってほしいです」。
両者の投書も日常的にわれわれ「日本人」が目撃している―しかし、最近頓とみに不思議に思われなくなってしまった―生活の一コマである。前者は、(投稿者が「東京都府中市」在住なので)特に東京や横浜、それに名古屋や大阪などの大都会でしばしば目にする一コマであるかもしれない。私は時々地方都市に所用で出かけるが、このような場面に遭遇した経験はほとんどないからである。それにしても、このような「無言状態」が日常的に見られるようになったのは、いつ頃からだろうか。
後者の「客と店員」である前に「人と人」として挨拶すべきだとの少年の思いは、最近の日本に見られる経済・政治・社会の利己的現象に向けられているように私には思える。最近の日本社会は「公」(公的領域)と「私」(私的領域)の分割を当然のように思わせる状況が続いている。少年の「『客と店員』である前に『人と人』として挨拶すべき」という思いは、「公と私の分割は当然のことなのですか」と問うているのである。これについては後で言及する。それにしても、われわれは家庭でも、民間企業、居酒屋、レストラン、学校、病院、裁判所それに役所といった事業体や組織それに公的機関においても「挨拶」無しではすまされないだろう。それが何故、「客と店員」の場合には「挨拶」が「恥ずかしい」ことになってしまうのか。そう考えた少年の素朴な疑問は正しい疑問ではないだろうか。
両者の投書を読んですぐ思い浮かんだ言葉がある。新約聖書の「マタイによる福音書4章」に出てくる「イエスの言葉」である。聖書では「40日40夜、断食をし、空腹になられた」イエスが、悪魔に「もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてみよ」と言われ、「人はパンだけで生きるものではなく、神の口から発する一語一語の言葉で生きるものである。」(Man shall not live by bread alone、 but by every word that proceeds from the mouth of God.)と答えた、この「人はパンのみに生きるにあらず」、である。
私はここ20年ほぼ毎年ヨーロッパの国々、特にイギリスにおける協同組合や社会的企業それに他の非営利・協同組織を訪問・調査してきたこともあって、ヨーロッパの人たちが日常の生活で交(かわ)し合う挨拶については周知している。スーパーマーケットでも町の店舗でも、客と店員が「ハロー」と挨拶を交わしてからお喋りするのも、また知り合いの客同士が挨拶を交わしてお喋りするのも当たり前のことなのである。そして勘定がすめば客は「サンキュー」と言い、レジの店員は「サンキュー・バァーイ(バイバイ)」と言い返してくれる。客が店員に挨拶するのは当たり前のことではないか、との少年の主張はまったく正しいのである(挨拶せず、お喋りもしない日本の客がおかしいのである)。
私の経験を記しておこう。私は家族と共にイギリスのブラッドフォード市の郊外に家を借りて、1985~86年のおよそ1年間をそこで過ごした。近所の人たちは親切で、私たち家族のために買い物、クリニック、ごみの集配、ガス・水道の修理、図書館案内、バス・鉄道の乗り方、公園、家族旅行、それに息子と娘の学校生活などいろいろ世話を焼いてくださった。本当に助かった。何しろ私たちは初めて海外に出て海外で生活したのだから。私たち家族が住んでいた家から徒歩で5分ともかからない所に息子と娘が通う小学校があり、その隣りに2階建て高齢者住宅があった。その高齢者住宅の住民は、天気の良い午前中に小学校沿いの歩道のベンチに座って子どもたちや通行人にこのように声をかけるのだ:lovely day、 isn't it ?(いいお天気ですね。)最初私は、見ず知らずのおばあさん・おじいさんたちだったので、私ではなく誰か別の人に挨拶をしているのかと思って黙って通りすごそうとしたが、次のおばあさんが同じように「いいお天気ですね」と挨拶する。振り向くとそこを歩いているのは私ただ一人、つまり私に挨拶していたのである。「見知らぬ人に挨拶することに不慣れな日本人」の私も気づいて、Yes、 lovely、 good morning to you と挨拶を返した。それからは天気の良い午前中の挨拶はhelloやmorning、時にlovely weatherとなり、私たち家族が日本人であること知ったおばあさん・おじいさんたちは日本のことにいささか興味を持ったようだった(その地域コミュニティに住んでいる日本人は私たち家族だけだった)。こんな簡単な、しかし、心温かい言葉が仲介して私たちは会話を交わすようになっていったのである。
さて、このような私の小さな経験を振り返ってみただけでも、先ほどの「イエスの言葉」は、「無言国ニッポン」という現状の背後にいかに社会的に重大な問題が潜んでいるかを思わせるに十分な現象である、と私には思える。イエスの言葉を私なりに言い換えれば、こうなるであろう。「人間は言葉によって人間本来の関係を創りだし、人間の本来的な要求を満たしていくのだ」、と。したがって、言葉で生きているはずの日本人の口から「こんにちは」の挨拶や「ちょっとごめん」・「失礼」の声かけが次第に出てこなくなっているのは、日本社会のどこかが「病んでいる」からだと私は診断している。そうであるのなら、何らかの症状が現れているはずである。その症状が「無言国ニッポン症候群」である、と私は言いたいのである。
私の個人的な経験を含めて、この症候群が大都市を中心に伝染していったのは、自公連立の小泉政権(2001年4月~06年9月)が、金融市場と労働市場を中心にさまざまな部門において可能な限りの規制緩和を実施して、働けど働けど貧困から抜け出せない「ワーキング・プワー」(working poor)を生みだした新自由主義政策=「小さな政府」を遂行し、その結果を「自己責任」という言葉でいとも簡単に括ってしまい、ついに人びとの間に二重三重の「新たな格差」が広がっていくのを許してしまってからではないか、と私は考えている。新自由主義政策のイデオロギーはあのハイエクの言葉から察しがつく。すなわち、「私的領域の不平等は免れ難いし、むしろ好ましいことでもある。民主主義は、精々のところ、市場の力によって決定することができない生活の領分に厳格に限定されるべき功利主義の装置である」。もう一人の、新自由主義に凝り固まった人物R.ノージックに至ってはどう仕様も無い。彼はこう言うのである。「民主的なシチズンシップの行使を通じて社会的正義・公正を追求するいかなる試みも市民権の侵害である。したがって、国家(政府)は、最も目立たないが実行可能な方法で安全を用立てる夜警として行動すればよいのである。国家はその市民の物質的な福祉に関与すべきではない。何故なら、国家が物質的な福祉に関与することは、市場によって最適に決定される資源の配分に国家が干渉することを必然的に意味するからである」。当時の小泉首相も竹中平蔵大臣もハイエクとノージックと似たり寄ったりである。要するに、「市場の力」がすべてであるのだから、その結果は「自己責任」ということになるのである。
「無言国ニッポン症候群」の伝染因子が明らかになったのは2004年の「イラクで人質になった日本人3名に対する(多数派の)日本人による激しいバッシング」であった、と指摘しておく。これは政治的にも社会的にも激しいバッシングであって、まさに「究極の自己責任」を問う恐怖感を日本社会全体に与えたのである。欧米人から見ても、この恐怖感は実に異常なものに映った。シカゴ大学のノーマン・フィールド教授(当時)はこの異常さを次のように語っている(朝日新聞2005年8月17日付朝刊)。「日本人は今、他人や社会の出来事との関係を拒否することが新種のアイデンティティになっていないか」。「(日本の)国民の圧倒的多数が、自分は経済的成功を遂げた国家の一員だと信じる社会、日本の国民的アイデンティティの核を作ってきたこの意識は、バブル崩壊後も生き続けている。日常に潜む抑圧を告発する個人は、この多数派から『私は黙ってこの日常を生きているのに』との迷惑意識を向けられる」。「イラクで人質となった3人へのバッシングもそうだ。3人は身近でないイラク人に共感し、個人として行動した。それは、無意識の日常生活を生きたい人びとには迷惑なことだったのである」。
「日本国民の圧倒的多数派」は今もなお、「(日本社会の)日常に潜む抑圧を告発することは迷惑だ」、「黙って日常生活を生きていこう」と考えているのだろうか。福島原発事故を受けた「脱原発」を考えることもなく、また戦後67年にもなろうとしているのに、米軍基地が「独立国ニッポン」にかくも多数存在し、しかもその70%が沖縄にあるような「世界的に異常な状態」を許しておいて、「無意識の日常生活を生きたい」などと国民の多数派は考えているのだろうか。「イエスの言葉」は「沈黙してはならない」と言っているのに。
ヘーゲルは、市民のステータスであるシチズンシップは「(市民自らが)自分自身の生活について判断を下す能力があることを承認する」のであるから、そのような能力を有する人間としての市民は、「自治・権利・責任・参加」を遂行することを通じて、「他のどんなアイデンティティよりも人間の基本的な政治的欲求を充足させることができる」と考えた。ヘーゲルはそれを「承認の必要性」と称した。ヘーゲルの言う「承認の必要性」とはこうである。「個人は自らが他者によって承認されることではじめて幸福に導かれる」とする「承認を求める闘い」を行う。「承認を求める闘い」は「人びとの平等な尊厳を求める闘い」であり、この闘いによって「対等平等な人びとの間での相互の承認」のための秩序が創りだされる、と。脱原発も米軍基地撤去もシチズンシップの範囲であり、「イエスの言葉」を以て脱原発と米軍基地撤去を主張しなければならないのである。
最後に、「無言国ニッポン」に反対する少年が訴えている「公と私の分割」について言及しておこう。「公と私の分割」は男女の中立性を意味しない。このことをまず理解しておこう。事実、私的領域での「自由」は男女間の不平等な関係に基づいているからである。一般に、家族という私的領域における女性のステータスは、公的領域における女性のステータスと同じように、夫という男性のステータスに本来的に従属している、とみなされているし、ましてや家父長的な社会にあっては、女性はシチズンシップを行使する能力のある合理的な政治的行為者ではない、とみなされてしまう。これを現代の文脈から言えば、男性は政治的および経済的行為者とみなされるのに対し、女性は市民というよりもむしろケアラー(家族の世話係・介護者)とみなされてしまうのである。このはなはだしい不平等を自由主義はまったく正当化できない。何故なら、シチズンシップは、自由主義の伝統にあっては、何よりも「一連の個人的権利」だと定義され、そしてそれらの個人的権利を有することは個々人が「自治」を有することを意味することとされて、権利は個人の利益を生みだし、他の個人やコミュニティ全体による干渉を受けることなく個人の潜在能力を引き出す「生活空間」を個人に与えるのであると考えられているからである。この自由主義のロジックは、かつては男性のためのロジックであったが、現代は「男女の不平等」のロジックとみなされるようになっているのである。
それ故、シチズンシップが女性にとってより大きな意味を持つためには、シチズンシップの「平等主義の価値」がどうすれば私的領域の個人関係にも適応されるようになるのか、また子どもや他の扶養家族へのケアの不平等で一方的な負担が女性の肩にかからないようにして、どうすれば女性が市民として十分に社会的な参加ができるよう諸資源を手に入れ、それらを利用できるようになるのか、という問題にわれわれは取り組まなければならないのである。しかし同時に、決定的に重要なことは、自由主義の伝統の中心をなす「平等」という理想が女性の自立の機会を広げてくれる推進力を女性に与えること、これである。こうして、現代では、「公と私の分割」は「男女の中立性を保持する」というロジックそのものを滑稽なものにしているのであるから、公的領域においても私的領域においても男女の平等を実現する諸条件や枠組みをわれわれは再生産していかなければならないのである。
さて、「公と私の分割」がどうして「無言国ニッポン症候群」と結びつくのか、という問題に移ろう。ここでは、二つのことが問題になる。一つは、「自由主義の危機」に関わる点である。これは、自由主義者がシチズンシップの「責任履行能力」を無視あるいは軽視していることと関連する。ダニエル・ベルが主張しているように、新自由主義政策を許してきた資本主義が直面している「経済的ジレンマは、われわれが俗物的欲求を是としてきた事実の結果である。この俗物的欲求は、道徳的見地に立とうが税を課せられようが、欲深さを抑えることに抵抗するのである」。要するにこれは、「自由主義という名の個人主義」であって、この個人主義は「民主主義やシチズンシップに対して自分本位の態度や道具主義的な態度を助長してきたのであって、民主主義やシチズンシップを共同生活の表現としてみなすのではなく、自己の利益を促す方法としてみなすのである。権利は大いに要求するが、責任はまったく受け入れないのである」。新自由主義的資本主義の人間像は、民主主義やシチズンシップに対して自分本位あるいは道具主義の態度を取り、また民主主義やシチズンシップを人びとの「共同生活の表現」とみなさずに「自己利益を促す方法」とみなし、かつ「権利は大いに要求する」が「責任はまったく受け入れない」という「自由が勝手気ままに変異する」ことを最善とする人間像なのである。丁度あの「橋下徹とその仲間」のように、である。他者の尊厳を無視あるいは軽視する、他者への配慮を欠く社会的な空気が「無言国ニッポン症候群」をつくりだす因子になっているのである。
もう一つは、「俗物的欲求」や「欲深さ」とも関連するが、「責任」を「自治の条件」とみなさず、単純に「自由の侵害」とみなす傾向の強まりである。これは、「権利の行使と責任の履行は相補的な関係にある」という事実を市民が理解しなければ、社会秩序や社会規律に対する権利の重要性が見失われてしまい、その結果、「権利は絶対的なものである」との主張を許してしまう危険性が生まれてしまう、ということである。じつは、「無言国ニッポン症候群」の因子の一つは、この「権利と責任」が相補的な関係にあるのではなく、対立的な関係にあると人びとに思わせている社会的な空気だと言えるのである。
俗物的欲求や欲深さを正当化する新自由主義者は「人間の行動について単純で割り切った考え方をする」ので、「権利を行使する能力の不平等が現に果たしている役割」について真剣に考察することなくあしらってしまう。したがって、新自由主義者は「社会に対する義務や責務(責任)の意識が欠けていることの問題をより広い範囲に及ぶ社会的な問題の一つの側面だとみなすのではなく、個人としての弱点や欠点の問題だとみなし、したがってまた、シチズンシップの遂行を妨げている本当の障害物である制度や機関や機構―主に排他的な政府・国家や市場の不平等―を無批判的に受け入れる」のである。このような誤った判断は「問題の根本に手をつけないままさらなる不平等を生みだすような政策を先導してしまう」のである。「橋下徹とその仲間」が喧伝している政策は、まさに権利の一層の充実を求めている「弱い立場の人たちにとっての自由」に対する脅威と言うべきである。何故なら、「橋下徹とその仲間」は「権利の縮小」と「新しい権利の停止」を擁護しているからである。私は思うのだが、「橋下徹とその仲間」は、少子高齢社会やジェネレーション・ギャップの可能性といった日本社会の現況を(政治的に)目前にすると、「伝統的な家族構造への回帰」や「ケアラー(世話係・介護者)としての女性と活動的で積極的な市民としての男性」という分裂を再現する恐れが大いにあるだろう。イギリス保守党の「鉄の女」と褒めそやされたサッチャー元首相は1988年5月に―自分は他の一般的な女性とは違うステータスにあるので、とわざわざ断って―スコットランド国教会長老派総会でこう演説した。「イギリスには社会というようなものは存在しません。存在するのは個人の男女、それに家族なのです。」(There is no such thing as society in Britain. There are individual men and women、 and there are families.)ミセス・サッチャーは「あなた方市民は経済的、社会的、政治的な諸結果すべてを『自己責任』として受け止め、対処しなければなりませんよ。何故なら、イギリスには社会というようなものがないからよ」、とそう主張したのである。これが多くの市民、とりわけ女性の怒りを呼んでしまったことは言うまでもない。
われわれは、シチズンシップの意識を高めていくのに権利が果たす役割の重要性を承認しなければならない。われわれはまた、権利はガバナンスの問題、すなわち、公正な資源配分や社会の秩序や規律の維持といった問題を成功裡に解決するのに決定的に重要であることも承認しなければならない。この「権利の重要性」は、「権利こそ政治的行動の延長線上にあること、また権利こそ敬意をもって個人を思いやるのに値するものだと明確に理解すること」を意味している。権利は正義と公正の原則に従って、またコミュニティの各メンバーのステータスは平等であるという認識に従って、資源を配分する一つの方法として測り知れない価値を有していること、さらに権利には社会的な安定を持続させるのに果たすべき重要な役割があることを市民は承認しなければならないのである。
最後に、「無言国ニッポン」を優しく告発してくれた84歳と13歳の二人の市民にキース・フォークスの次の言葉を送りたい。
人間は多様でありまた創造的であるのだから、人と人との対立は避けることができない。だがこの対立は、しばしば非常に生産的であって、しかも必ずしも激しい感情や言葉(あるいは暴力行為)を伴うものではない。実際、シチズンシップがその一部を成している政治のまさにその目的は、妥協や歩み寄りを通じて紛争や争議を解決することである。権利が社会的な対立を解決するのに重要な役割を果たすのは、個人は一人ひとりが最大の尊敬を払われなければならず、他者の目的のための単なる手段だとみなされてはならない、ということを権利が人びとをして想い起させるからである。
《別のページへもどる――2006年10月31日~2011年12月10日》
『いのちとくらし研究所報』(非営利・協同総合研究所いのちとくらし)への執筆 (本文下線がある論文・エッセイはPDFで読めます)
中川雄一郎のページ(現在、理事長)
『レイドロー報告』30周年、中川雄一郎、非営利・協同総合研究所いのちとくらし所報、No.29、 2010.02.20
日本協同組合学会第30回大会とレイドロー報告、中川雄一郎、非営利・協同総合研究所いのちとくらし所報、No.32、 2010.10.31
シリーズ『非営利・協同Q&A』誌上コメント(その4、最終回)、出席者:富沢賢治(研究所顧問、聖学院大学大学院教授)、中川雄一郎(研究所理事長、明治大学教授)、坂根利幸(研究所副理事長、公認会計士)、角瀬保雄(研究所名誉理事長・顧問、法政大学名誉教授)、司会:石塚秀雄(研究所主任研究員)、非営利・協同総合研究所いのちとくらし所報、No.36、 2011.02.28
新着情報news
- 2014年03月29日
- 総研いのちとくらし『研究所ニュース』の「理事長のページ」をUP。
- 2013年09月01日
- 「日英社会的企業比較研究センター」のホームページUP。
中川雄一郎

明治大学名誉教授
非営利・協同総合研究所いのちとくらし理事長
◇非営利・協同総研いのちとくらし『研究所ニュース』の「理事長のページ」。(下線部リンク先へ)
▼2014年09月01日~2016年12月10日
▼2012年02月29日~2014年05月31日
▼2006年10月31日~2011年12月10日―別のページ
◇『協同の発見』への寄稿一覧
![]()
編集人:飯島信吾
ブログ:ある編集者のブログ
UP 2012年10月07日
更新 2012年10月21日
更新 2012年10月24日
更新 2012年10月31日
更新 2012年11月04日
更新 2012年11月15日
更新 2012年11月23日
更新 2012年12月20日
更新 2013年01月10日
更新 2013年02月18日
更新 2013年03月14日
リニューアル更新
2014年03月10日
更新 2014年03月29日
更新 2014年06月08日
更新 2014年06月20日
更新 2015年09月15日
更新 2015年12月07日
更新 2015年12月20日
更新 2016年03月27日
更新 2017年04月15日